6割が経験「夏バテ」、実は生活習慣で防げる——医師が語る予防と回復のヒント
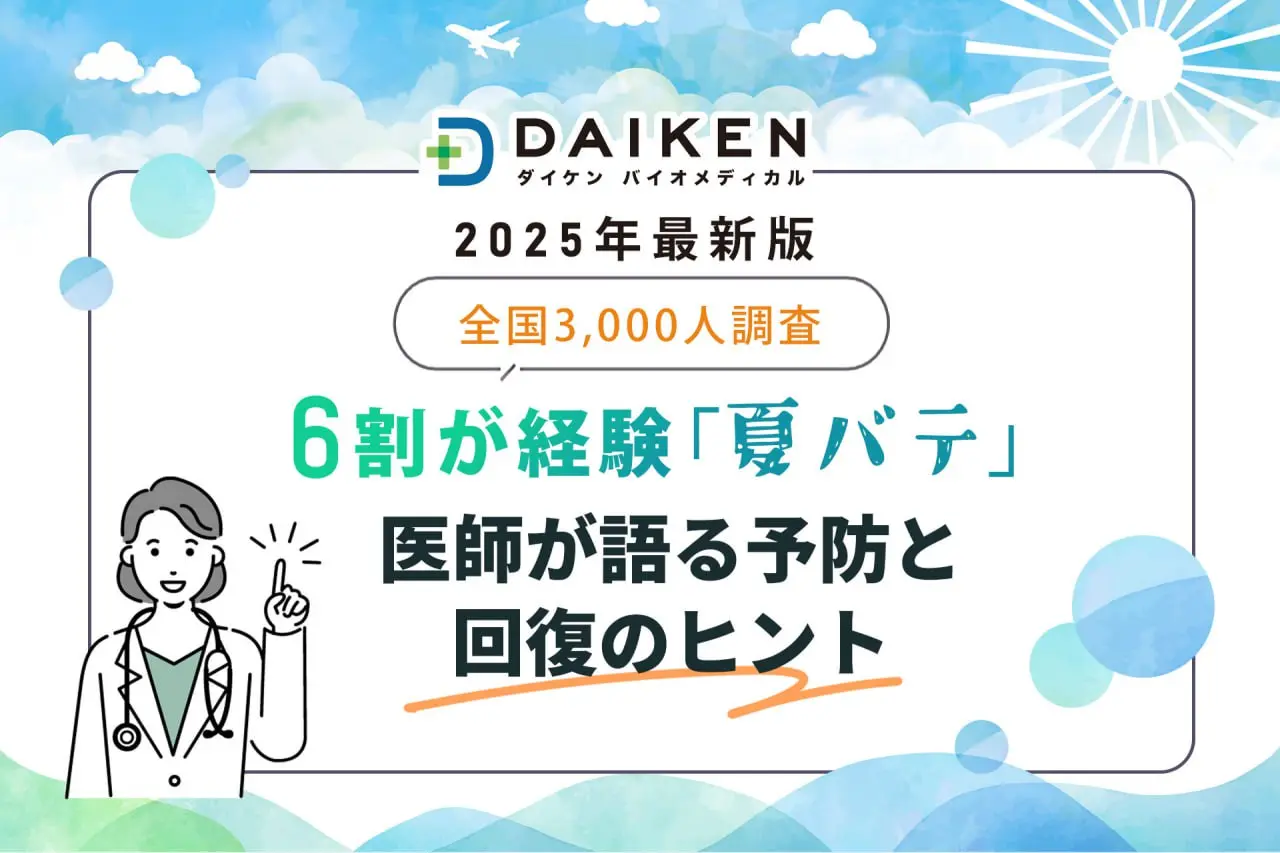
全国3,000人調査で明らかに——最多症状は「食欲不振」「倦怠感」、医師コメント付きで夏バテ対策を解説
日本製の健康食品の開発・販売を手がける大研バイオメディカル株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役:林東慶)は、「夏バテの症状と対策」に関するアンケート調査を実施しました。
本調査は、全国の3,000名を対象に「夏バテを経験したことがあるか」を尋ねた一次調査(事前調査)と、夏バテを「経験したことがある」と回答した58%の中から1,000名を抽出して実施した二次調査(本調査)の二段階構成で行いました。
さらに今回、夏バテの予防・回復に役立つ具体的な対策について、鎌田百合医師のコメントも交えて紹介します。
■調査概要
調査名:夏バテに関する調査
調査期間:2025年6月27日〜30日
調査方法:クロスマーケティング社のQiQUMOを使用したインターネット調査
調査対象:
事前調査:全国の15歳以上の男女3,000名
本調査:「夏バテを経験したことがある」と回答した1,746名のうち1,000名を対象に実施
■6割が夏バテを経験、最も多い症状は「食欲不振」「倦怠感」
Q0. あなたはこれまでに「夏バテ」を経験したことがありますか?

事前調査の結果、全体の58.2%が「夏バテを経験したことがある」と回答しました。
続いて、
Q1. あなたが「夏バテになった」と感じるのはどのような時ですか?

という設問に対して、具体的な症状として最も多かったのは「疲労感・倦怠感」(596件)、次いで「食欲不振」(573件)、「胃腸の不調」(262件)、「睡眠の質が落ちる」などが続きました。
これらの結果から、夏バテは単なる“だるさ”ではなく、食事・睡眠・内臓機能など生活の基本に広く影響を及ぼす状態であることがわかります。
また、「頭痛」「めまい・立ちくらみ」といった症状も複数挙がっており、放置すれば日常生活に支障が出る可能性もあります。
■夏バテ対策、上位は「水分補給」「冷房使用」 一方で“無対策”も1割
Q2. 夏バテ対策として、あなたが実際に行っていることを教えてください。

夏バテ対策として実際に行っていることを尋ねたところ、最も多かったのは「水分や塩分を意識してとる」(654件)、続いて「冷房を適切に使う」(609件)、「しっかり睡眠をとる」(445件)、「栄養バランスのとれた食事」(348件)といった生活習慣の見直しによるセルフケアが上位を占めました。
一方で、「特に何もしていない」と回答した人も約1割(98件)にのぼり、夏バテを感じていても有効な対策を取れていない層が一定数いることも明らかに。
さらに、「サプリメントや健康食品で栄養を補給している」と回答した人は114件とまだ一部にとどまっているものの、暑さによる食欲低下で不足しがちな栄養素を“補助的に摂る”という選択肢も少しずつ広がりつつあります。
このように、夏バテを自覚しながらも、十分な対策を講じていない人が多い一方で、具体的な方法がわからないという声も少なくありません。
そこで今回、内科医の鎌田百合先生に、夏バテのメカニズムとともに、日常生活で実践できる予防・回復のポイントをわかりやすく解説していただきました。

<夏バテ対策を心がけよう>
夏バテとは、高温・多湿の気候に体が対応できずに現れるさまざまな症状をいいます。夏は室内と室外の温度差によって自律神経に乱れが生じます。自律神経の不調によって食欲もなくなり、疲れ、集中力の低下などが起こり体調を崩しやすくなります。今回のアンケートでも、疲労感・倦怠感や食欲の低下は高い頻度でみられていますね。
実は、夏バテは適切な対策で防ぐことができます。夏バテ対策のポイントは、生活習慣や環境の改善です。この機会に普段の生活を見直し、できることから実践してみましょう。
・体の冷やし過ぎに注意する
室内外の温度差が大きいほど、自律神経が乱れやすくなります。エアコンは快適に夏を乗り切るために必要な設備ですが、冷やしすぎには注意が必要です。エアコンの温度調節には気をつけ、冷やしすぎないように適切に使用しましょう。
外出時など、温度調節が難しい場面では上着やひざかけを用意し、自身で調節できるようにすると体の冷やしすぎを予防できます。また、冷房の風が直接体に当たると、体温が必要以上に奪われてしまいます。風向きを調整し冷えすぎないように気をつけましょう。
さらに、暑い時期は冷たい飲み物や食べ物を摂りがちですが、摂りすぎると胃腸の働きが低下し、体調を崩す原因になります(*1)。胃腸に負担をかけないように、温かい料理を取り入れてみましょう。
・こまめな水分補給、栄養バランスの良い食事をとる
アンケートでも、夏バテ対策で食事や水分に気をつけている方が多く見られました。
夏は汗をかきやすく、水分やミネラルを失いやすくなります。水分補給はこまめに取ることがポイントです。のどの渇きを感じる前に意識して飲むようにしましょう。特に汗をかいたあとは、ナトリウムなどの電解質を含む飲み物を選ぶと良いでしょう(*2)。
また、暑さのせいで食事は冷たいそうめんや冷麺といったさっぱりした食事が増えがちですが、炭水化物ばかりに偏らないよう注意が必要です。夏バテ予防のためには、ビタミンやミネラル、タンパク質を意識して取り入れましょう。
ビタミンの中でも、特に積極的に取り入れたいのがビタミンB1です。ビタミンB1は、炭水化物に含まれる糖質をエネルギーに変える酵素を助ける働きがあります(*3)。つまり、ビタミンB1が体内で充足していると、エネルギーを効率よく得られ、疲労回復効果も期待できるのです。ビタミンB1は、ウナギ、豚肉などに多く含まれます(*4)。意識して食べるようにしてみてください。
・睡眠をとる
自律神経の働きを整えるためには、十分な睡眠が欠かせません(*5)。睡眠の質が悪かったり、寝不足が続いたりすると、体がうまく回復できず、夏バテの症状が出やすくなってしまいます。
特に、暑い環境ではぐっすり眠れませんね。良質な睡眠をとるために、エアコンや扇風機を使用して室温を快適にすることが大切です。
また、就寝前のスマートフォンの使用を控えたり、静かで暗い環境にしたりと、睡眠環境を整える工夫もしてみましょう。
・軽い運動をする
暑い日が続くと、つい運動を避けがちです。しかし、短時間でも軽く体を動かして汗をかくと、暑さと冷房で乱れやすい体温調節機能が改善し、夏バテの予防につながります。
涼しい時間帯の散歩や、室内でのストレッチ、ラジオ体操など、無理のない範囲で日常的に体を動かす習慣をつけましょう。
<もし夏バテになってしまったら>
十分な対策をしていても、夏バテになってしまうことはあります。
もし体がだるくなったり、食欲が落ちたりといった不調が出てしまった場合には、無理をせず、体をいたわることが大切です。ここでは、夏バテから回復するためにおすすめしたい過ごし方を紹介します。
・まずは「休む」ことが最優先
夏バテのときは、体の回復力そのものが落ちています。無理をして動き続けると、症状が長引いたり、悪化したりしてしまうこともあります。まずは休養が優先です。涼しい部屋でゆっくり横になり、体力を回復させましょう。
十分な睡眠は疲労回復には欠かせません(*6)。仕事や家事などですぐに休めない場合も、なるべく早く就寝するようにしたり、昼寝を取り入れたりするなど、体をいたわる工夫をしてみてください。
・食べやすいものから少しずつ栄養をとる
夏バテになると、どうしても食欲が落ちてしまいます。栄養をとらなければ体は十分回復できません。食べられるものを少しずつ摂りましょう。
食事は、炭水化物、タンパク質、ビタミンやミネラルをバランスよく含む内容を心がけましょう。疲労回復のためには、ビタミンB1が多く含まれる食材を積極的に摂ってみましょう。
また、食欲がないからといって冷麺などの冷たいものばかり食べるのは、かえって胃腸に負担をかけてしまいます。胃腸が冷えすぎないよう、具だくさんのスープなどもおすすめです。水分は、常温の飲み物や温かいお茶を選ぶのもよい方法です。
・室温と衣類で体温を整える
体の回復を助けるためには、快適な室温を保つことが大切です。冷房は上手に使い、寒くなりすぎないように調節しましょう。冷風が直接当たらないようにし、冷えすぎを防ぐこともポイントです。
また、室内でも体が冷えないよう、薄手の羽織や靴下を使って調整しましょう。汗をかいたあとはすぐに着替えることも、体調維持に役立ちます。
・症状が長引くときは、無理せず病院受診を
だるさや頭痛、食欲の低下など夏バテの症状が続く場合は、無理をせず病院を受診しましょう。
夏バテと思っていた症状が、実は他の病気だったという場合もあります。数日たっても食欲がまったく戻らない、体重が減ってきた、強い倦怠感があるなど不調が続く場合は、医療機関を受診しましょう。
<おわりに>
夏バテは、高温多湿な環境によって自律神経が乱れ、体調を崩しやすくなる状態です。しかし、日々の生活習慣や環境を少し見直すことで予防することができます。
体の冷やしすぎに注意し、栄養バランスの良い食事とこまめな水分補給、十分な睡眠、そして軽い運動を取り入れてみましょう。
この夏を元気に乗り切るために、まずは自分の体に目を向けて、できることから始めてみましょう!
参考文献
(*1) Sun WM. Effect of meal temperature on gastric emptying of liquids in man. Gut. 1988 Mar;29(3):302-5.
(*2) 髙田邦夫, バランスの取れた熱中症及び夏バテの予防法の提案
(*3) ビタミン B1|日本静脈経腸栄養学会
(*4) 食品成分データベース|文部科学省
(*5) 8月 夏バテしない生活習慣を! | 全国健康保険協会
(*6) 健康づくりのための睡眠ガイド2023|厚生労働省
◆ 本件に関するお問い合わせ先
会社名:大研バイオメディカル株式会社
メール:info@daikenshop.co.jp
公式ホームページ:https://www.daikenshop.co.jp/
