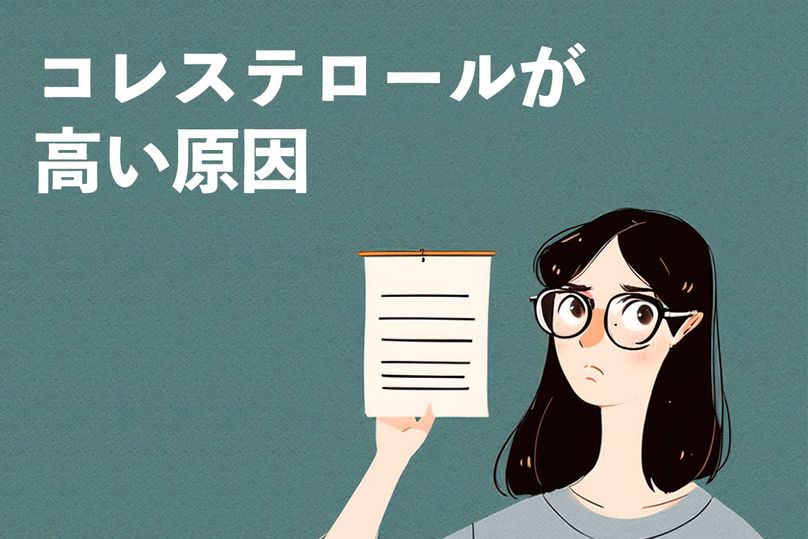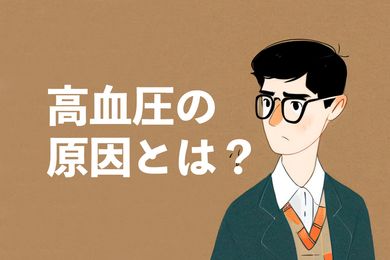コレステロールとは、脂質の一つをいいます。体内にはコレステロール、中性脂肪、リン脂質、遊離脂肪酸の4種類の脂質が存在します。コレステロールは、細胞膜やホルモン、脂肪の消化吸収を助ける胆汁酸の材料であり、生命の維持に必須の脂質です(1)。 ただし、コレステロールはエネルギー源として使用されることはありません。
コレステロール値が低くなると肌や髪に潤いがなくなりパサパサになり、血管の壁が弱くなり出血を起こしやすくなります。また、コレステロール値が高くなると動脈硬化が進行し、放置すると脳梗塞や心筋梗塞などの重篤な病気のリスクになるため、適切な治療が必要です。
コレステロール値が高くなる原因と、下げる方法を詳しく説明します。
コレステロールとは?
コレステロールは20~30%は食べ物から取り込まれ小腸で輸送蛋白(コレステロールトランスポーター)の働きで吸収されます。残りの70~80%は肝臓で糖質や脂質を材料に生成されます。食べ物から取り込まれるコレステロールを外因性コレステロール、体内で作られたものを内因性コレステロールと呼びます。
コレステロールは脂質のため、そのままでは液体である血液に溶けることができません。そのためLDL(低密度リポタンパク質)やHDL(高密度リポタンパク質)といったリポ蛋白という粒子と結合し、血流に乗ってからだの隅々まで運ばれます。
コレステロールにはLDLコレステロールとHDLコレステロールの2種類があります。
LDLコレステロール(悪玉コレステロール)
LDLコレステロールは、肝臓で生成されたコレステロールを全身に運びます。運ばれたコレステロールは全身の細胞で使用されますが、細胞は必要以上のコレステロールを取り込みません。そのため、LDLコレステロールが増えすぎると細胞で使われずに血液中を循環したままになります。
使用されなかった余分なコレステロールは血管の壁に沈着し、プラークと呼ばれる構造ができます。プラークが蓄積し血管壁が厚く、内壁が狭くなる状態をアテローム硬化と呼びます。アテローム硬化は動脈硬化のタイプの一つで、脳血管障害や心筋梗塞などの引き金となるため特に注意が必要です。
アテローム硬化は進行すると血管が脆弱になり、少しの力で破損します。破損を修復するために血小板が集まり血栓ができ、これにより血管が詰まると心筋梗塞や脳梗塞を発症します。
このため、LDLコレステロールは悪玉コレステロールと呼ばれます。
HDLコレステロール(善玉コレステロール)
HDLコレステロールは臓器で使われなくなった余分なコレステロールを回収し、肝臓に戻します。脂質が蓄積して動脈硬化を起こした血管からもコレステロールを回収することができます。
このため、HDLコレステロールは善玉コレステロールと呼ばれます。
コレステロール値の基準値
コレステロール基準値を以下に示します。(2)
| コレステロール |
基準値 |
|
LDLコレステロール |
140 mg/dL未満 |
|
HDLコレステロール |
40 mg/dL以上 |
|
中性脂肪 |
150 mg/dL未満 |
|
Non-HDLコレステロール |
170 mg/dL未満 |
こちらは、高血圧、糖尿病、過去の心筋梗塞などがない方での基準値です。動脈硬化のリスクが高いと判断される場合は、LDLコレステロール値の目標値は更に低い場合があります。
脂質検査の採血は原則として10時間以上絶食後に行うことが推奨されています。LDLコレステロール、HDLコレステロールは採血時間の影響は少ないとされています(3)が、食事に大きく影響する中性脂肪が高くなるとコレステロール値を正しく測定できない場合もあります。
コレステロール値が基準値を外れた場合、これを脂質異常症と呼びます。
脂質異常症のうち、どの値が異常値かによって細かく分類されます。HDLコレステロールが基準値より低い場合、低HDLコレステロール血症と診断します。LDLコレステロールが基準値より高い場合、高LDLコレステロール血症と診断します。
基準値を外れたからすぐ治療が必要なわけではありませんが、いずれも動脈硬化リスクが高まるため、適切な治療が必要です。
コレステロール値が高い原因
一般的にLDLコレステロール値が高いことを「コレステロール値が高い」といいますので、本記事もこのように定義します。コレステロール値が高くなる原因は以下のようなものが考えられます。
生活習慣
偏った食生活が原因の場合があります。飽和脂肪酸やコレステロールの過剰な摂取は、コレステロール値が高くなる原因です。肥満もコレステロール値が高くなることが知られています。BMI(体重(kg)÷身長(m)2)が25以上で肥満と定義されており、25未満に体重を維持するようにしましょう。
加齢
加齢により細胞の入れ替わるサイクルが遅くなり、細胞膜の材料であるコレステロールが使われなくなります。また、女性は更年期にさしかかると女性ホルモンであるエストロゲンの分泌量が減少し、材料であるコレステロールが使われなくなります。そのため、若い頃と同じ生活をしていてもコレステロール値が上昇します。
二次性高コレステロール血症
ほかの基礎疾患に基づいて生じる二次性である場合があります。
代謝性疾患である甲状腺機能低下症は、代謝を調節する甲状腺ホルモン分泌が低下し代謝が悪くなります。また、糖尿病は脂質の代謝異常をきたします。そのほかにも、閉塞性黄疸、原発性胆汁性肝硬変などの肝疾患や、ネフローゼ症候群などの腎疾患、薬剤性(コルチコステロイド、経口避妊薬、利尿剤など)が原因となり得ます。
二次性高コレステロール血症の場合は、原因である疾患の治療を行うことでコレステロール値が正常化する場合があります。
遺伝
家族性高コレステロール血症など、遺伝的にコレステロール値が高い場合があります。コレステロールを肝臓で処理する能力が低いためコレステロール値が高くなり、若い頃から動脈硬化が進行します。この場合は、薬物療法を行う必要があります。
コレステロール値を下げる方法
コレステロールは生活習慣の改善で下げることが可能な場合があります。コレステロール値を下げる方法をいくつかご紹介します。
食事療法
・飽和脂肪酸の摂取量を減らす
肉の脂身、バターなどに多く含まれる飽和脂肪酸の摂取は、LDLコレステロール値を上昇させ、脳卒中や心筋梗塞リスクといった心血管リスクを増加させます。飽和脂肪酸摂取量を減らすことで心血管リスクを減少させることが示されています(4)。 総エネルギー摂取量の7%未満の摂取量に留めることが推奨されています。
・コレステロール摂取量を減らす
コレステロールは食事で吸収されるものと体内で合成されるものがあります。食事摂取量が増えればLDLコレステロール値は上昇します(5)。
コレステロール摂取量は200mg/日未満にすることが推奨されていますが、令和元年国民健康・栄養調査(6)によると、日本人の1日平均摂取量は男性366mg、女性317mgですので、意識的にコレステロール摂取量を減らすことが必要です。
・不飽和脂肪酸の摂取、オメガ3の摂取
EPA、DHAなどのオメガ3系多価不飽和脂肪酸の摂取により心筋梗塞などの冠動脈疾患発症抑制効果があります(7)。 不飽和脂肪酸が豊富なサンマ、イワシなどの青魚やくるみなどのナッツ類、オリーブオイルなどを多く摂取するよう心がけましょう。
・食物繊維の摂取
食物繊維は野菜、海藻、きのこ、果物などに含まれます。コレステロール吸収抑制や胆汁酸合成促進の作用があり(5)、LDLコレステロール値を低下させます。1日25g以上の食物繊維の摂取が推奨されています。
運動療法
有酸素運動が有効とされています。ややきついと感じる程度の運動を15分以上、週120分以上行うと、HDLコレステロール値が上昇します(8)。 LDLコレステロール値の低下も期待できるため、コレステロール値が高い場合は運動を行うことが推奨されます。
無理な運動は骨折をきたしたり心臓に負担がかかったりする場合があるため、無理のない範囲で、主治医と相談しながら行うようにしましょう。
体重管理
コレステロール値を下げるためには体重管理も大切です。肥満がある場合は、総エネルギー量を制限し適切な体重を維持することでLDLコレステロール値が減少します。肥満は高血圧や糖尿病などの動脈硬化促進因子の原因にもなります。BMI 25未満を目標とし、食事管理や運動療法を行いましょう。
薬物療法
食事や運動療法を行ってもLDLコレステロール値が減少しない場合は、薬物療法が必要な場合があります。動脈硬化のリスクに応じて治療を行うため、病院を受診し医師に相談しましょう。
まとめ
LDLコレステロール値が高くなると動脈硬化を進行させ、さまざまな疾患のリスクになります。適切な食事、運動習慣を心がけ、LDLコレステロール値が高くならないように心がけましょう。