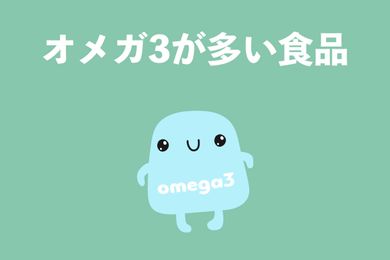うっ血とは、血液の流れが悪くなり静脈の血流が滞り、血液が多く溜まってしまう状況をいいます。漢字では鬱血と書きます。鬱には「ふさがる」という意味があり、血管がなんらかの原因でふさがっているためこの漢字を使用します。
うっ血は充血と混同される方も多いですが、充血とは体のある部分に血液が動脈を通じて異常に流れ込む状態をいいます。静脈の血流が滞るうっ血とは別の状態です。
軽症の場合はだるさやむくみなど、ごく軽度の症状にとどまることもあります。しかし実は重大な病気が隠れていたり、放置すると悪化したりする可能性もあり注意が必要です。
この記事ではうっ血の原因や症状、予防方法などについて詳しく解説します。
うっ血とは?血流が滞るとは?
心臓はポンプとしての働きがあり、動脈、静脈といった血管を通じて全身あらゆる臓器に血液を送る機能を持ちます。
血液は心臓から動脈に流れ込み、体のあらゆる臓器に行き渡り、酸素を供給したあと、二酸化炭素を回収して静脈を通り心臓に戻ります。
なんらかの原因で心臓の機能が低下したり、静脈が圧迫されたり詰まったりすることで血液の流れが滞り、うっ血が起こります。
心臓のポンプ機能が低下すると、血液を動脈へ送り出すことができなくなります。
ると静脈から血液が心臓に戻ることができなくなり、血流が滞ります。溜まった血液は行き場がなくなり肺にたまり息切れを起こすほか、むくみや、急激な体重増加、尿量の減少などさまざまな症状を起こします。(1)
うっ血が起こる主な原因
うっ血はさまざまな要因で発症します。主に以下のようなものが原因になります。
心臓の病気
心臓のポンプ機能が弱まると血液が滞るためうっ血が起こります。
僧帽弁閉鎖不全や大動脈弁閉鎖不全などの心臓弁膜症、心臓にある冠動脈という血管が急激に詰まって心筋が壊死してしまう急性心筋梗塞、ウイルスが心臓に感染して引き起こされる心筋炎などもうっ血の原因になります。
動脈硬化
動脈硬化もうっ血の原因となります。動脈硬化が起こると心臓が動脈へ血液を送り出すときに強い力が必要になり、それが続くと心臓が徐々に疲弊し心不全を起こし、うっ血を発症します。
さらに、冠動脈が動脈硬化を起こすと、突然冠動脈が閉塞し急性心筋梗塞を引き起こすことがあります。
そのため、うっ血の予防には動脈硬化のリスクを可能な限り減らすことが重要です。糖尿病、高血圧、脂質異常症などの生活習慣病は動脈硬化が進行する主な原因であり、これらのリスクを下げることが必要です。
下肢静脈瘤
足の静脈にある逆流防止弁が正常に働かなくなることで血液の流れが悪くなる下肢静脈瘤という病気は、足の静脈がこぶのように浮き出てくるとともに、足にうっ血が起こります。
物理的圧迫
また、妊娠により子宮が大きくなり静脈を物理的に圧迫すると、血流が滞りうっ血が起こります。
ごくまれですが、部位によっては、腫瘍が静脈を圧迫してうっ血が起こることもあります。
薬の副作用
医薬品や抗がん剤の副作用でも心臓の機能が低下しうっ血を起こすことがあります。
もし薬の影響が考えられる場合は、薬のメリットと症状をよく考えて使用継続や中止を考える必要があるかもしれません。主治医と相談するようにしましょう。
うっ血の症状
うっ血は、血液の流れが滞り全身でさまざまな症状を引き起こします。主な症状を説明します。
むくみ(浮腫)
うっ血の最も一般的な症状の一つがむくみです。心臓に戻れなかった体の余分な血液が行き場をなくし、足首、ふくらはぎ、まぶたなどに貯留することでむくみを起こします。ときに重だるさを感じることがあり、貯留した水分によって体重が増加します。
呼吸困難
肺でうっ血が起こる状態を肺うっ血といい、進行し肺に水が大量貯留した場合を肺水腫といいます。
肺水腫では肺に水が溜まることで肺での酸素交換ができなくなります。軽症では動くとすぐ息切れを起こし、ピンク色の泡沫状の痰を伴う咳や動悸が起こることがあります。肺にさらに水が溜まって重症になると、肺でのガス交換ができなくなるため、呼吸困難感が強くなり体の末端に酸素が行き届かなくなります。
脳に酸素が行き届かなくなると意識障害を起こすこともあります。
疲労感
心臓の機能が低下し血流が滞り、全身に酸素がいきわたらなくなると疲れを感じやすくなります。
尿量減少
尿は腎臓で血液をろ過して作られます。うっ血により血流が滞り腎臓への血流が低下すると、尿量が減少することがあります。体内の老廃物や不要な水分が排出できなくなるため、腎不全などの重篤な状態になることがあります。
心臓の機能が落ちている方や、動脈硬化が進んでいる方はうっ血のリスクが高い状態です。
このような症状が起こった場合は医療機関を受診するようにしましょう。
うっ血の治療法
うっ血が起こった際の治療は原因によってさまざまです。
血液の流れが滞っているためにうっ血が起こっている場合は、薬物療法を行い、不要な水分を出す利尿剤を使用します(2)。
心臓のポンプ機能が低下している場合は、心臓の動きを戻すために強心剤を使用する場合もあります。また、冠動脈疾患や弁膜症などが原因でポンプ機能が低下している場合には、必要に応じてカテーテル治療、外科的治療(手術)などが行われる場合もあります。
重症度やうっ血の原因によって治療法が異なるため、まずは原因を特定し、その上でその病状にあった適切な治療が行われます。
生活習慣でうっ血の改善
食事のポイント
1.塩分の制限
動脈硬化は心臓を疲弊させ、うっ血を起こすリスクになります。
血圧が高いと心不全のリスクが高まります(3)。塩分の過剰摂取が高血圧の重要なリスクと考えられており、高血圧治療ガイドライン2019では、1日の塩分摂取量を6g以下にするよう推奨されているため(1)、減塩を心がけましょう。
2.減量
肥満は動脈硬化の進展を助長し、心不全の発生に関連します(4)。
減量により血糖、血圧、中性脂肪の改善も期待できます(5,6)。動脈硬化の原因である高血圧に関しては、約4kgの減量を行うことで収縮期血圧4.49mmHg、拡張期血圧3.19mmHgの減少が期待できます(6)。
脂質の多い肉類や揚げ物を避け、1日の総摂取カロリーを減らしバランスの良い食事をこころがけましょう。
3.脂質、糖質の制限
糖尿病も心不全の大きなリスクです(7)。糖質の過剰な摂取は控えましょう。
LDLコレステロールは動脈硬化の主要な原因です(8)。
コレステロールを下げるために、コレステロール含有量の多い卵、レバー、干物などは控え、食物繊維の多い食事を摂取しましょう。
また、青魚などに多く含まれるDHAやEPAなどのオメガ3脂肪酸は、血中の中性脂肪を減少させることで血液をサラサラにし血栓を予防したり、動脈硬化を予防したりする効果があることが知られています(9)。
オメガ3脂肪酸は1日2~3gの摂取で血圧低下作用が期待できます (10)。
運動のポイント
運動をすると筋肉量が増えることで代謝が良くなり、血管内皮機能が改善することで心不全発症のリスクを減らすことができます。
運動は有酸素運動が推奨されています。しかし心臓の機能が低下している人は過度な運動により心臓に負荷がかかってしまい、かえってうっ血が悪化する可能性があります。そのため、運動を開始する際には医師に相談するようにしてください。
心臓が悪い人は、負荷をかけすぎないように注意し、歩行、自転車、軽いエアロビクス体操などの運動から行うようにしましょう。
低~中強度の運動量で十分な効果が得られます。具体的には、息切れしない強さで、「ややきつい」と思う強度を超えないようにしてください。
最初は1回5~10分、1日2回から、1回30分~60分まで徐々に増やしましょう。週3~5回の運動が推奨されています。(11)
運動により下肢の筋力が増すことで、ふくらはぎの筋肉が収縮し足の静脈内の血流を送る「筋ポンプ作用」により下肢の血流が良くなりうっ血を改善することも期待できます。
まとめ
うっ血は血流が滞ることでさまざまな症状が起こります。
症状がごく軽度の場合もありますが、急に症状が悪くなったり、実は重大な病気が隠れていたりすることもあるため、異常を感じた場合は放置せずに適切な対応が必要です。
息苦しさ、むくみ、体重増加、だるさなどがみられた場合は病院を受診して医師に相談するようにしてください。