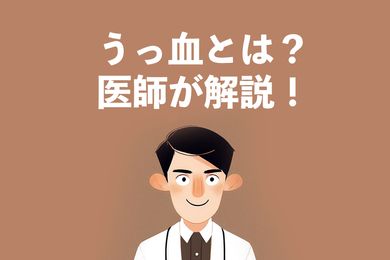多くの方が、血圧は健康管理の重要な指標のひとつであることを知っています。しかし、血圧の正常値や高血圧の基準値、高血圧によるリスクなどを知っている方は、それほど多くありません。
ここでは、血圧についてや血圧の正常値、高血圧や低血圧が引き起こす疾患、高血圧を下げる方法などを解説します。
血圧とは何?
血圧とは、心臓が血液を送り出すときに血管の内側を押す力です。血圧は、心臓が送り出す血液量(心拍出量)と血管の弾力性、末梢血管の抵抗性、血液の粘度、体を循環している血液量などの要因により決まります。血圧は全身の血管にありますが、一般的には上腕動脈の血圧のことです。
血圧は、診察室で測定する診察室血圧と、自宅で測定する家庭血圧に分けられます。診察室で緊張している人の診察室血圧は、自宅でリラックスした状態で血圧を測定する家庭血圧よりも高く出やすい傾向があります。(1)
収縮期血圧と拡張期血圧の定義
心臓は、ポンプのように収縮と拡張を繰り返し、全身に血液を送り出しています。収縮期血圧は、心臓が収縮して血液を全身に送り出すときに、血管の内側の壁にかかる圧力です。最も強い圧力がかかるため、最高血圧や上の血圧ともいわれています。
拡張期血圧は、血液が心臓に戻ると一時的に血液をため込み心臓が拡張するときに、血管の内側の壁にかかる圧力です。血管の血液量が減り血管の壁にかかる圧力が最も低くなるため、最低血圧や下の血圧ともいわれています。(2)
血圧の数値分類と定義
血圧は、正常血圧、正常高値血圧、高値血圧、高血圧の4段階に分類されています。さらに高血圧は重症度によって、Ⅰ度、Ⅱ度、Ⅲ度の3段階に分類されています(1)。正常高値血圧は、収縮期血圧が正常血圧の基準値以上で高血圧の基準値未満、拡張血圧が正常血圧の範囲内にある状態です。現状では高血圧と診断されませんが、このままだと将来高血圧になってしまうリスクが高いといわれています。
高値血圧は、現状では高血圧とは診断されませんが、正常高値血圧よりもさらに高血圧になるリスクが高い状態です。収縮期高血圧とは、高齢者によくみられ収縮期血圧だけが高い血圧です。血圧の数値分類を以下の表にまとめました。
血圧の数値分類
|
分類 |
診察室血圧(mmHg) |
家庭血圧(mmHg) |
|
収縮期血圧 拡張期血圧 |
収縮期血圧 拡張期血圧 |
|
|
正常血圧 |
<120 かつ <80 |
<115 かつ <75 |
|
正常高値血圧 |
120-129 かつ <80 |
115-124 かつ <75 |
|
高値血圧 |
130-139 かつ/または 80-89 |
125-134 かつ/または 75-84 |
|
Ⅰ度高血圧 |
140-159 かつ/または 90-99 |
135-144 かつ/または 85-89 |
|
Ⅱ度高血圧 |
160-179 かつ/または 100-109 |
145-159 かつ/または 90-99 |
|
Ⅲ度高血圧 |
≧180 かつ/または ≧110 |
≧160 かつ/または ≧100 |
|
(孤立)収縮期高血圧 |
≧140 かつ <90 |
≧135 かつ <85 |
参考:「高血圧治療ガイドライン2019」
家庭血圧が正常値の方以外は、できるだけ早く医師の検査・指導を受けることをおすすめします。
各年齢・性別の平均血圧値
各年代・性別の平均血圧を以下の表にまとめました。※血圧の単位は(mmHg)
|
総数 |
20代 |
30代 |
40代 |
50代 |
60代 |
70歳~ |
(再掲)40-89歳 |
||
|
男性 |
収縮期血圧 |
132.0 |
115.3 |
117.3 |
125.8 |
131.7 |
135.8 |
135.8 |
133.9 |
|
拡張期血圧 |
76.2 |
67.7 |
73.7 |
81.3 |
82.0 |
78.5 |
73.1 |
76.2 |
|
|
女性 |
収縮期血圧 |
126.5 |
105.7 |
107.9 |
114.3 |
123.7 |
131.0 |
136.1 |
129.0 |
|
拡張期血圧 |
73.1 |
63.8 |
66.3 |
71.2 |
75.4 |
76.7 |
73.0 |
74.2 |
|
参考:「令和元年国民健康・栄養調査報告」
年齢があがると男女ともに血圧が高くなる傾向があることがわかります。また、同年代では男性の方が女性よりも血圧が高い傾向もみられます。(3)
日本高血圧学会が発行している「高血圧治療ガイドライン2019」によると、過去50年で男女ともに血圧は低下傾向にあります。これは、高血圧患者が降圧剤を服用して血圧をコントロールしている割合が増えたことが関係していると指摘されています。また、高血圧に対する予防意識の高まりも、血圧が低下傾向にある理由のひとつと考えられています(1)。
血圧の高低に基づく可能性のある疾患のリスト
血圧が正常値よりも髙くても低くても、さまざまな疾患のリスクを高めます。以下に血圧の高低に基づく可能性のある疾患を紹介します。
血圧が高いことが原因で発生する疾患
-
動脈硬化:血管の壁が厚く硬くなり、各部が必要としている血液が十分に届かなくなります。進行すると、血管の壁の堆積物が破裂し血栓となり血管を詰まらせ、心筋梗塞や脳梗塞を引き起こすことがあります。
-
脳梗塞:脳の血管が血栓で詰まり、血液の流れが滞ってしまう病気です。血液が流れない部分の細胞が死んでしまい、麻痺や感覚障害などの後遺症や最悪の場合は命にかかわるケースもあります。
-
心筋梗塞:心臓の筋肉に血液を送る冠動脈に血栓が詰まり、血液の流れが滞ってしまう病気です。血液が流れなくなった部分の細胞は死んでしまい、広範囲の心筋が酸素不足になると突然死に至るケースもあります。
-
慢性腎臓病:腎臓の機能低下や障害があらわれる病気です。初期は自覚症状がほとんどなく、貧血や頭痛、めまいなどの自覚症状が出るころには、かなり進行しているケースが多いようです。
上記以外に脳出血や腎硬化症、糖尿病、高血圧性心肥大、心不全、狭心症、大動脈瘤、認知症などさまざまな疾患を引き起こしやすくなることがわかっています(1)(4)。
血圧が低いことが原因で発生する疾患
-
脳貧血:脳に送られる血液量が低下することにより、めまいや失神などを引き起こす病気です。
-
狭心症:心筋に血液が十分に運ばれないことで酸素不足になり、胸の痛みや圧迫感を引き起こす病気です。
-
多臓器不全:血圧が急激に低下しショック状態になると、全身に血液が行き渡らなくなり複数の臓器の機能が低下してしまう病気です。
上記以外にも、心筋梗塞や不整脈なども引き起こしやすくなるといわれています。(5)(6)
高血圧の定義
高血圧は、繰り返し血圧を測定しても、正常値よりも高い状態のことです。基準値は、家庭血圧と拡張血圧でそれぞれ定められています。家庭血圧で収縮期血圧が135 mmHg以上かつ/または拡張期血圧が85 mmHg以上、診察室血圧では収縮期血圧が140mmHg以上かつ/または拡張期血圧が90mmHg以上と定義されています。「高血圧治療ガイドライン2019」では、家庭血圧と診察室血圧で高血圧の判定が異なる場合は、家庭血圧での判定を優先することが推奨されています。(1)
高血圧を下げる方法
高血圧を下げる方法は、生活習慣を改善する方法と薬を服用する方法に大きく分けられます。重症の高血圧の方は、すぐに薬を服用するケースもありますが、まずは生活習慣の改善で高血圧が改善できるか試すケースが多くみられます。(1)
-
塩分摂取の制限:塩分の過剰摂取は血圧を上昇させるため、1日の塩分摂取量を6g未満に抑えることが推奨されます。実践するのは難しいですが、少しでも塩分摂取量を減らそうという気持ちが大切です。
-
バランスの取れた食事:野菜や果物、全粒穀物、低脂肪の乳製品、魚などを積極的に摂取し、脂肪分が多く含まれている食べ物を控えるよう心がけましょう。
-
適度な運動:毎日ウォーキングなどの有酸素運動を毎日30分以上するような習慣を身につけることが大切です。定期的に運動する習慣がない方は、普段の生活で、これまでよりも多く歩くことを心がけることから始めましょう。
-
体重管理:肥満の方は、適正体重になるように減量すると、血圧改善が期待できます。適切な食事量と運動で、BMIが25未満になるように減量しましょう。 ※BMI=体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)
-
禁煙:喫煙は、血管を収縮させ血圧を上昇するだけでなく、動脈硬化を促進させ心血管疾患のリスクを高めます。喫煙本数を減らす節煙でも血圧を低下させることが期待できますが、禁煙外来などを利用して完全な禁煙を目指しましょう。
-
節酒:適量を超えたアルコール摂取は、血圧をあげる作用があるとされています。純アルコール換算で男性20~30ml、女性10~20mlを超えた飲酒を控えるように心がけましょう。目安は、ビール中瓶1本、日本酒・ワイン1合、ウイスキーダブル60mlです。
-
ストレス解消:過度なストレスは高血圧の原因のひとつと考えられています。全くストレスを感じない生活をするのは難しいので、自分に合ったストレス解消法を見つけましょう。
-
降圧剤の服用:生活習慣を改善しても血圧の低下がみられない、または重症の高血圧の場合、降圧剤を服用し血圧を下げます。服用する降圧剤の服用量や種類は、健康状態によって異なります。主治医の指導を守って服用しましょう。
高血圧治療ガイドラインによる降圧目標は以下の通りです。
|
診察室血圧 |
家庭血圧 |
|
|
75歳未満(成人) |
収縮期血圧:130mmHg未満 拡張期血圧:80mmhg未満 |
収縮期血圧:125mmHg未満 拡張期血圧:75mmHg未満 |
|
75歳以上 |
収縮期血圧:140mmHg未満 拡張期血圧:90mmHg未満 |
収縮期血圧:135mmHg未満 拡張期血圧:85mmHg未満 |
参考:「高血圧治療ガイドライン2019」
ただし、脳血管障害や糖尿病、慢性腎障害(CKD)、冠動脈疾患などを患っている方の降圧目標は異なる場合があります。降圧目標は、個人の健康状態によって異なるため、主治医の指導に従ってください。
まとめ
血圧を正常値の範囲内に保つために、食事や運動習慣などを見直すことが大切です。また、血圧異常は、自覚症状があらわれにくく、いつの間にか進行し重大な病気を引き起こす可能性があります。それを防ぐために、家庭血圧を測定する習慣をつけておくことがおすすめです。
万が一、家庭血圧を測定し正常値の範囲内から外れていた場合は、必ず医師に相談してください。