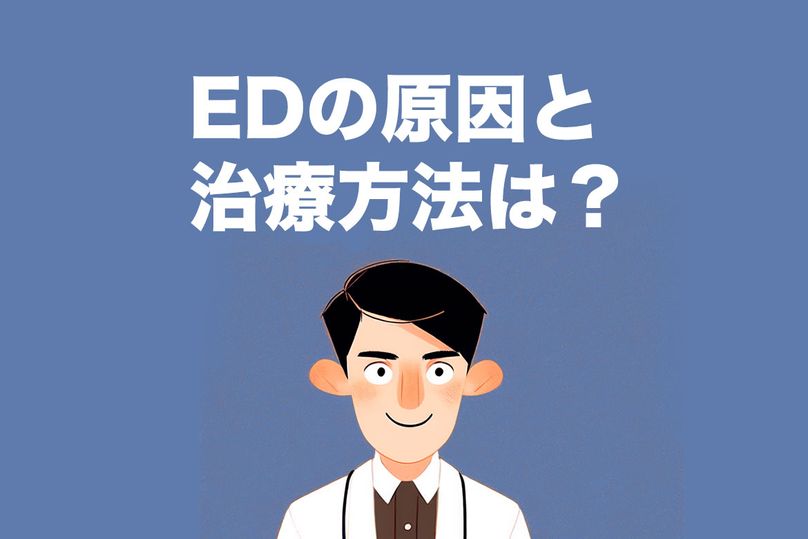ED(Erectile Dysfunction:勃起不全)は、男性において一般的な悩みのひとつであり、日本でも多くの人が経験しています。EDは性的興奮によって十分な勃起が得られない、またはその状態を維持できない状態を指し、性行為が満足に行えないことが特徴です。近年、生活習慣の変化や加齢にともない、EDに悩む男性が増加しています。日本人国内の40歳以上の男性において、約3人に1人がEDであるといわれています。(1)
EDはさまざまな原因により引き起こされると考えられており、年齢だけの問題ではありません。EDの治療がきっかけで他の病気が見つかる可能性もあります。この記事では、EDの定義や原因、診断方法、そして治療方法についてくわしく解説しています。
ED(勃起不全)とは?
EDの定義
EDは「Erectile Dysfunction」の略で、日本語では「勃起不全」または「勃起障害」と訳されます。日本性機能学会および日本泌尿器科学会の「ED診療ガイドライン」によると、EDは「満足な性行為を行うのに十分な勃起が得られないか、または維持できない状態が持続または再発すること」と定義されています。
ED治療の必要性については、明確な医学的基準があるわけではありませんが、EDによってご自身やパートナーがお困りの場合や不安感などがある場合は、医療機関に一度相談してみるとよいでしょう。(2)(3)
EDの症状
EDの症状には、以下のような症状があります。(1)
-
性的刺激を受けても全く勃起しない
-
勃起しても短時間しか続かず、その状態を維持できない
-
勃起の硬さが十分でないため、性交が困難である
-
一度萎えてしまうと、再び勃起することが難しい
このような症状が続く場合、ご自身のだけでなくパートナーとの関係性にも悪影響を及ぼすことがあります。EDは単なる身体的な問題だけでなく、精神的なストレスにもつながります。当てはまる症状がある場合、早めに治療を検討してみてもよいかもしれません。
ED(勃起不全)の原因
EDの原因はさまざまです。ここでは、「器質性ED」、「心因性ED」、「混合性ED」、「薬剤性ED」にの4つに分類して原因を解説します。(2)
器質性ED
器質性EDは、血管や神経の障害などの身体的な問題が原因で引き起こされるEDです。勃起現象には陰茎への血流が重要な役割を果たしているため、陰茎への血管と神経が健康に保たれていないとEDのリスクが高くなると考えられます。
血管障害や神経障害を引き起こす動脈硬化や高血圧、糖尿病、心疾患などが器質性EDの原因として挙げられます。肥満や運動不足、乱れた食生活、睡眠不足、飲酒や喫煙などの生活習慣の乱れは動脈硬化の原因となることがあり、EDの発症リスクを高めます。また、これらの生活習慣の乱れは、高血圧や糖尿病、心疾患などを合併するリスクも高くなります。
EDを引き起こす神経疾患には、多発性硬化症や脳卒中、てんかん、パーキンソン病などの疾患があります。これらの神経疾患は、疾患そのものがEDの原因になりますが、その治療薬もEDを引き起こすことが明らかになっています。くわしくは、後述の「薬剤性ED」の項目で解説します。(1)(2)(4)(5)
心因性ED
心因性EDは、心理的な問題が原因で起こるEDです。ストレス、不安、うつ病、緊張などが原因となり、性的興奮が十分に得られないことがあります。過去の体験のトラウマやパートナーとのトラブル、性行為に対する過度なプレッシャーなどもEDになりやすいと考えられています。(1)(4)(5)
混合性ED
EDの原因はひとつではなく、複数の原因によりEDが引き起こされていることもあります。混合型EDは、器質性と心因性の両方が原因となっているEDです。
例えば、糖尿病の場合は、糖尿病による血流障害や神経障害が原因で勃起しにくくなった状態に、糖尿病に合併しやすい高血圧や肥満、運動不足などが加わること、さらにはうつ状態や不安、性欲低下などの心理的な原因が重なることでEDが悪化します。混合性EDでは、身体的な治療だけでなく、心理的なサポートも重要となります。(2)
薬剤性ED
薬剤性EDは、使用している薬剤による副作用が原因で引き起こされるEDです。薬剤性EDが報告されている薬剤には、降圧薬や利尿薬、抗うつ薬、前立腺肥大症治療薬、非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)などがあります。
薬剤性EDは、薬を変更することで改善する可能性がありますが、自己判断での薬の中止は危険なため、必ず医師に相談するようにしましょう。(2)(3)(4)
ED(勃起不全)の診断
EDの診断には、EDの程度を評価する「国際勃起機能スコア(IIEF-5)」が使用されることが多いです。国際勃起機能スコア(IIEF-5)は国際的に広く使用されている診断ツールです。(4)(5)
国際勃起機能スコア(IIEF-5)
国際勃起機能スコア(International Index of Erectile Function:IIEF-5)は、5つの質問項目から成り立ち、EDの程度を評価するためのスコアです。質問項目には、勃起機能、オルガスム機能、性的欲求、性交の満足度、全体的な満足度が含まれます。(2)(4)(5)
検査方法
EDの診断には、国際勃起機能スコア(IIEF-5)、過去および現在の性的関係や心理状態、治療歴、合併症の有無などを問診で確認するほか、以下の検査が行われることがあります。(2)
-
血液検査:血糖値やホルモンの数値を調べ、糖尿病やホルモン異常による性腺機能低下がないかを確認します。
-
夜間陰茎勃起現象(NPT)の評価:睡眠中にあらわれる自然な勃起を調べる検査です。心因性EDと器質性EDを鑑別するのに有用だとされています。
ED(勃起不全)の治療方法
薬物療法
日本では、「ホスホジエステラーゼ 5 阻害薬(PDE5)」であるシルデナフィル(バイアグラ)、バルデナフィル(レビトラ)、タダラフィル(シアリス)の3つの薬剤がED治療薬として使用可能です。ED治療薬(PDE5阻害薬)は、陰茎の血管を拡張して血流量を増やし、勃起を促し持続させます。
また、陰茎の血管障害の進行を抑える働きもあるため、EDの悪化を防ぐ効果が期待できます。ED治療薬(PDE5治療薬)の用法用量は、EDの症状や全身の健康状態などによって異なるため、医師の指示通りに服用するようにしてください。持病や使用している薬によっては、ED治療薬(PDE5治療薬)を服用できない場合もあるため、現在治療中の疾患がある方は必ず医師に伝えるようにしましょう。とくに、狭心症の治療薬のニトログリセリン製剤などは血圧が過度に低下する可能性があり、ED治療薬(PDE5治療薬)を服用することができないためご注意ください。
また、インターネットなどで医師の処方せんなしで入手できるED治療薬は、偽の薬を販売している悪質なケースも多く、思わぬ健康被害などが生じるリスクがあるため、絶対に購入しないようにしましょう。(1)(2)
心理療法
心因性EDの場合、先述の薬物療法とともに、心理療法による治療を行うことが有効です。心理療法には、ご本人とパートナーとのカウンセリングや性教育などがあります。ストレスや性に対するトラウマや不安が原因の場合、専門のカウンセラーと話し合い、問題を解決することで症状の改善が期待できます。パートナーとのコミュニケーションを改善することも重要です。(2)
生活習慣の改善
肥満や運動不足、乱れた食生活、睡眠不足、飲酒や喫煙などはEDを引き起こす要因になるため、生活習慣の見直しもED治療には重要です。肥満の方では、運動や食生活の改善などで体重が減少し、EDが改善したことが報告されています。勃起機能の改善に有酸素運動、禁煙が有効であることも明らかになっています。(1)(2)(5)
まとめ
ED(勃起不全)は、男性にとってセンシティブな問題ですが、EDで悩んでいる方は少なくありません。EDの原因は多岐にわたり、それぞれに応じた診断と治療が必要です。EDは適切な治療や対処により改善することが可能です。生活習慣の改善や心理的サポートも、EDの治療や予防に効果的であることが明らかになっています。EDの症状に悩んでいる方は、まずはかかりつけの医師に相談することをおすすめします。