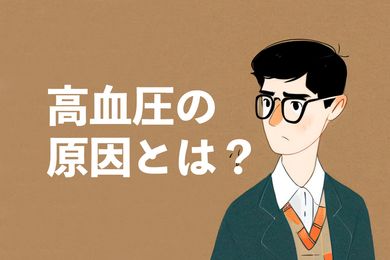高血圧は、日本におよそ4300万人の患者さんがいると推定されており、とても頻度の高い疾患です。診察室での収縮期血圧が140mmHg以上、または拡張期血圧90mmHg以上を高血圧と診断します。また、自宅で測定する家庭血圧の場合は、収縮期血圧135mmHg以上、または拡張期血圧85mmHg以上を高血圧と診断します(1)。
高血圧は自覚症状が出現することがあまりないまま、徐々に動脈硬化を進行させます。そのまま放置すると動脈硬化はどんどん進行し、硬くなった血管が破れたり、血管が細くなって詰まったりします。その結果、脳卒中や心臓病などの重篤な疾患を引き起こします。
そのため、高血圧を指摘されている場合は、放置せずに治療を行い正常な血圧に保つことが重要です。
高血圧になる原因の一つに不適切な食生活があります。血圧が高くなりやすい食べ物を多く摂っていると高血圧を発症しやすくなり、重篤な病気を発症するリスクが高まります。
この記事では、高血圧を指摘された場合、食べてはいけない、控えたほうがいい食品を解説します。
高血圧の原因
高血圧の原因は生活習慣、遺伝的要因、加齢などさまざまなものがあります。
生活習慣の要因には、塩分の過剰摂取、ストレス、運動不足などがあります。血縁者に高血圧の人がいる場合、高血圧のリスクが高まります。高血圧は、単一の原因ではなく、複数の因子が複雑に絡みあって発症することが多いとされています。
しかし、生活習慣を改善することで高血圧が改善する可能性があります。
特に、生活習慣の中でも食生活はすぐに見直すことができる上に、適切な食事療法を行えば、血圧を下げる効果が期待できます。
高血圧を改善するための食事のポイント
高血圧を改善するには、次の3つのポイントを意識して普段の食事を摂るようにしましょう。
塩分控えめの食事
人間は、塩分を過剰摂取すると一時的に高くなった体内の塩分濃度を下げるため、水分を溜め込もうとします。すると血液量が増え、血管にかかる圧力が増し、血圧が上がります。
そのため高血圧には減塩がたいへん有効です。食塩摂取の目標値は、高血圧症治療ガイドライン2019(1) では、高血圧患者の減塩目標を6g/日未満とすることを強く推奨しています。
塩分を控えるといっても、日頃の慣れた味から薄味に変えるのは強いストレスを伴います。そこで、以下のような調理の工夫をすると上手に減塩することができます。
【調理の工夫】
-
香辛料や酸味を利用し味付けをしましょう。香りや香ばしさなども利用できると、薄味でもおいしく食べることができます。
-
だしの旨味やコクで満足感を高めるのも良いでしょう。薄味に慣れることも重要です。
-
醤油やソースは、かけるのではなくつけて食べましょう。直接かけると、かけすぎたり
-
どれだけ使ったのかわからなくなってしまいます。
どれだけ減塩の食事に切り替えても、食べ過ぎてしまうと結局塩分摂取量は増えてしまいます。さらには食べ過ぎによってカロリーも必要以上に摂ってしまい肥満の原因にもなるため、食べ過ぎにも気をつけてください。
野菜や果物を多く取り入れる
カリウムは体内から塩分を排出させる働きがあります(2)。カリウムが多く含まれている野菜や果物を積極的に摂取することで、塩分が排出され高血圧を改善させることができます。1日あたり、3500mg以上の摂取が推奨されています。
しかし、腎臓が悪い場合、カリウムが十分に排泄できなくなるため、摂りすぎには注意が必要です。腎臓が悪いことを指摘されている場合は、カリウムの摂取量は医師に相談しましょう。
また、果物には果糖という糖分が多く含まれます。糖分を摂りすぎると糖尿病のリスクが高まり、動脈硬化の進行につながります。過剰な摂取にならないよう適量を心がけることが大切です。
魚やナッツの積極的な摂取
オメガ3系脂肪酸は、血圧を下げることがわかっています。オメガ3系脂肪酸は、青魚のサンマやサバに含まれるEPAやDHA、ナッツ、植物油に含まれるα-リノレン酸などがあります。オメガ3系脂肪酸を1日2~3g摂取すると収縮期血圧、拡張期血圧ともにおよそ2mmHg程度低下することがわかっています(3)。
高血圧で食べてはいけない食品リスト
それでは、高血圧の方が食べてはいけない食品にはどんなものがあるのでしょうか。気をつけたほうがいい食品を解説します。
塩分が多い食品
塩分摂取量が多いと血圧は上昇します。次の食材は特に塩分が多く含まれているので注意しましょう。
【外食】
外食は濃い味に作られていることが多く、特にハンバーガーなどのファーストフードは塩分が多く含まれています。
【加工食品】
ソーセージ、ハム、ベーコンなどの加工食品は、細菌の繁殖を抑え食品の保存性を高めるために、塩分濃度が高くなっています。冷凍食品、缶詰、インスタント食品なども、同様の理由で塩分が多く含まれます。漬物、梅干しなど「ご飯のお供」にも塩分は多く含まれています。たとえば、梅干し1個あたり1~2gの塩分が含まれています。
【麺類】
ラーメン、うどん、そばなどの麺類も塩分が多い食品です。特に、スープには塩分が多く含まれています。スープを残すだけでも2~3gほどの減塩ができると言われているため、麺類を食べるときはスープを残すようにしましょう。
【スナック菓子】
せんべい、ポテトチップスなどのスナック菓子も塩分が多い食品です。おやつで知らず知らずのうちにたくさん食べてしまうと、塩分摂取量が多くなります。
このような食事をたくさん摂っている場合は、知らず知らずのうちに塩分摂取量が多くなってしまう可能性があります。
飽和脂肪酸を含む食品
肉の脂身、バターなどに多く含まれる飽和脂肪酸は、過剰に摂取すると悪玉コレステロールと呼ばれるLDLコレステロールを上昇させます。LDLコレステロールが高くなると動脈硬化が進行し、脳卒中や心筋梗塞などの心血管リスクを増やします(4)。
牛肉、豚肉などの赤身肉や、バター、チーズ、牛乳などの乳製品に多く含まれます。日本人の食事摂取基準(2020年版)では、飽和脂肪酸は総摂取エネルギー量の7%未満に留めることが推奨されています(5)。
コレステロールは、細胞膜やホルモン、脂肪の消化吸収を助ける胆汁酸の材料であり、生命の維持に必須の脂質です(6)。そのため、全く食べないと肌のハリがなくなったり、免疫機能が落ちたりすることがあるため、注意が必要です。
糖分が多い食品
糖分が多く含まれる食品も注意が必要です。糖分を過剰に摂取すると糖尿病のリスクが上がります。糖尿病は動脈硬化を進行させ、高血圧のリスクになります(7)。
清涼飲料水は糖分がとても多く含まれています。500mlのペットボトルにおよそ40~60gの糖が含まれています。
チョコレート、ケーキ、クッキーなどのお菓子にも、糖分が多く含まれています。お菓子には、糖分だけでなくバターなどの飽和脂肪酸も多く含まれ、高カロリーであるという特徴もあります。おやつでついつい食べすぎてしまうと、糖分だけでなくカロリー過多となって肥満の原因にもなります。肥満も高血圧のリスクとなるため、お菓子は食べすぎないように気をつけましょう。
アルコール
アルコールを摂取すると、アルコールが代謝されたアセトアルデヒドの血管拡張作用により、一時的に血圧が下がります。
しかし摂取量が多くなり飲酒習慣が続くと、血圧が上昇することが知られています。交感神経を介した作用や、電解質異常などが原因とされています。さらには、酒のつまみは塩辛いものが多く、塩分摂取量が多くなり、これも高血圧の原因になります。
飲酒が原因で血圧が高い場合は、飲酒量を減らすとそれに応じて血圧が下がることがわかっています(8)。
血圧を管理するためには、1日に摂取するエタノール量を、男性20~30mL以下、女性はその半分程度にすることが推奨されています(1)。エタノール20~30mlに相当するのは、ビール中瓶1本、日本酒1合程度です。飲酒をする場合は、この量よりも飲まないように心がけましょう。
まとめ
血圧を下げるために食べてはいけないものを解説しました。
塩分が多いものを控え、カリウムが多く含まれる食品で塩分を排出させましょう。糖分の多い食事は控え、飲酒量は控えめにしましょう。
このような食生活の見直しを行っても血圧が下がらない場合は、治療が必要な場合がありますので、病院を受診し医師に相談しましょう。