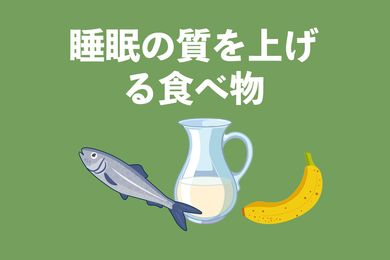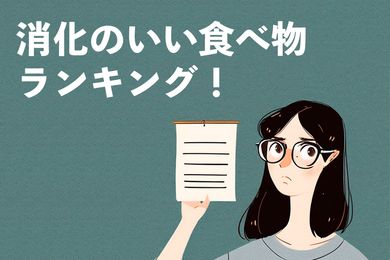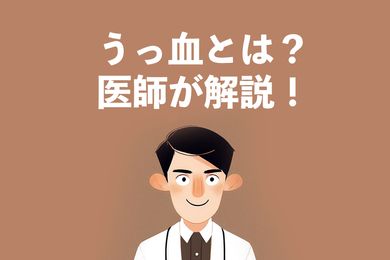不眠症とは、入眠困難、中途覚醒、早朝覚醒などによって睡眠時間が十分に取れないことや、睡眠の質が下がることで、日中に倦怠感、意欲低下、集中力低下などの体の不調が出現する状態をいいます。
不眠症は国民病と言われるほど患者が多い病気です。令和元年国民栄養・健康調査によると、1日の平均睡眠時間が6時間未満の割合は、男性37.5%、女性40.6%と高く、さらには男女とも30%を超える人がなんらかの不眠症状を有するとされています(1)。不眠症とは?
不眠症は、2014年に公表された睡眠障害国際分類第3版(ICSD-3)(2)によると、眠る機会や環境が適切であるにも関わらず、入眠困難、睡眠維持困難、早朝覚醒があり、日中の疲労、倦怠感、注意力や集中力の低下、イライラ、日中の眠気などがある状態と定義されます。少なくとも週3回かつ3ヶ月以上持続する場合を慢性不眠症、3ヶ月未満であれば短期睡眠障害と呼びます。
ICSD-3では、不眠症は不眠障害に病名が変更されています。しかし不眠症のほうが一般的に使われるため、この記事では不眠症という言葉を使用し説明します。
不眠症は、大きく分けて以下の3つのパターンがあります。
-
入眠障害:寝付くまでに時間がかかる
-
中途覚醒:夜中に何度も目が覚める
-
早朝覚醒:朝早く目が覚める
以前は熟眠障害も加えた4種類でしたが、主観的で定量化が難しいため、ICSD-3では熟眠障害は除外されました。
睡眠不足は注意力や判断力が低下し、作業効率の低下、学力低下につながり、事故等の重大な結果を招くこともあります。
また、慢性的な睡眠不足は、肥満(3)、高血圧(4)、2型糖尿病(5)、心血管障害(6)などさまざまな病気のリスクにつながります。
不眠症の原因
心理的要因
ストレスや興奮、緊張などで眠れなくなるのは誰しも経験したことがあるのではないでしょうか。仕事のトラブルや人間関係の悩みがあって眠れない、試験の前などに眠れないというのはいずれも心理的要因です。楽しいイベントの前に眠れないといった症状も心理的要因にあたります。
ストレスは、うつ病などの精神疾患につながることもあるため(7)、睡眠の質と量とともに十分な睡眠を取る必要があります。
また、うつ病も不眠の原因となります。不眠症と思っていたら実はうつ病だったということもあるため、不眠に加えて気分の落ち込みや意欲低下がある場合は医療機関を受診しましょう。
身体的要因
風邪などで咳をしている、関節リウマチや外傷などで痛みがある、アトピー性皮膚炎などでかゆみがある、頻尿であるなど、体の病気や症状があると不眠症をきたす場合があります。原因があきらかである場合は、症状を緩和する対症療法や、病気の治療により不眠が改善される場合があります。
不眠症の背景にある頻度の高い病気の一つに、睡眠時無呼吸症候群があります。睡眠中に気道狭窄が起こり途中で起きたり睡眠の質が悪くなり不眠を起こします。
足がむずむずして眠れない場合、むずむず足症候群という病気かもしれません。この病気は、眠ろうとすると足にむずむずした不快感や、脚の内側を虫が這っているような感覚があり、不眠症を招きやすいとされています(8)。
薬の副作用によって眠れない場合もあります。たとえば、ステロイド薬、抗うつ剤は不眠の原因となります。
生活習慣の要因
夜更かし、休日になかなか起きないなどといった不規則な生活リズムだと、体内時計が乱れて眠れなくなることがあります。これを概日リズム睡眠・覚醒障害と呼ばれます。
夜間勤務があって昼夜逆転の生活を送っている場合も、体内時計が狂ってしまうため不眠の原因となります。休日の寝溜めなども不規則な生活につながり、かえって不眠症を引き起こす要因となります。
コーヒーやお茶に含まれるカフェインは覚醒作用があり、不眠をきたします。また、アルコールは睡眠を浅くし、利尿作用もあることから不眠の原因となります。不眠を解消するために飲酒する方がいらっしゃいますが、睡眠導入には効果があっても結局睡眠が浅くなり不眠になり、眠るために飲酒量が増えて悪循環に陥ってしまうことがあります。
環境要因
環境が整っていないと不眠の原因になります。眠る部屋が暑い、寒い、音がうるさい、明るいといった場合、眠ることが困難になります。枕が変わったり、普段と違う部屋やベッドになったりするだけでも眠れなくなる場合があります。
不眠症の症状をチェック
もしかして私は不眠症?と不安になった方は、次のような症状がないか、不眠症の症状をチェックしてみましょう。
-
ベッドに入ってもなかなか寝付けない
-
眠るまでに1時間以上かかる
-
夜中に何度も目が覚めてしまう
-
目が覚めた後はなかなか眠れない
-
眠ったはずなのにぐっすり眠った感じがしない
-
寝てもなかなか疲れが取れない
-
朝早く目覚めてしまう
不眠症の改善策
不眠症の改善に最も有効なのは、非薬物療法です。環境を整え、睡眠の妨げとなっている原因を調べ改善することで、不眠症を治すことが可能です。
しかし日常生活に支障が出たり、環境を整えても改善しない場合は薬物療法が必要となる場合があります。
不眠症を改善させるためにはどのようなことを行えば良いか、ポイントを紹介します。
生活習慣の見直し
不眠症を改善させるためには、まずは体内時計を24時間に調整しましょう。人間の体内時計は24時間より長い周期でできているため、何もしないと生活がどんどん後ろにずれていきます。朝起きたら日光浴をすることで体内時計はリセットされ、24時間のリズムを作り、夜自然に眠くなるようにすることができます。
適度な運動を行うと疲労感が出て、寝付きが良くなり深い睡眠が得られるようになります。激しい運動は逆に睡眠を妨げるので、長続きするよう軽い運動にしておきましょう。
また、瞑想や深呼吸は副交感神経を活性化させ、リラックスして眠りにつきやすくなります。好きな音楽を聴いたり、入浴でリラックスすることも効果的です。寝る前のリラックスタイムを作ると良いでしょう。
睡眠環境の改善
深い睡眠をとるためには、睡眠に適した環境にすることが不可欠です。光や音が少ない環境を作り、入眠できるようにしましょう。遮光カーテンを使用したり、耳栓を使用したりすると効果的です。眠る前にスマートフォンやパソコンなどの光を見ると、脳が興奮して眠ることが難しくなります(9)。睡眠の質が低くなるため、眠る1、2時間前はスマートフォンの使用は控えるようにしましょう。
寝具を調整するのも良いでしょう。首や肩への負担が少ないような枕の高さを選びましょう。マットレスも体への負担が少ない寝姿勢を保てるような適度な硬さが良く、掛け布団は吸湿性、放湿性があるものを選ぶと快適に眠れます(10)。
食生活の工夫
規則正しい食生活は、体内時計を一定にする効果があります。
寝る直前に食事を摂ると、消化のため胃腸に負担がかかったり消化活動で睡眠が妨げられたりすることで、十分な睡眠が取れなくなります。夕食はできるだけ寝る3時間前までに済ませましょう。
メラトニンというホルモンは眠りに入りやすくしたり、途中で目が冷めにくくなる効果があり、セロトニンから合成されます(11)。セロトニンの材料であるトリプトファンを多く含む食事を摂ることで、セロトニンからメラトニンが生成され、眠りやすくなります。トリプトファンからメラトニンに生成されるまでには14~16時間かかるため、朝食で摂取すると夜にメラトニンに変換されます。
トリプトファンは卵、大豆製品、乳製品に多く含まれます。朝食に取り入れると効果的です。
睡眠導入として寝る前に飲酒をしている場合は、睡眠の質を悪化させるため控えましょう。寝る前のカフェインやタバコも、カフェインやニコチンには覚醒作用があり入眠困難の原因となるため、控えましょう。
医療的アプローチ
咳や、痛みやかゆみなどの症状が辛くて眠れない場合は、医療機関を受診し治療を行いましょう。症状が緩和されるだけでも不眠の症状が改善されます。
不眠になる原因がある場合は、まずは不眠の背景にある原因疾患の治療が必要です。医療機関を受診し相談してください。身体的症状がある場合は内科を、精神的症状がある場合は心療内科を受診しましょう。原因の疾患の治療で不眠が改善する場合があります。
環境調整や生活習慣の見直しなどを行っても不眠症が良くならない場合は、薬物療法を行います。睡眠薬には何種類かあり、不眠のパターンや症状に合わせて薬が処方されます。それでも良くならない場合は、精神科や心療内科などの専門医に相談しましょう。
まとめ
不眠は続くとさまざまな病気のリスクとなるため、単に不眠と楽観的に考えず、眠れる方法を考えましょう。
生活習慣の見直し、環境を整えたり、リラックスしたりするだけで眠りにつくことができるかもしれません。不眠だからとすぐに薬物療法を行うのでなく、まずは環境調整を行いましょう。
この記事で紹介したことを実践しても眠れない場合は、医療機関を受診し医師と相談しましょう。
<関連記事>
GABA(ギャバ)成分情報|入眠のサポート&ストレスの緩和効果・副作用
こちらもご参考に:『医療情報提供のオンラインクリニック