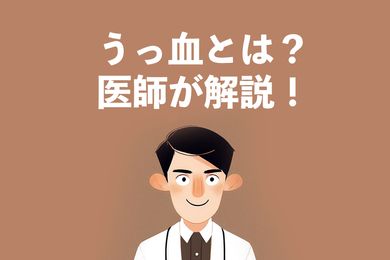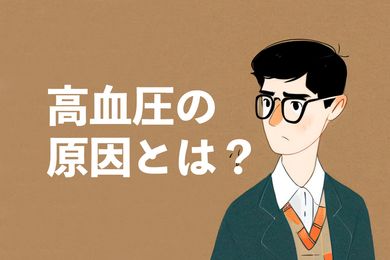高血圧とは?
血圧とは、血液が動脈を流れる際に血管にかかる圧力の値のことです。心臓が収縮して血液を動脈へ送り出すときに血管にかかる圧を収縮期血圧、心臓が拡張したときの圧を拡張期血圧といいます。
血圧は血管の弾力性、血管の太さ、血流量の3要素により決まります。心臓は血液をポンプ機能により、血液が流れるホースである動脈へ送り出します。末梢血管まで血液が流れ細胞に酸素をいきわたらせたあと、静脈を通って心臓まで戻ります。そのため、以下のようなことが起こると血圧は上昇します。
- 血管の弾力性が低下
- 末梢血管が細くなる
- 血液の量が増える
また、そのほかにも腎臓や内分泌系などの多くの因子によって調整されています。
血圧がとても高くなると頭痛やめまいなどの症状を起こす場合がありますが、ほとんどの場合は症状がないため放置されていることもあります。高血圧を放置すると心臓や血管へ負担がかかります。心臓への負担が強くなると心不全を起こします(1)。 血管への負荷は動脈硬化を進行させ、放置すると血管がもろくなり、脳卒中や心臓病を引き起こし命に関わることがあります(2)。そのため、高血圧は放置せずに治療することが重要です。
高血圧の基準
家庭血圧は診察室血圧よりも収縮期、拡張期ともに5mmHg程度低いといわれ、定義でも若干の違いがあります。
高血圧の基準は、診察室血圧では収縮期血圧140mmHg以上または拡張期血圧90mmHgを高血圧、家庭血圧では収縮期血圧135mmHg以上または拡張期血圧85mmHg以上です。
正常血圧は診察室血圧で120/80mmHg以下、家庭血圧で115/75mmHg以下とされております。正常血圧と高血圧の間の血圧は正常高値血圧、高値血圧とよばれます。定義上高血圧ではありませんが、将来的に高血圧になるリスクが高いとされており、定期的な血圧測定が推奨されています。
血圧値の分類
(成人血圧、単位はmmHg)(3)
|
分類 |
診察室血圧 |
家庭血圧 |
||||
|
収縮期血圧 |
拡張期血圧 |
収縮期血圧 |
拡張期血圧 |
|||
|
正常血圧 |
<120 |
かつ |
<80 |
<115 |
かつ |
<75 |
|
正常高値血圧 |
120-129 |
かつ |
<80 |
115-124 |
かつ |
<75 |
|
高値血圧 |
130-139 |
かつ/または |
80-89 |
125-134 |
かつ/または |
75-84 |
|
I度高血圧 |
140-159 |
かつ/または |
90-99 |
135-144 |
かつ/または |
85-89 |
|
II度高血圧 |
160-179 |
かつ/または |
100-109 |
145-159 |
かつ/または |
90-99 |
|
III度高血圧 |
≧180 |
かつ/または |
≧110 |
≧160 |
かつ/または |
≧100 |
|
(孤立性) 収縮期高血圧 |
≧140 |
かつ |
<90 |
≧135 |
かつ |
<85 |
血圧は、運動、食事、入浴などで大きく変化します。血圧は、安静時の血圧で診断します。
血圧を測定する際は座ったあと1~2分安静にしてから測定してください。朝は起床後1時間以内、食前、排泄後、内服前に、夜は就寝前に測定することが推奨されています。
高血圧の原因
高血圧の原因はさまざまで、原因によって以下の3つに分類されます。
本態性高血圧
原因を特定できない高血圧のことをいいます。高血圧患者のおよそ9割が本態性高血圧とされています。食塩の過剰摂取、肥満、喫煙などの生活習慣、ストレス、加齢などのさまざまな要因が複合的に絡み合って発症します。
二次性高血圧
なんらかの血圧を上げる病気があり、それが原因で高血圧を引き起こすものをいいます。睡眠時無呼吸症候群、腎血管性高血圧、大動脈弁狭窄症、副腎や甲状腺ホルモンの異常などが原因となることが多いとされています。原因疾患の治療で降圧が期待できます。
白衣高血圧
病院の診察室や健診などで血圧を測定したときに高値になる状態をいいます。普段と異なる環境のためストレスを感じ、高血圧になると考えられています。家庭血圧が高くなければすぐの治療は必要ありませんが、将来的に高血圧になりやすいことが知られています。
血圧を下げる方法
高血圧は、生活習慣を見直すことで改善が期待できます。
1.塩分摂取量を減らす
食塩摂取の目標値は、高血圧症治療ガイドライン2019(3) では、高血圧患者の減塩目標を6g/日未満とすることを強く推奨しています。
令和元年国民健康・栄養調査では食塩摂取量の平均値は男性10.9g、女性9.3gと多く、目標値からは程遠い状態です。しょうゆや味噌には塩分が多く含まれているため、日本人の食生活は塩分が多くなりやすいためとされています。
減塩のために有効な食行動として厚生労働省から以下のものが提案されているので、ぜひ実践しましょう。
塩分を控えるための12ヶ条(4)
- 薄味に慣れる
- 揚げ物・汁物の量に気をつけて
- 効果的に塩味を
- 「かけて食べる」より「つけて食べる」
- 酸味を上手に使う
- 香辛料をふんだんに
- 香りを利用して
- 香ばしさも味方です
- 油の味を利用して
- 酒のつまみに注意
- 練り製品、加工食品には気をつけて
- 食べすぎないように
2.食事内容を見直す
塩分以外の食事内容も見直すことが大切です。
カリウムの摂取:
カリウムは腎臓からナトリウムを排泄させる効果があり、適切な摂取により血圧降下作用が期待できます(5)。WHOは脳血管障害や心障害を予防するために、1日あたりカリウム3500mg以上の摂取を推奨しています(6)。
カリウムはバナナやぶどうなどの果物、ほうれん草などの野菜、イモ類などに多く含まれています。カリウムは水様性のため、水に溶けて流れ出てしまわないように調理の工夫をしましょう。慢性腎臓病患者ではカリウム摂取制限が必要な場合があるため、カリウム摂取量に関して医師の指示に従いましょう。
多価不飽和脂肪酸の摂取:
魚介類に含まれるEPA、DHAなどのオメガ3系脂肪酸は、1日2~3gの摂取で血圧低下作用があり、摂取を推奨されています(3)。
ナットウキナーゼの摂取:
納豆に含まれるナットウキナーゼには、血圧の上昇を抑える効果があります。納豆1パック50gあたりおよそ1500FUのナットウキナーゼが含まれています。北米の臨床試験では、1日20000FUのナットウキナーゼを摂取すると、平均血圧を拡張期で87mmHgから84mmHgへ低下させることが示されました(7)。
3.減量、適正体重の維持
BMI(Body Mass Index)は体重(kg)÷身長(m)2で計算され、BMI≧25kg/m2を肥満と判定します。
BMI値が高いと高血圧を発症するリスクが高まることがわかっています(8)。肥満患者での減量による降圧効果はあきらかで、体重1.0kgの減少で収縮期血圧を約1.1mmHg、拡張期血圧を約0.9mmHg低下させます(9)。
4.運動
有酸素運動で高血圧を改善させましょう。運動療法によって収縮期血圧で2~5mmHg、拡張期血圧で1~4mmHgの低下が期待されます(3)。運動はややきついと感じる程度の強度で、定期的に、できれば毎日30分以上持続して行いましょう。運動療法はⅡ度高血圧以下で脳心血管病のない高血圧患者さんが対象となります。III度高血圧以上の場合は降圧後に運動療法を行ないましょう。
5.節酒
飲酒習慣は血圧上昇の原因です。1日あたりエタノールで男性20~30mL(おおよそ日本酒1合、ビール中瓶1本、焼酎半合、ウイスキーダブル1杯、ワイン2杯に相当)以下、女性はその半分に制限することが推奨されています(3)。
6.禁煙
禁煙は血圧を下げるために重要です。喫煙により交感神経が活発になり、血管収縮が起こり血圧が上昇します。また、動脈硬化を進行させ、脳心血管病の発症リスクを増加させます。
7.ストレスを溜め込まない
ストレスを感じると交感神経が活発になり、血圧が上昇します。白衣高血圧もストレスが原因とされています。睡眠をとったり気分転換をするなど、ストレスを取り除くことが大切です。
まとめ
高血圧は自覚症状がほとんどないため、指摘されても放置されている場合があります。しかし放置すると動脈硬化の進行によって心筋梗塞や脳卒中などの重篤な病気を発症することがあります。
血圧を下げるためにはバランスの取れた食事と運動が大切です。適切な食習慣や運動習慣を取り入れ、血圧を下げましょう。
また、血圧の異常を指摘された場合は、医師に相談するようにしてください。