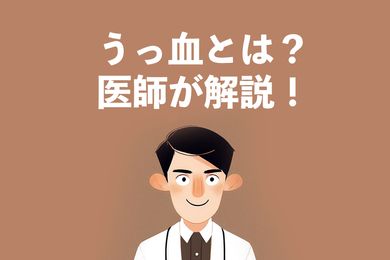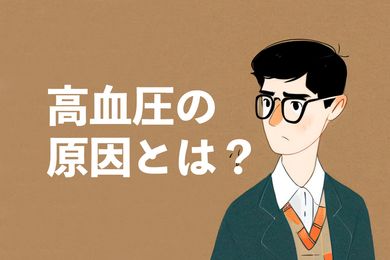高血圧は、生活習慣病のリスク要因とされています。20歳以上の成人のおよそ2人に1人が高血圧をもつ、たいへんコモンな疾患です(1)。血圧は年齢によって平均値が異なります。加齢に伴い高血圧を発症しやすくなり、特に40代から高血圧になるリスクは高まります。
この記事では、高血圧になりやすい原因と血圧を下げる方法を詳しく解説します。
血圧とは?
血圧とは、心臓から流れた血液が動脈を通る際に血管にかかる圧力の値をいいます。心臓はポンプのように収縮と拡張を繰り返し、全身に血液を送り出します。心臓から出た血液は動脈へ流れ、体の隅々を巡ったあと静脈から心臓へ戻ります。心臓が収縮して血液を動脈へ送り出すときに血管にかかる圧を収縮期血圧、心臓が拡張したときに血管にかかる圧を拡張期血圧といいます。
血圧がとても高くなると頭痛やめまいなどの症状を起こす場合がありますが、ほとんどの場合は症状がないため、指摘されても放置されていることがあります。高血圧を放置すると心臓や血管へ負担がかかります。心臓への負担が強くなると心不全を起こします(2)。 血管への負荷は動脈硬化を進行させ、放置すると血管がもろくなり、脳卒中や心臓病を引き起こし命に関わることがあります。そのため、高血圧を指摘された場合は適切な治療を行いましょう。
収縮期血圧
収縮期血圧は、心臓が収縮して血液を全身に送り出すときに、血管の内側の壁にかかる圧力です。最も強い圧力がかかるため、最高血圧や上の血圧ともいわれています。
拡張期血圧
拡張期血圧は、血液が心臓に戻ると一時的に血液をため込み心臓が拡張するときに、血管の内側の壁にかかる圧力です。血管の血液量が減り血管の壁にかかる圧力が最も低くなるため、最低血圧や下の血圧ともいわれています。
血圧の正常値
血圧は、正常血圧、正常高値血圧、高値血圧、高血圧の4段階に分類されています。さらに高血圧は重症度によって、Ⅰ度、Ⅱ度、Ⅲ度の3段階に分類されています(1)。正常高値血圧は、収縮期血圧が正常血圧の基準値以上で高血圧の基準値未満、拡張血圧が正常血圧の範囲内にある状態です。現状では高血圧と診断されませんが、このままだと将来高血圧になってしまうリスクが高いといわれています。高値血圧は、現状では高血圧とは診断されませんが、正常高値血圧よりもさらに高血圧になるリスクが高い状態です。収縮期高血圧とは、高齢者によくみられ収縮期血圧だけが高い血圧です。血圧の数値分類を以下の表にまとめました。
高血圧治療ガイドライン(3)で定義される高血圧診断基準は以下の表のとおりです。
病院で測定する診察室血圧は、自宅で測定する家庭血圧より5mmHg程度高く定義されます。診察室血圧が収縮期血圧で140mmHg以上、または拡張期血圧が90mmHg以上の場合、高血圧と診断します。正常血圧と高血圧の間は、正常高値血圧や高値血圧と呼ばれます。高血圧の定義は満たしませんが、将来的に高血圧に移行するとされています。
血圧値の分類(成人血圧、単位はmmHg)
|
分類 |
診察室血圧 |
家庭血圧 |
||||
|
収縮期血圧 |
拡張期血圧 |
収縮期血圧 |
拡張期血圧 |
|||
|
正常血圧 |
<120 |
かつ |
<80 |
<115 |
かつ |
<75 |
|
正常高値血圧 |
120-129 |
かつ |
<80 |
115-124 |
かつ |
<75 |
|
高値血圧 |
130-139 |
かつ/または |
80-89 |
125-134 |
かつ/または |
75-84 |
|
I度高血圧 |
140-159 |
かつ/または |
90-99 |
135-144 |
かつ/または |
85-89 |
|
II度高血圧 |
160-179 |
かつ/または |
100-109 |
145-159 |
かつ/または |
90-99 |
|
III度高血圧 |
≧180 |
かつ/または |
≧110 |
≧160 |
かつ/または |
≧100 |
|
(孤立性) 収縮期高血圧 |
≧140 |
かつ |
<90 |
≧135 |
かつ |
<85 |
年齢別の血圧平均値
血圧は年齢、性別によって平均値が若干異なり、加齢に伴い徐々に上昇します。令和元年国民健康・健康調査によると、年齢別の血圧の平均値は以下のようになります。
年齢別の血圧平均値(収縮期血圧/拡張期血圧)
|
年齢 |
男性 (mmHg) |
女性 (mmHg) |
|
20-29歳 |
115.3 / 67.7 |
105.7 / 63.8 |
|
30-39歳 |
117.3 / 73.7 |
107.9 / 66.3 |
|
40-49歳 |
125.8 / 81.3 |
114.3 / 71.2 |
|
50-59歳 |
131.7 / 82.0 |
123.7 / 75.4 |
|
60-69歳 |
135.8 / 78.5 |
131.0 / 76.7 |
|
70歳以上 |
135.8 / 73.1 |
136.1 / 73.0 |
この表をみると、年齢ごとに徐々に血圧が上昇しているのがわかります。40代男性の収縮期血圧は120mmHgを超えており、正常値を超え、正常高値血圧になっています。血圧が加齢とともに上昇する理由は、大きく2点あります。
血圧が加齢とともに上昇する理由
1. 加齢
年齢を重ねると生活習慣の影響が蓄積されます。塩分の多い食事、ストレス、コレステロールの蓄積などが徐々に血管にダメージを与え、血管の弾力性が落ち、動脈硬化が進行します。すると血管の弾力性がなくなり、血圧が上昇します。
若年者では血管の弾力性が十分に保たれているため、血圧は高くなりにくいと考えられています。
2. エストロゲン
先程の表をみると、閉経までの女性は同じ年齢の男性と比べて血圧が低いことがわかります。これは、女性ホルモンであるエストロゲンが関係するためです。
エストロゲンには血管拡張作用があります。血管が拡張することで血圧が下がるため、エストロゲンを分泌している期間は血圧が男性よりも低くなります。閉経期でエストロゲンが急激に減少すると、自律神経の乱れによって血圧の調整機能が落ちます。すると血圧が急激に上がり、平均値が男性とほぼ同じ値になります。
更年期の高血圧はホルモンバランスや更年期症状によっても左右されるため、血圧が不安定なことも特徴です。さらに、更年期でエストロゲンが減少すると脂質代謝にも影響します。悪玉であるLDLコレステロールが増加し、善玉であるHDLコレステロールが減少します。これによって動脈硬化が進行し、高血圧のリスクになります。
血圧の高低に基づく可能性のある疾患のリスト
血圧が正常値よりも髙くても低くても、さまざまな疾患のリスクを高めます。以下に血圧の高低に基づく可能性のある疾患を紹介します。
血圧が高いことが原因で発生する疾患
-
動脈硬化:血管の壁が厚く硬くなり、各部が必要としている血液が十分に届かなくなります。進行すると、血管の壁の堆積物が破裂し血栓となり血管を詰まらせ、心筋梗塞や脳梗塞を引き起こすことがあります。
-
脳梗塞:脳の血管が血栓で詰まり、血液の流れが滞ってしまう病気です。血液が流れない部分の細胞が死んでしまい、麻痺や感覚障害などの後遺症や最悪の場合は命にかかわるケースもあります。
-
心筋梗塞:心臓の筋肉に血液を送る冠動脈に血栓が詰まり、血液の流れが滞ってしまう病気です。血液が流れなくなった部分の細胞は死んでしまい、広範囲の心筋が酸素不足になると突然死に至るケースもあります。
-
慢性腎臓病:腎臓の機能低下や障害があらわれる病気です。初期は自覚症状がほとんどなく、貧血や頭痛、めまいなどの自覚症状が出るころには、かなり進行しているケースが多いようです。
上記以外に脳出血や腎硬化症、糖尿病、高血圧性心肥大、心不全、狭心症、大動脈瘤、認知症などさまざまな疾患を引き起こしやすくなることがわかっています(1)(4)。
血圧が低いことが原因で発生する疾患
-
脳貧血:脳に送られる血液量が低下することにより、めまいや失神などを引き起こす病気です。
-
狭心症:心筋に血液が十分に運ばれないことで酸素不足になり、胸の痛みや圧迫感を引き起こす病気です。
-
多臓器不全:血圧が急激に低下しショック状態になると、全身に血液が行き渡らなくなり複数の臓器の機能が低下してしまう病気です。
上記以外にも、心筋梗塞や不整脈なども引き起こしやすくなるといわれています。(5)(6)
まとめ
高血圧は自覚症状がなく、高血圧を指摘されても放置されている場合があります。しかし徐々に動脈硬化を進行させ、気がついたら重篤な病気を発症している場合があります。特に、40代以降は加齢やホルモンバランスの影響で高血圧になりやすいため、定期的な血圧測定を行ったり健診を受けたりすることが大切です。高血圧を指摘されたら、医療機関を受診し治療を受けましょう。