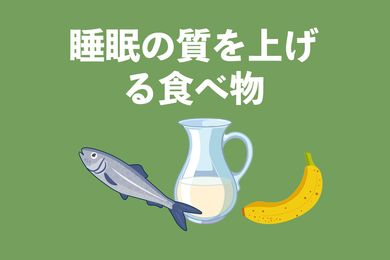睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、睡眠中に呼吸が止まることや浅くなることを繰り返す病気です。
心身の健康にとって、質の良い睡眠は欠かすことのできない要素ですが、睡眠時無呼吸症候群があると、無自覚のうちに脳が目覚めている状態が起こり、日中の眠気や倦怠感、集中力の低下を引き起こします。
また、睡眠時無呼吸症候群を放置すると、心筋梗塞、脳梗塞、生活習慣病など、さまざまな健康問題を引き起こすリスクが高まるため、早期に適切な治療を行うことが重要です。
この記事では、睡眠時無呼吸症候群の症状や原因、治療方法についてくわしく解説しています。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)とは?
睡眠時無呼吸症候群(Sleep Apnea Syndrome:SAS)とは、睡眠中に何度も呼吸が止まったり、浅くなったりを繰り返す病気です。
医学的には、「10秒以上続く無呼吸・低呼吸が1時間に平均5回以上認められ、さらに一部は心拍数や血圧のような自律神経の活動性が低く、規則正しい睡眠中にも認められる場合」と定義されます。
睡眠時無呼吸症候群では睡眠が断続的になるため、質の良い睡眠が得られず、日中の眠気や倦怠感が出現します。
また、睡眠中の酸素濃度の低下により動脈硬化のリスクが高まり、心筋梗塞や脳梗塞、高血圧などを引き起こすリスクが約3~4倍高くなることが明らかになっています。
とくに、重症の睡眠時無呼吸症候群では心血管系疾患のリスクが約5倍にもなります。睡眠時無呼吸症候群は治療により、合併症の発症や死亡率を低下させることができることが明らかになっているため、早期に専門の医療機関で適切な治療を行うことが重要です。
睡眠時無呼吸症候群は、上部の気道が閉塞して生じる「閉塞型(Obstructive Sleep Apnea Syndrome:OSAS)」、呼吸を調整する脳の働きが低下して生じる「中枢型(Central Sleep Apnea Syndrome;:CSAS)」、これらの両方が関係する混合型の3つのタイプに大きく分類されます。
睡眠時無呼吸症候群の大多数は閉塞型のタイプになっています。
睡眠時無呼吸症候群は、女性よりも男性に多く、高齢になるほど発症率が高いことが報告されています。また、女性では閉経後に増加する傾向がみられます。(1)(2)(3)(4)
睡眠時無呼吸症候群の症状
睡眠時無呼吸症候群の症状には、以下のような症状が挙げられます。本人は無自覚であることも多く、周囲の方からの指摘が診断のきっかけになることもあります。
-
十分な睡眠をとったにもかかわらず、日中に強い眠気を感じることが多い
-
周囲の人からいびきがうるさいと指摘される
-
周囲の人から睡眠中の呼吸停止を指摘される
-
睡眠中に息苦しさで目覚めることがある
-
睡眠中に頻繁に目が覚め、トイレに起きる
-
起床時に頭痛やだるさを感じる
-
睡眠中に呼吸が苦しくなる夢を何度もみる
このほか、記憶力や集中力の低下、性格の変化、抑うつ状態、性機能障害などの症状がみられる場合があります。
睡眠時無呼吸症候群は、高血圧や糖尿病を引き起こす原因となることもあります。
睡眠時無呼吸症候群を疑うような症状がある場合は、早期に専門の医療機関で検査・治療を受けるようにしましょう。(2)(3)(4)(5)(6)
睡眠時無呼吸症候群の原因
睡眠時無呼吸症候群の原因はタイプによって異なり、「閉塞型睡眠時無呼吸症候群(OSAS)」は上部の気道の閉塞、「中枢型睡眠時無呼吸症候群(CSAS)」は呼吸を調整する脳機能の低下によって起こります。
最も一般的なタイプである「閉塞型睡眠時無呼吸症候群(OSAS)」は、肥満や加齢、扁桃肥大、鼻炎・鼻中隔の弯曲、あごの後退や小ささなどが発症の原因となり、これらの原因によって上気道(鼻・口からのどまでの気道)が狭くなることにより生じます。
「中枢型睡眠時無呼吸症候群(CSAS)」は、脳が適切に呼吸を制御できないことで発生し、脳や神経、心臓の病気などが関連していることがあります。
中枢型睡眠時無呼吸症候群の原因となる疾患には、甲状腺機能低下症、脳幹梗塞、脳炎などがあります。まれに、遺伝性の疾患(先天性中枢性低換気症候群)によって生じることもあります。(3)(4)(6)(7)
睡眠時無呼吸症候群の治療方法
日中の眠気や倦怠感、睡眠中のいびきや息苦しさ、起床時の頭痛、肥満などの症状から睡眠時無呼吸症候群が疑われた場合、携帯型の簡易モニターによる検査や睡眠ポリグラフ検査(PSG)などにより、睡眠中の呼吸状態を評価し、睡眠時無呼吸症候群を診断します。
簡易モニターでは、睡眠中の鼻と口の空気の流れ、胸部と腹部の呼吸運動、酸素飽和度などを測定します。
在宅でより普段の睡眠に近い状態で検査できるというメリットがありますが、患者さまご自身で装着などを行うため、データが不正確となりやすいというデメリットもあります。
そのため、ほかの病気や睡眠障害などの疑いがなく、中等度から重度の睡眠時無呼吸症候群が疑われる場合のみ、簡易モニターによる検査を診断に使用します。
睡眠時無呼吸症候群の確定診断には睡眠ポリグラフ検査(PSG)が推奨されています。
PSGでは、脳波、眼電図、顎の筋電図、心電図、気流、呼吸努力、酸素飽和度を測定します。
1時間あたりの無呼吸と低呼吸を合わせた回数を「無呼吸低呼吸指数(AHI)」といい、睡眠時無呼吸症候群の程度を判定する指標となりますが、PSGではAHIを正確に算出できるため、より正確に睡眠時無呼吸症候群の程度を把握することが可能です。
睡眠時無呼吸症候群の治療は、原因や症状の程度により異なり、以下のような治療が行われます。(2)(3)(4)(6)
生活習慣の改善
肥満が原因と考えられる場合、体重の減量によって症状が軽減することが多く、食生活の改善や適度な運動など、生活習慣を改善することが重要です。
睡眠の質を低下させるアルコールも控えることを推奨しています。
経鼻的持続陽圧呼吸療法(CPAP)
中等度から重度の睡眠時無呼吸症候群では、経鼻的持続陽圧呼吸療法(Continuous posi-tive airway pressure:CPAP)という治療法が第一選択となります。
CPAPは鼻にマスクを装着し、持続的に空気を送ることで気道が塞がるのを防ぐ治療法です。CPAPは睡眠時無呼吸症候群に最も有効な治療方法で、日中の眠気などの症状が大幅に改善に効果があり、死亡率が低下するという報告もあります。
口腔内装置(マウスピース)
CPAP治療の適応とならない軽度から中等度の睡眠時無呼吸症候群に対しては、専用のマウスピースを装着することで、下あごを前方に移動して固定する治療方法です。
下あごの後退やあごが小さいことが原因で気道が狭くなっている方には有効な治療方法と考えられています。
手術療法
CPAPや口腔内装置が使用できない睡眠時無呼吸症候群で、扁桃肥大などによって気道が狭くなっている場合は、扁桃腺の摘出を行う手術などで症状が改善することがあります。
まとめ
睡眠時無呼吸症候群は、睡眠中の無呼吸や低呼吸によって健康に深刻な影響をおよぼす病気です。
睡眠時無呼吸症候群の症状は日中の強い眠気や集中力の低下、さらに重大な健康リスクにつながることもあるため、早期診断と治療が重要です。適切な治療を受けることで睡眠の質が向上し、日常生活のパフォーマンスも改善されます。
睡眠時無呼吸症候群の疑いがある場合は、早めに専門の医療機関でご相談されることをおすすめします。
<関連記事>
GABA(ギャバ)成分情報|入眠のサポート&ストレスの緩和効果・副作用