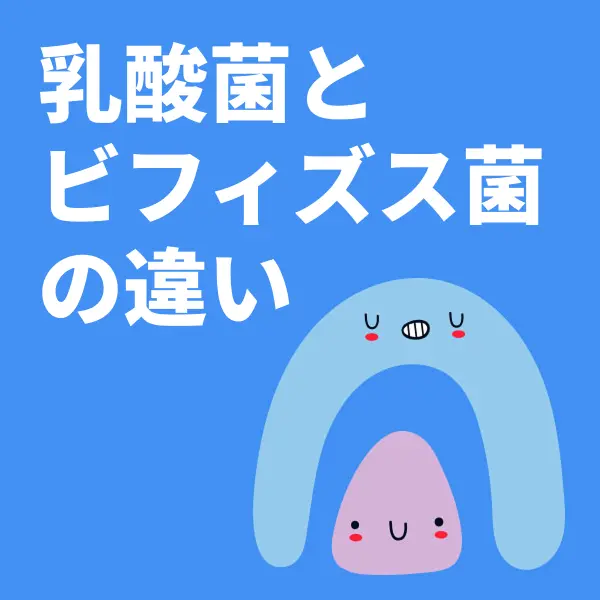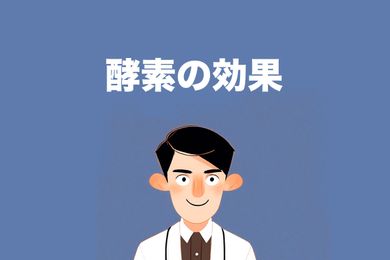ビフィズス菌と乳酸菌の違いは?実は全く別の菌!

善玉菌やプロバイオティクスという言葉を聞くと、多くの方がビフィズス菌とあわせて乳酸菌を思い浮かべるかと思います。
しかし、ビフィズス菌と乳酸菌がどのような関係にあるのかについてご存知の方はあまり多くないかもしれません。
違い1. ビフィズス菌と乳酸菌の定義
もともと「乳酸菌」という言葉は、「糖を代謝して乳酸を多量に作る菌の総称」として使われていました。しかし、近年のゲノム解析などの進展により、その定義が見直されています。(1)
現在では、「乳酸菌」は主にLactobacillales(ラクトバチルス目)に属する菌が該当します。
一方で、ビフィズス菌(Bifidobacterium属)は、分類上はアクチノバクテリア門に属し、乳酸菌とはまったく異なる系統の細菌です。
違い2. ビフィズス菌と乳酸菌が生成する物質
乳酸菌が主に乳酸を生成するのに対し、ビフィズス菌は酢酸や酪酸などの短鎖脂肪酸を多く生成し、免疫調整や脂肪蓄積の制御といった健康機能にも関与しています。
違い3. ビフィズス菌と乳酸菌のすむ場所
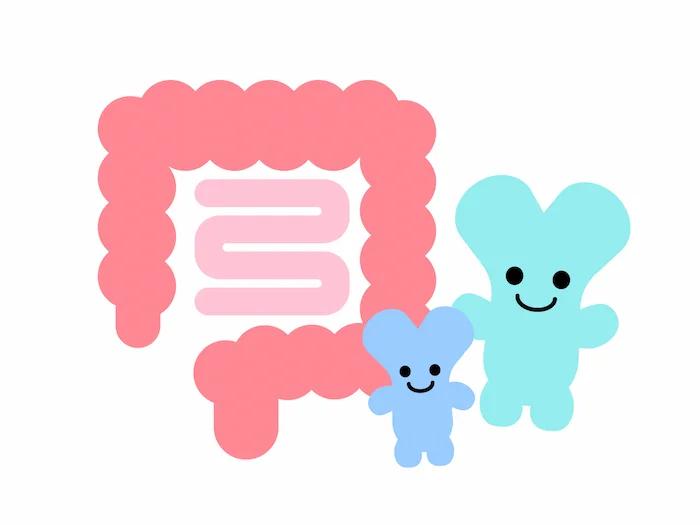
ビフィズス菌は乳酸菌とは異なる分類に属し、性質も大きく異なります。たとえば、乳酸菌の多くは酸素が存在しても生育可能ですが、ビフィズス菌は嫌気性(酸素を嫌う性質)であり、酸素下では生育しにくい特徴があります。
また、生息する場所にも明確な違いがあります。ビフィズス菌は主に大腸に生息し、乳酸菌は主に小腸に生息しています。
この違いの理由は、それぞれの菌が好む環境条件が異なるためです。小腸は消化・吸収が盛んな場所であり、腸壁の血流も豊富なため、比較的酸素が存在します。そのため、ある程度の酸素でも生育できる「通性嫌気性菌」である乳酸菌にとっては、小腸が適した環境となります。
一方、大腸は内容物の通過が遅く、酸素の供給もほとんどないため、酸素を嫌うビフィズス菌にとって最適な無酸素環境(嫌気環境)が整っています。さらに、大腸には乳酸菌よりも多様な糖質(オリゴ糖や食物繊維の発酵生成物など)が存在し、ビフィズス菌の栄養源として利用されやすいことも大きな理由です。
実際、腸内細菌の構成を調べた研究では、大腸内では約99.9%がビフィズス菌であり、乳酸菌はわずか0.1%程度と報告されています(朝日新聞 Re:ライフ より)。
|
項目 |
ビフィズス菌 (Bifidobacterium) |
乳酸菌 (Lactic acid bacteria) |
|
分類 |
ビフィドバクテリウム属(Bifidobacterium) |
ラクトバチルス属(Lactobacillus)など、Lactobacillales目に属する菌 |
|
学術定義 |
乳酸菌とは別の菌だが、生理学的に関連性がある |
「乳酸を多量に作る菌」の総称。現在はLactobacillales目の菌を指す |
|
主な機能や効果 |
腸内環境の改善、免疫調整、脂肪蓄積抑制、大腸の健康維持 |
腸内環境の改善、整腸作用、消化サポート |
|
主な生息場所 |
大腸(酸素の少ない環境を好む) |
小腸(酸素がある環境でも生育できる) |
|
酸素への耐性 |
酸素が苦手(嫌気性) |
酸素があっても生きられるものが多い(通性嫌気性など) |
|
代謝の特徴 |
乳酸に加え、短鎖脂肪酸(酢酸など)を多く産生する |
主に乳酸を産生する |
体内から整える:乳酸菌

「乱れた生活習慣をなんとかしたい」「体調が気になる」方へ、1,000億個以上の乳酸菌で体内フローラを補給し、体内から調子を整えてみませんか?
乳酸菌は善玉菌の一種です。体内の微生物のバランスを健康に保ち、乱れたときは健康な状態へ戻してくれる可能性が示唆されています。
疲労やストレスをため込んでしまうと、暴飲暴食や不規則な食事などの負のループに陥りがちです。また、さまざまな不調が起こり、体内が乱れていく場合があります。
この「乱れ」を整えて、「守る」働きをサポートしてくれるのが乳酸菌です。
乳酸菌サプリメントの特徴
-
1袋1,000億個以上の乳酸菌で体内フローラの補給にサポート
-
厳選された、研究報告されている5つの菌株。さらにビフィズス菌と乳酸菌のW配合
-
母から子に受け継がれる「守る」!ヒト由来3つの乳酸菌を使用
-
季節を問わず、体調管理の仲間になり、ムズムズの時期も健康維持に