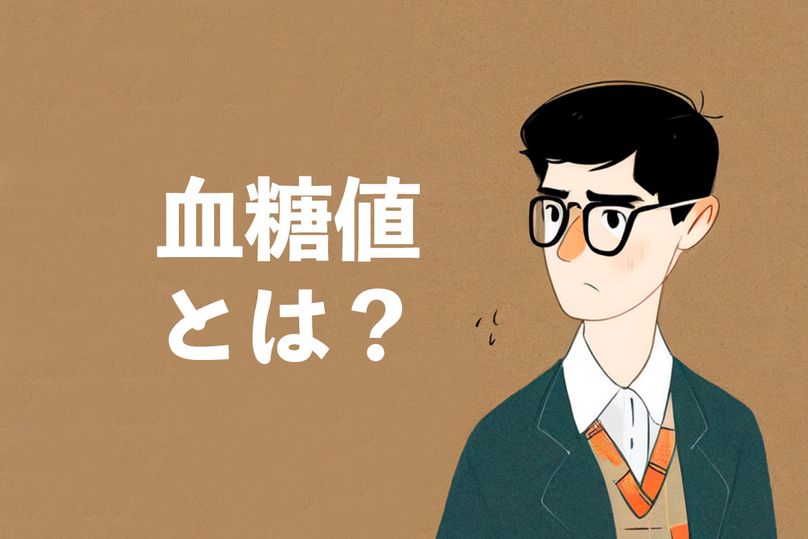健康診断で「血糖値が高い」と言われたけれど、意味もわからないし症状もないので放置しているという方が少なくありません。血糖値とは「血液中に含まれるブドウ糖の量」のことであり、血糖値が高いまま放置すると、糖尿病などの病気につながる可能性があり、血糖値のコントロールは健康を維持する上で非常に重要なポイントとなっています。
この記事では、そもそも血糖値とは何かについて説明するとともに、血糖の正常値、特に食後血糖値と空腹時血糖値について詳しく解説します。また血糖値はどうして上がるのか、さらに血糖値が上がった場合の症状についてまとめ、最後に血糖値を下げる生活習慣をいくつかご紹介いたします。
血糖値とは?
血糖値とは、「血液内のブドウ糖の濃度」と定義されています(1)。ブドウ糖は糖類の一種であり、人間を含む動物や植物のエネルギー源として用いられる物質です。特に脳にとっては唯一のエネルギー源であり、生きていく上で欠かせない栄養素の一つに数えられます。
ブドウ糖は、糖類の中でもそれ以上分解できない単糖類に分類されています。グルコースと呼ばれることもあります。
血液中のブドウ糖(=血糖)は、多すぎず少なすぎず、常に適切な量である必要があります。血液中のブドウ糖が足りない(=血糖値が低すぎる)と、エネルギー不足による疲れや集中力の減少、意識障害などが起こることがあります。また血液中のブドウ糖が多すぎる(=血糖値が高すぎる)と、糖尿病になる可能性があります。
血糖の正常値
血糖の正常値は、食事をした時間と採血した時間の関係によって変わります。絶食後10時間以上経ってから測定した血糖値のことを「空腹時血糖値」、食事の後で測定した血糖値のことを「食後血糖値」と呼んでいます。
空腹時血糖値は「絶食10時間以上」、つまり最後の食事から10時間以上空けて測定した血糖値です(2)。空腹時血糖値は、1日のうちで最も低いタイミングでの血糖の値を示しています。空腹時血糖の正常値は100mg/dl未満です。100-109mg/dlの場合は正常高値と呼ばれますが、この数値が長期間で続けると、将来的に糖尿病に罹患する危険性があるため注意しましょう。
食後血糖値とは、食事をしてから2時間後に測定した血糖の値を指すことが多いです。食事の後に血糖値がどのくらい上がるかを示しています。正確な医学用語ではありませんが、1日のうちで最も血糖値が高くなるのが食事をしてから約2時間後と言われていること、糖尿病の診断で行う糖負荷試験は食後2時間後の血糖値を測定して行うこと、また食後血糖値が高いこと(食後高血糖)は糖尿病の予備軍であることなどから、注目を集めています。食後血糖値が140mg/dlを超えると、食後高血糖と診断されます(3)。
随時血糖とは、食事をした時間を問わずに測った血糖値のことです(4)。基準値は200mg/dl以下となっています(5)。
血糖値が上昇する仕組み
血糖値は、食事を摂ると上昇し、食事からある程度の時間が経過するとともに低下します。食べ物や飲み物に含まれる炭水化物が腸で吸収され、ブドウ糖に分解されて血液中に入るからです。血液中に入ったブドウ糖は全身の細胞に取り込まれ、エネルギーとして使われて消えるので、時間とともに血糖値は下がります。
細胞が血液中のブドウ糖を取り込むときに必要なのが、膵臓(すいぞう)から分泌される「インスリン」というホルモンです。インスリンは、血糖値を下げる唯一のホルモンです。インスリンの働きは主に2つあります。
一つは、細胞の壁にある「ブドウ糖の通り道」を開ける鍵の役割です。インスリンが細胞にある鍵の部分(受容体)に結合するとブドウ糖が通るための通路が開き、細胞内にブドウ糖が取り込まれます。インスリンがたくさんあるとブドウ糖が通れる通路が増え、血糖値は下がるのです。なんらかの理由でインスリンが想定よりも少ない、もしくはインスリンが壊れていて鍵の役割を果たせないと、細胞内にブドウ糖が取り込めず、血液中に余ってしまい血糖値が高くなります。
インスリンのもう一つの機能は、細胞内に取り込まれずに余ったブドウ糖を中性脂肪やグリコーゲンに変えて身体に蓄えることです。
これら2つの働きにより、食事の後に上がった血糖値は空腹時のレベルにまで下がるのです。
血糖値が上がる症状
血糖値が高くなると、喉が渇く、尿が増える、体重が減る、疲れやすくなる、意識障害などの症状が出ることがあります。
コントロールされているはずの血糖値が正常を超えて上昇する原因としては、血糖を細胞に取り込むのに必要なインスリンの量が足りない、もしくはインスリンの量は足りているが働きが弱くて血糖が下がらない、ブドウ糖の原料となる食べ物の摂りすぎ、のいずれかが考えられます。
血糖値の上昇と関連する可能性のある病気として、主なものに糖尿病があります。そのほか、下垂体や副腎・甲状腺などの病気の一部(内分泌疾患)や先天性風疹などの感染症、 Down症候群など一部の遺伝性症候群などで血糖値が上がる可能性があります。さらにステロイドやインターフェロンなど、薬の影響で血糖値の上昇が見られることもあります。
血糖値を下げる生活習慣
血糖値は、生活習慣を変えることによってある程度下がります。特に血糖値が気になる方で肥満の方については、体重を減らす生活習慣を取り入れましょう。内臓脂肪が多いとインスリンの効きが悪くなり、血糖値が上がりやすくなります。
食事
血糖値を下げる生活習慣として、まずは、食事の見直しから始めるのが最も簡単です。一番やりやすいのは食事の量の見直しです。満腹になる一歩手前の腹八分目で食事をストップするところから始めましょう。面倒な計算も必要なく、今すぐ手軽にできるのに効果が高い方法です。
食事の量とともに、取り方も見直すポイントがいくつかあります。1日3食(朝・昼・晩)を規則正しく摂ること、夜寝る前には食べないこと、ゆっくりよく噛んで食べることなどに気をつけてみましょう。
食事の内容で注意したいポイントは、バランスの良い食事を摂ることです。身体に必要な栄養素には、ブドウ糖の原因となる炭水化物のほかに脂質とタンパク質がありますが、これらのバランスを取ることが大切です。野菜やきのこ・海藻類なども積極的に摂りましょう。加工食品はできるだけ避けましょう。
またアルコールの摂りすぎには注意が必要です。適度な飲酒(1日あたりアルコール換算で20〜25g)は糖尿病の発生を抑えるとする報告もありますが、飲みすぎは血糖値を上昇させる可能性が指摘されています(6)。お酒はほどほどにしておきましょう。
運動
定期的な運動も、血糖値を下げるために良い習慣です。体を動かすと血液中のブドウ糖が筋肉に取り込まれて使われることで血糖値が下がります。また運動によって内臓脂肪が減ると、インスリンの効きが良くなります。
おすすめしたい運動の種類としては、有酸素運動全般、特に手軽に始められるウォーキングなどがあります。まずは通勤の時に駅まで歩く、職場ではなるべく階段を使うなど、できることから始めてみましょう。ゆっくり歩きだけでなく、ところどころ早歩きを入れると、さらに効果的です。さらに余裕がありそうと言う場合は、まっすぐ立って踵を上げ下げするような筋肉トレーニングを取り入れると良いでしょう。
禁煙
そして、生活習慣管理の中で最も重要なものとして、禁煙があります。タバコを吸っている人は、今すぐ禁煙しましょう。タバコを吸う人は、吸っていな人と比べて2型糖尿病に1なる確率が1.4倍も高いことがわかっています(7)。また本数が多いほど、糖尿病になりやすいという報告もあります(7)。さらに、タバコを吸っている方は、吸わない方と比べると、糖尿病になった時に心筋梗塞や脳梗塞で死亡する危険性が1.5〜3倍も高いことが知られています。喫煙者が糖尿病になりやすい理由として、タバコを吸うことによって交感神経の働きが高まり、血糖値が上がりやすくなると同時にインスリンの効きが悪くなることが原因の一つとして考えられています。
まとめ
以上、そもそも血糖値とは何か、血糖値の正常値と血糖値が上がる仕組みなどについて説明するとともに、血糖値を下げる生活習慣についていくつかご紹介いたしました。
血糖値の管理は健康を保つために欠かせない要素であるとともに、ある程度は自分でコントロールできるものです。今回ご紹介した良い生活習慣を維持するとともに、年に1度の健康診断で血糖値を測定する習慣をつけましょう。また健康診断は受けっぱなしにせず結果をきちんと確認し、血糖値が高ければ医療機関を受診しましょう。