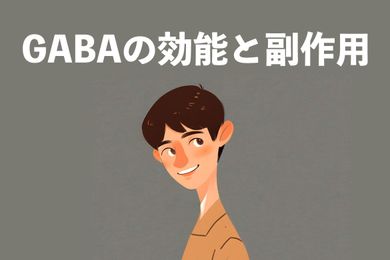皆さん、ブドウ糖についてどれくらい知っていますか?「ブドウ糖」と聞くと、甘い物をイメージするかと思いますが、実はブドウ糖は脳唯一の栄養素であり、又体を動かす為の大切なエネルギーの源です。
勉強している時、体を動かした後、甘いものが食べたくなった事はありませんか?それは、ブドウ糖を摂取する事で脳が活性化したり、疲労回復につながるからです。エネルギーの源であるブドウ糖について解説していきます。
ブドウ糖とは?
ブドウ糖の学名は「グルコース」です。果物や穀物など身近な食べ物に含まれています。日本では、ブドウから発見されたので、「ブドウ糖」と呼ばれていますが、化学の分野では、「グルコース」と呼ばれています。
人間の体に必要な三大栄養素といえば、「炭水化物」「脂質」「たんぱく質」です。「炭水化物」には体内に吸収される「糖質」と体内に吸収されない「食物繊維」に分けられます。炭水化物を分類すると、「糖類」「オリゴ糖」「多糖類」。
糖質は「単糖類」「少糖類」「多糖類」「糖アルコール」「その他の糖質」に分かれています。
-
単糖類には、ブドウ糖、果糖、ガラクトース、リボースがあります。
-
少糖類には、ショ糖、麦芽糖、乳糖、オリゴ糖があります。
-
糖アルコールには、キシリトール、ソルビトールがあります。
-
その他の糖質は、アスパルテーム、アセスルファムカリウム、ステビアがあります。
厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」策定検討会報告書より、「基礎代謝量を、1,500kcal/日とすれば、脳のエネルギー消費量は3000kcal/日になり、これはブドウ糖75g/日に相当する。脳以外の組織もブドウ糖をエネルギー源として利用することから、ブドウ糖の必要量は少なくとも100g/日と推定され、すなわち、糖質の最低必要量はおよそ100g/日と推定される。(2020年版策定検討会報告書より引用)
糖質は体内で消化吸収されてブドウ糖となり、脳や筋肉のエネルギーとして使用されています。その中でも脳はブドウ糖を唯一の栄養素として使用するため、糖質が不足すると、集中力や思考力の低下により、疲労を感じやすくなることがあります。
また、血液中のブドウ糖(グルコース)の量を「血糖値」と言い、血糖値は高すぎても、低すぎても体に影響を与えます。そのため、適切な血糖値を維持することで健康を保つ事が大切になります。
ブドウ糖の効果
体の重要な源
「炭水化物」には糖質と食物繊維に分かれており、糖質は体に吸収される重要な栄養素です。糖質は体内で消化吸収されてブドウ糖となり、脳や筋肉のエネルギーとして使用されています。
集中力
血液中のブドウ糖(グルコース)の量を「血糖値」と言い、血糖値は高すぎても、低すぎても体に影響を与えます。そのため、適切な血糖値を維持することで健康を保つ事が大切になります。
空腹になる事で糖質不足(血糖値が低くなる)になり、イライラしてしまう傾向があります。血糖値が低くなることで、脳のエネルギーが不足し、集中力や思考力の低下に繋がります。
疲労回復
ブドウ糖はインスリンの作用で筋肉のエネルギー源にもなるため、糖質が不足することで、身体が疲れやすくなります。ブドウ糖は素早くエネルギーに変換され、脳のエネルギー源や、筋肉へのエネルギーとなるため、疲労回復に繋がります。
ブドウ糖を含む食べ物
|
食品名 |
100gあたりのブドウ糖(g) |
|
はちみつ |
33.2g |
|
干しブドウ |
28.6g |
|
プルーン(乾燥) |
24.6g |
|
トマトケチャップ |
11.1g |
|
バナナ(乾燥) |
9.0g |
|
ぶどう(皮なし・生) |
7.3g |
|
パイナップル缶 |
7.1g |
|
いちじく |
5.6g |
|
キウイフルーツ |
5.0g |
|
柿 |
4.8g |
出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」
「ブドウ糖」は、人間が生きていく上で重要な栄養素の一つです。健康的な生活を送るために摂り過ぎには注意し、適切な量をバランスよく摂取することが大切です。
ブドウ糖と糖質の違いとは?
グルコースと糖のエネルギー変換について
ブドウ糖(グルコース)は血糖として身体の中を循環しています。
生物が利用することのできるエネルギー源は、糖、脂肪、たんぱく質ですが、細胞の代謝の化学反応を進ませるための化学的なエネルギー源はATP(アデノシン三リン酸)です。このATPによって細胞内では色々な化学物質が合成・分解され代謝産物を細胞が利用しています。
砂糖とブドウ糖の甘さの違い
ブドウ糖(グルコース)は、自然界に最も多く存在する単糖類です。単糖類とは、それ以上分解できない糖類です。
一方、砂糖は、ブドウ糖と果糖が結合してできた甘味をもつ調味料です。甘さという点では、「ブドウ糖」の方が「砂糖」より劣り、「砂糖」に比べて7割程度の甘さしか感じられません。
「ブドウ糖」は砂糖に比べて吸収効率に優れていることから医薬品として扱われており、「砂糖」は医薬品として扱われることはありません。
ブドウ糖の摂取目安
2020年版日本人の食事摂取基準【1】では、糖質と食物繊維を合わせた炭水化物としての摂取目標が示されており、性別や年齢に関係なく摂取エネルギー量の50~65%が目標値として設定されています。
ブドウ糖単体では特に基準はなく、世界保健機構(WHO)の基準を参考にすると、砂糖などの甘い糖分は1日25gまでが目安といわれています。この25gには、他の菓子類や飲料、調理に使う砂糖も含まれるため、すべてをブドウ糖から摂取してよいわけではありません。また、糖尿病などの疾患によって、摂取量の目標値は異なってくるので摂取量には注意が必要です。
ブドウ糖の摂取における注意点
高血糖による疾患・症状について
血糖値とは、血液中に含まれるブドウ糖(グルコース)の濃度のことをさします。食事中に摂取される炭水化物、穀物、果物を摂取することで、消化吸収されブドウ糖となり血糖値の濃度が変化します。どんな健康な人でも食事の前と後では血糖値は変化します。その中でも血糖値が高くなる事で起こる代表的な疾患が「糖尿病」です。
糖尿病とは?
食事により摂取された栄養素の一部はブドウ糖となって、腸から吸収されます。食事をしない、寝ている間も、主に肝臓によりブドウ糖が作られています。ブドウ糖は常に体の血液中を巡り、臓器や組織へと運ばれ、インスリンの力を借りて、組織へ取り込まれていきます。そのため、血液中の糖の濃度は一定の範囲におさまっています。
しかし、糖尿病になると、インスリンが十分に働かないことで血液中の糖分が増加し、様々な症状を引き起こします。
糖尿病の症状とは?
糖尿病では、かなり血糖値が高くならなければ症状が現れないため、気が付かない人も多くいます。
- 喉が渇く、水分をよく飲む
- 尿の回数が増える
- 体重が減る
- 疲れやすくなる
血糖値が高い状態が続くと意識障害に至ることもあるので、大変危険です。また、血糖値が高い状態が続くことで、進行すると、失明、腎不全、足壊疽、脳梗塞、心筋梗塞など様々な合併症に繋がり、生活の質を著しく低下させます。
血糖を脂肪に変換するメカニズム
「炭水化物」「脂質」「たんぱく質」は、食物から摂取しすぎると全て体脂肪として蓄えられます。
摂取したエネルギーに対して、消費するエネルギー量が少なければ、その余ったエネルギー量が体脂肪として蓄えられます。体脂肪とは、中性脂肪のことで、中性脂肪はグリセロールと3つの脂肪酸から構成されています。糖質を摂りすぎると、余ったものはグリセロールに似た形をした物質と、脂肪酸に似た形をした物質を作り出して「中性脂肪」を生成します。中性脂肪は脂肪組織として体内に蓄積され、これが肥満に繋がります。
ブドウ糖不足の注意点
ブドウ糖不足による症状
ブドウ糖は体内のエネルギー源となる大切な栄養素です。不足することで次のような症状が起こる可能性があります。
低血糖とは
低血糖とは、糖尿病を薬で治療されている方に高い頻度でみられる緊急の状態です。一般に、血糖値が70mg/dl以下になると、人の体は血糖値をあげようとします。
また、血糖値が50mg/dl未満になると、脳などの中枢神経が糖の不足の状態になり、特有の「低血糖症状」が起こります。
血糖値に応じて様々な「低血糖症状」が表れます。
70mg/dl以下の場合:汗をかく、不安な気持ち、脈拍が速くなる、手や指が震える、顔色が青白くなる。50mg/dl程度の場合:頭痛、目のかすみ、集中力の低下、生あくび50mg/dl以下の場合:異常な行動、けいれん、昏睡(意識のない状態)
低血糖の原因として
- 食事量や炭水化物の不足
- 糖尿病薬を使ったあとの食事の遅れ
- 運動の量や時間が多い時の運動中、運動後
- 空腹での運動・インスリン注射や飲み薬の量が多い
- 飲酒
- 入浴
低血糖が起きた時の応急対応として、10gブドウ糖又は、ブドウ糖を含む飲料水150ml~200mlをとる。(砂糖の場合は、砂糖20g)すぐに医療機関で医師の治療を受けてください。