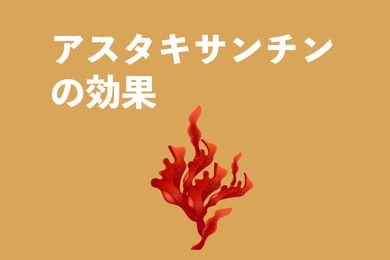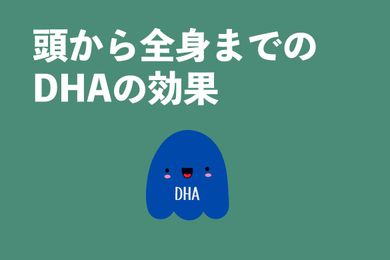近年タウリンに多くの注目が集まっています。体力を要する作業やスポーツをはじめる前、また疲労を感じたときなどに、タウリン入りの「医薬品」や「医薬部外品」にあたる栄養ドリンクを手にしたことのある人は多いのではないでしょうか。それは、タウリンには、持続的なエネルギーを提供し疲労を回復させる効果があると考えられているからです。
しかし、本当にそうなのでしょうか?タウリンには「医薬品」として確認された効果もありますが、多くの研究の結果解明されてきたさまざまな作用があります。
この記事では、タウリンの効果や作用と、食材からタウリンを効率良く摂取する方法を薬剤師が解説します。タウリンに対して知見を深めるきっかけにしてみてください。
タウリンとは?
タウリン(Taurine)は、アミノ酸とよく似た構造をしている「アミノ酸誘導体」です。アミノ酸の構造式にはアミノ基(-NH3)とカルボキシル基(-COOH)がありますが、タウリンの構造式にはカルボキシ基の代わりにスルホ基(-SO2-OH)があります。スルホ基には硫黄元素(S)が含まれているのが特徴です。。
タウリンはカニ、エビ、イカ、タコ、海藻などの魚介類に多く含まれています。これらを食べることでタウリンを体内に摂取できますが、人は体内でシステインなどの含硫アミノ酸からタウリンを自己合成できます。摂取されたタウリンは、腸管から吸収され血液中に移行し、タウリンを必要とする細胞へ取り込まれます。水に溶けやすく、またほとんど代謝を受けないことから、使われなかったタウリンは腎臓から尿中に排泄されます。
一般的に、体重の約0.1%のタウリンが人体には含まれており、脳、心臓、肝臓、筋肉、網膜などに多く存在します。人の赤ちゃんは、出生後徐々にタウリンを自己合成する能力を持つようになるため、新生児期はまだ母乳やミルクからタウリンを摂取する必要があります。そのため、タウリンは母乳にも豊富に含まれていることがわかっています。
日本において、タウリンは「専ら医薬品として使用される 成分本質 (原材料) 」に区分されており、原則として抽出物や生成物として食品に添加できません。 魚介類などに含まれるタウリンは天然のタウリンですが、栄養ドリンクなどに含まれるタウリンは合成されたタウリンです。栄養ドリンクの瓶をよく見ると、「医薬品」や「医薬部外品」ではなく、「清涼飲料水」とかかれている製品もあります。清涼飲料水は食品に該当するため、日本ではタウリンを含むことができず、かわりにアルギニンなどのアミノ酸やカフェインが含まれています。また、タウリンは「肝・循環機能改善剤 MELAS 脳卒中様発作抑制剤」として実際の医療現場で医師によって処方される医療用医薬品でもあり、うっ血性心不全の症状や肝機能の改善に使用されています。
タウリンの効果とは?
効果1:血糖値を下げる
本来食事によって血糖値が上がると、インスリンというホルモンが分泌され、血糖値が下がります。このインスリンを作っている膵臓の細胞が破壊されたり、インスリンの働きが悪くなったりすると、血糖が下がりにくくなり糖尿病になります。
糖尿病になると、血管がもろくなって傷つくことで、様々な合併症が引き起こされます。糖尿病性網膜症・糖尿病性腎症・糖尿病性神経障害などが徐々に進行すると、視力障害、腎不全、手指足指の壊死からの切断につながります。日頃から血糖値に関心を持ち、糖尿病のリスク軽減につとめる生活習慣を心がけることが大切です。
タウリンには、膵臓の細胞の機能低下を抑え、インスリン抵抗性を改善する作用があるため、タウリン摂取は血糖値の低下につながると考えられています。
効果2:肝臓の機能を改善
肝臓でコレステロールから作られる胆汁酸は、タウリンと抱合することで水に溶けやすくなるため、胆汁に溶け込めるようになります。すると肝臓から胆汁が排泄されやすくなり、胆汁中に含まれるビリルビンも排出され、高ビリルビン血症を改善することがわかっています。
また胆汁酸には毒性があり、肝臓内に胆汁酸が滞っていると肝障害につながります。タウリンと抱合することで胆汁酸が肝臓から排出されやすくなったため肝障害が起こりにくくなり、タウリンには肝細胞保護作用があることがわかります。タウリンはこれらの様々な作用により、肝機能異常を改善 しています。
効果3:疲労回復、運動パフォーマンスの向上
タウリンは、特に持久力の必要な運動パフォーマンスの向上効果が期待されています。また、タウリンを摂取することで運動をして疲労を感じるまでの時間が長くなったという報告もあります。タウリンを運動直前に急性に服用した方が良いのか慢性的に服用していた方が良いのかといった摂取タイミングに関する課題、タウリンは多く摂取すればそれだけ効果が期待できるのかといった適切な用量に関する課題については、さまざまな研究が行われています。
タウリンと疲労回復との関係性について明らかにはなってはいませんあが、ビタミンBが栄養素のエネルギー変換に関係しているのと同様に、タウリンは脂肪の代謝に関係していることがわかっています。このようなエネルギー生成につながる作用によって、タウリン摂取が疲労回復につながっていると考えられています。
効果4:心機能の低下の改善
心臓は、細胞内にカルシウムイオンが取り込まれると収縮し、流出すると弛緩します。心不全の場合は、このカルシウムイオンの動態に問題が発生し、心臓がうまく収縮弛緩できなくなり全身への血液の流れが悪くなっている状態です。タウリンには、心不全の症状である息苦しさや疲労感、浮腫などを改善したとの報告があります。
タウリンは、心臓の細胞内におけるカルシウムイオンが少ない時には取り込みを促進し、カルシウムイオンが多い時には取り込みを抑制することで、カルシウムイオンの動態を調節しています。その結果、心筋の収縮力の調節につながり、心機能の低下を改善させることがわかっています。これ以外にも、タウリンの心機能の改善の作用がいくつか報告されてきています。
タウリンが不足すると?
人体のタウリンが不足すると、心臓や肝臓の機能が低下したり、脂質や糖の代謝に異常が生じる可能性があります。疲労、めまいなどの症状が現れるかもしれません
また、タウリンは網膜にも多く存在しているため網膜の機能に異常が生じ視覚障害が起きる可能性もあります。
タウリンを含有する食品
肉類(特に赤身)、乳製品、魚介類にはタウリンが含まれています。
タウリンを多く含む食品は以下です。
魚介類:カニ、エビ、イカ、タコ、アジ、サバ、ブリやマグロの血合い
貝類:ハマグリ、シジミ、カキ、サザエ、ホタテ
近海魚:アジ、サバ
日常的にバランスのとれた食事をとることで十分なタウリンを摂取できます。しかし、野菜や果物などの陸上の植物にはタウリンは含まれていないため、完全な菜食主義者の場合、十分な量のタウリンを食事から摂取できない可能性があります。
タウリンを効果良く摂取する方法
タウリンは水溶性物質のため、油と一緒に摂取しなくても人体に吸収されます。逆に、タウリンを含む食材を水に漬けて保存したり茹でたりすると、タウリンは水分の方へ溶けだしやすくなります。そのため、刺身としてそのまま食べたり、煮汁ごと飲めるスープなどに調理すると、タウリンを効率良く摂取できます。
しかし、摂取されたタウリンは長時間体内にとどまらず、使われなかった分は尿中に排泄されてしまいます。医療用医薬品として投与されたタウリンは、投与約 1 時間に血中濃度が最も高くなり、約2時間後には血中濃度は半減し、7 時間後には通常の生体内濃度にまで減少しました 。これらのことより、タウリンは一度に大量に摂取するより日常的に摂取することが重要であることがわかります。
タウリンの摂取量
日本において、タウリンの毎日の推奨摂取量は具体的に定められておらず、厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2020版)」においてもタウリンに関する記載はありません。
- タウリンは体内で自己合成できる
- 体内で使われなかったタウリンは、余剰分として尿中に排泄される
これらの理由により、タウリンには摂取目安が定められていないと考えられます。
タウリンの摂取が勧められる方
- 高ストレスや長時間労働のビジネスパーソン
- アスリートや運動パフォーマンスが気になる方
- 完全な菜食主義の方
- 乳幼児や小児(タウリンは子供の発達に非常に重要であるため多くの乳児用粉ミルクに添加されています)
タウリンに副作用はあるの?
タウリンは水溶性のため、基本的には余分なタウリンは尿中に排泄され体内に蓄積されることはありません。過剰な摂取が続かない限り、通常は副作用は発生しません。
医療用医薬品のタウリンの副作用には、主に悪心・下痢・腹部不快感などの消化器症状や発疹が報告されています。その中でも、ミトコンドリア脳筋症・乳酸アシドーシス・脳卒中様発作(MELAS)症候群における脳卒中様発作の抑制目的で、52週間という長期間タウリンを投与した臨床試験(用量:以下表を参照)では、総症例数は少ないですが口内炎や胃腸障害の報告がありました。
参照:ミトコンドリア脳筋症・乳酸アシドーシス・脳卒中様発作(MELAS)症候群における脳卒中様発作の抑制目的での用法用量 下記表の1回量を1日3回食後に服用
|
体重 |
1回量 |
|
15kg未満 |
1g |
|
15kg以上25kg未満 |
2g |
|
25kg以上40kg未満 |
3g |
|
40kg以上 |
4g |
タウリンは腎臓から尿中に排泄されるため、腎排泄機能が未熟な子どもたちや生理機能が低下した高齢者では、排泄が遅れ血中濃度が上昇する可能性が考えられます。タウリンを継続して摂取する場合は、注意が必要です。
まとめ
ここまで紹介してきたように、タウリンにはさまざまな作用や効果がわかってきています。しかし現在の日本では、タウリンは「専ら医薬品として使用される 成分本質 (原材料) 」に区分されているため、食品に分類されるものにタウリンを添加できません。タウリンの効果が気になる方は、食材からの効率よく摂取する方法を参考にして、日常的にタウリンの摂取を心がけて生活してみましょう。