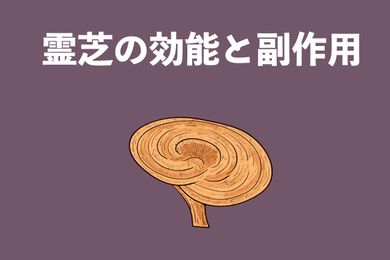ウコン、クルクミンの基本情報を解説
ウコンとは?
ウコン(英名Turmeric:学名Curcuma longa Linn)は、主にインドや東南アジアに分布するショウガ科ウコン属の植物で、日本では秋ウコンとも呼ばれる、生姜の仲間です(1)。実は、インドカレーの定番でもある「ターメリックライス」には、黄金色の香辛料であるターメリックとして秋ウコンが用いられているため、口にしたことがある方も多いかと思います。
ウコンは、2500年以上の歴史があるとされる古代インドの医学「アーユルヴェーダ」において重要な生薬であり、着色料や漢方薬、香辛料として長い間使用されてきたことが知られています(2)。ウコンをアーユルヴェーダで利用していた当時のインドでは、衛生環境があまり良くなかったこともあり、口腔衛生を維持するほか、胃や肝臓の病の治療薬などとしてウコンが非常に重宝されたと考えられています。
そして近年は、ウコンに含まれるクルクミン(Curcumin)という色素と、クルクミンから作られるウコン特有の成分グループであるクルクミノイド(Curcuminoid)が持つ幅広い効果に注目が集まり、ウコンは強力な健康食材としても頻繁に使用されています。
クルクミンとは?
「クルクミン」はウコンの根に含まれる、ポリフェノール化合物の一種でもある黄金色の色素です(1)。ターメリックライスに使用される香辛料ターメリックの特徴でもある黄金色は、このクルクミンにより作られています。
クルクミンは、クルクミン自身だけではなく、クルクミンから作られるデメトキシクルクミン(DMC)、ビスデメトキシクルクミン(BDMC)を含む「クルクミノイド」という化合物グループを形成し、抗炎症、神経保護、抗腫瘍など幅広い効能を示すことが報告されています(3)。
ウコンの幅広い効能は、クルクミンを含むこのクルクミノイドの生理活性によって生まれると考えられています。
それでは、ウコンが持つ効能と、それを示唆する研究報告を詳しく見ていきましょう。
ウコンが持つ効能とは?研究報告を解説!
近年、臨床研究におけるウコンの効果は医学界で大きな関心を集めています。ウコンやクルクミン、クルクミノイドに関する研究は、2020年以降に限っても1万報以上の学術論文が報告されており、多くの効能が示唆されています。
ウコンの効能は非常に幅広いため、この記事では、その中でも特に良く報告される代表的なものをご紹介します。
1. 抗炎症作用による関節や皮膚、胃腸などの保護
ウコンの効能の中でも最もよく知られているのは、抗炎症作用によるさまざまな炎症性疾患への働きです。
例えば、加齢に伴い軟骨がすり減ることで発症する変形性関節症の患者107人を対象とした研究では、ウコンエキス2g摂取グループと消炎鎮痛剤であるイブプロフェン800mg摂取グループへランダムに割り当て、6週間の摂取による膝機能への影響を評価した結果、ウコンエキス摂取グループとイブプロフェン摂取グループの両方で歩行時の痛みや階段昇降にかかる時間が改善したと報告されています(4)。
また、皮膚や腸、目の炎症に対しても、それぞれを抱える患者にウコンエキス、クルクミノイドを投与した研究で症状を改善した結果が報告されており、ウコンとクルクミンを含むクルクミノイドには幅広い炎症を抑える効果があることが示唆されています(5)。
2. 抗酸化作用による心血管の保護、免疫力のサポート
私たちにとって「酸化」は免疫においてとても重要な働きをしますが、酸化が過剰に働くことで生じる「酸化ストレス」は、かえって血管へのダメージや免疫異常など多くの疾患リスクになることが知られています。この酸化ストレスを抑えて適切なバランスを保つ「抗酸化作用」は、心血管の保護や免疫力の維持に重要であると考えられています。
多くのヒトを対象とした研究を俯瞰的に解析する「メタ分析」を行った研究では、クルクミンの摂取により、酸化ストレスの主な要因である活性酸素を除去する酵素()の働きが有意に増加したと確認されており、クルクミンの抗酸化作用が強く示唆されています(7)。
またこの研究以外にも、クルクミンを含むクルクミノイドの抗酸化作用はガンのリスクを抑える効果にも関わることが示唆されており、ウコンとクルクミン、クルクミノイドの効能を支持する報告が数多くされています(8)。
3. 精神安定、気分安定化のサポート
ウコンが含んでいるクルクミンは気分の安定にも寄与することが研究によって示唆されています。
うつ病患者へのクルクミンの投与による効能を調べた多くの研究で、クルクミンがうつ症状を緩和することを示唆する結果が報告されてきました(9)。
これらの膨大なデータを統計的に解析する「メタ分析」において、クルクミンはうつ症状の改善に有意に有効であることが示され、その信頼性がより強調されています。また、うつ病だけでなくアルツハイマー病などの認知機能に関わる効能も別の研究で示唆されており、ウコンとクルクミン、クルクミノイドの幅広い働きが支持されています(8)。
ウコンとクルクミンの摂取方法について解説
ウコンには幅広い用途があり、料理には着色剤や香辛料として使用され、料理の色や風味を引き立てるために使用されます。
また、直接スープや料理として味わう食材にもなります。ウコン製品も多様で、ウコンパウダーやウコン茶、ウコン由来のクルクミン含有健康食品なども多くあります。ウコンを効果的なケアとして利用したい場合は、特許を取得し規格化されたクルクミン製品の摂取がおすすめです。
ウコンの効能を支えるクルクミンの安全かつ効果的な摂取量については、世界保健機関WHOの推奨量に基づくと、成人の摂取基準量は体重1kgにつき3mg以内とされています(8)。そのため、健康な成人で体重が60 kgの方であれば、1日のクルクミン摂取量は180 mgを超えないようにするといいでしょう。
一方で、市販のウコン製品の多くは、クルクミン含有量の多さを謳っています。その主な理由は、クルクミンが水に溶けにくく摂取後に十分に吸収されないと同時に、吸収後も素早く代謝されるため、血中へのクルクミン摂取の反映の維持が難しいことです。
これは専門的には「生物学的利用能(バイオアベイラビリティ)が低い」と言われる問題で、ウコンやクルクミンを健康食品として摂取する際の課題となることが知られています(10)。
この課題に対しても研究が進められており、クルクミンのバイオアベイラビリティを高めるためのカプセル化技術やナノ粒子を活用した技術が報告されています(11)。そのため、特許を取得し規格化されたマイクロエンカプセレーション技術などを使用したウコン由来クルクミン製品を選ぶと良いでしょう。
この技術により、推奨用量のクルクミンを安定して摂取できることが期待されます。
ウコン由来クルクミンの副作用と注意点
ヒトを対象としてクルクミンの安全性を調べた研究では、1日12gまでのクルクミン摂取であれば安全であったという報告があります(12)。ヒトを対象として効能を調べてきた多くの研究で副作用は報告されませんでしたが、一部の研究では高用量のウコンを摂取した人の中で腹痛や下痢などの副作用が報告されています(5)。
そのため、これまで使用したことのない人には、まず少量で試して身体の変化を確認するとより安全であると考えられます。また、薬を服用している場合や医療治療を必要とする場合は、まず医師に相談することをおすすめします。妊娠中や授乳中の女性も、事前に医師に相談してください。