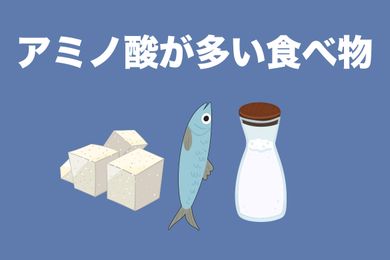カルシウムは、人体にもっとも多く含まれるミネラルです。しかし、報告によると、国民の約90%以上がカルシウム不足であると言われています。
厚生労働省が推奨しているカルシウムの摂取量は、は成人1日あたり650〜750mg前後です(1)。しかし、私たちは1日あたり平均して495mgのカルシウムしか摂取できていません(2)。では、炭酸カルシウム、クエン酸カルシウム、またはアクアミン、どれがいいでしょうか? どのようにしてカルシウムを補給すればよいのでしょうか?この記事では、まずはカルシウムについての理解を深め、カルシウムの賢い補給方法を紹介します。カルシウムの重要性
「カルシウム」は、人体のミネラルの中で最も必要量が高いが、慢性的に不足している栄養素です。体重の約1〜2%を占め、そのうち約99%のカルシウムは骨と歯に存在し、1%は血液、細胞内液、筋肉、組織に分布しています(1)。現代の食生活では、十分な量のカルシウムを摂取するのはかなり困難です。そのため、カルシウムを積極的に摂取することは、体の健康を維持するために最も重要なことの一つであるといえます。
カルシウムの効果と副作用
カルシウムは、骨や歯、血液、細胞内液、筋肉、そして組織に存在し、以下の5つの機能を持っています:
-
骨や歯の正常な発育と健康を維持するのに役立ちます
-
血液の正常な凝固機能をサポートします
-
筋肉と心臓の正常な収縮および神経の感受性を助けます
-
血液の凝固を助けるため、凝血酵素を活性化させます
-
細胞の透過性を調節します
日本では現在、年齢に関係なくカルシウムの栄養上限摂取量(UL)は1日あたり2.5gに設定されています(1)。この量の摂取は比較的安全であり、現段階では高カルシウムやその他の副作用が発生する可能性は低い量だと考えられています。
1日のカルシウム摂取推奨量
厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2020年版)」によると、1日の推奨カルシウム摂取量は年齢によって以下のように区分されています(1)。
|
年齢(歳) |
摂取推奨量(mg/日) |
|
|
男性 |
女性 |
|
|
1~2 |
428 |
415 |
|
6~7 |
587 |
532 |
|
7~8 |
585 |
538 |
|
8~9 |
645 |
750 |
|
10~11 |
708 |
732 |
|
12~14 |
991 |
812 |
|
15~17 |
804 |
673 |
|
18~29 |
789 |
661 |
|
30~49 |
738 |
660 |
|
50~64 |
737 |
667 |
|
65~74 |
769 |
652 |
|
75以上 |
720 |
620 |
注1:推奨摂取量は、体内蓄積量、尿中排泄量、経皮的損失量を算出し、これらの合計を見かけの吸収率で除して推定平均必要量を定めています。
注2:1歳以上は1日に2500mgのカルシウムを超える過剰摂取は避けてください。重篤な副作用を引き起こす可能性があります。
なぜカルシウム不足に?カルシウム不足の原因
年齢に伴う変化
骨密度のピークは20歳です(3)。30歳以降の中年期には、毎年一定の速度でカルシウムが失われ、女性の場合は閉経を迎える50歳頃になると、骨密度の減少が加速します。 特に更年期後の女性は、骨を作る骨芽細胞を活発にするエストロゲン(卵胞ホルモン)が激減するため、カルシウム不足に注意する必要が必要です(4)。
食習慣
インスタントラーメン、ハム、ソーセージなどの加工食品には過剰なリンが含まれています。これがカルシウムイオンと不溶性のリン酸カルシウムを形成し、消化管でのカルシウムの吸収に影響を与えてしまうので要注意です。 また、過剰なナトリウムはカルシウムの流失を促進し、これらの要因が体内のカルシウム不足を引き起こしやすくなります。
生活スタイル
屋内での長時間労働が多い人やインドアで休日は家にこもりがちな人は、太陽光をほとんど浴びず、体内でビタミンDが不足する可能性が高いでしょう。それによってカルシウムの吸収が不足することがあります。
生活習慣
カフェインの摂取過多、喫煙、飲酒などの生活習慣は、カルシウムの喪失を引き起こす可能性があります。
カルシウムの種類は?
|
カルシウム比較 |
||
|
種類 |
メリット |
デメリット |
|
炭酸カルシウム |
低コストでカルシウム含有量が多い |
吸収率が低く、副作用が大きい、空腹時に摂取すると消化器系の不良反応が生じやすく、食後または食事と同時に服用が必要 |
|
クエン酸カルシウム |
消化器への刺激が少なく、食事の時間制限がなく、ほとんどの人に適しています |
カルシウム含有量が低いです |
|
アクアミン |
多様なミネラル栄養素を含んでいます |
海洋由来のため、なま臭さが強いです |
|
コーラルカルシウム |
多様なミネラル栄養素を含んでいます |
ヴィーガンの方は摂取できません |
|
乳酸カルシウム |
口当たりが良い |
カルシウム含有量が低く、乳糖不耐症患者には適していません。 |
|
アミノ酸キレートカルシウム |
吸収率が最も高い |
カルシウム含有量が低く、価格が高い、pH値が高く、強アルカリ性であり、直接摂取すると消化器の火傷を引き起こしやすいです |
カルシウムの摂取方法
食品からカルシウムを摂取する場合、手軽で最適なのは牛乳や乳粉などの乳製品です。乳糖不耐症の人は、豆腐、干し魚、エビ、黒ごまなどの高カルシウム食品から摂取することができます。1日の食品からのカルシウム摂取が不足している場合は、カルシウムサプリメントで不足分を補充するとよいでしょう。
カルシウムを含む食材は?特に高カルシウムな食材
食品からカルシウムの摂取をする場合は吸収率を考慮するといいでしょう。一般的には乳製品の吸収率がいいとされています。他にもビタミンDは吸収を助け、マグネシウムは共同作業をしてくれることから一緒に摂取するとより良い効果を得られます。また、同時に摂取する他にも太陽光を浴びることも重要です。
|
食品のカルシウム含有量 |
||
|
食品の種類 |
食品(100g) |
カルシウム含有量(mg) |
|
乳製品 |
ナチュラルチーズ(エダム) |
660 |
|
全脂生乳 |
104 |
|
|
ヨーグルト |
120 |
|
|
豆類 |
豆腐(木綿) |
93 |
|
豆乳 |
15 |
|
|
魚介類 |
干し魚(かたくちいわし) |
2200 |
|
エビの干物 |
7100 |
|
|
ナッツ類 |
ごま(乾燥) |
1200 |
|
ごまペースト |
590 |
|
|
いちじく(生) |
26 |
|
|
アーモンド(乾燥) |
250 |
|
|
野菜類 |
水菜(生) |
210 |
|
キャベツ(生) |
42 |
|
|
焼きのり |
280 |
|
カルシウムサプリメントはどう選ぶ?
カルシウムサプリメントを選ぶ際には、カルシウムの含有量に注意するだけでなく、以下のようなビタミンやミネラルも配合されているかどうかを確認することが大切です。:
-
吸収 - ビタミンC:吸収効率を高めます。
-
運搬 - ビタミンD:体内で循環する際の輸送役を果たします。
-
導入 - ビタミンK:方向を指し示す役割を果たします。
-
安定化 - マグネシウム:カルシウムとマグネシウムイオンは一緒に体調を整えてくれます。
関連記事:マグネシウムの効果は?薬剤師が役割、マグネシウムを含む食品、摂取量、副作用について説明
カルシウムサプリメントはいつ摂取すべき?
摂取のタイミングは、カルシウム源や各々の体調によって異なります。例えば、一般的な炭酸カルシウムは食事中、または食後に摂取することが推奨されていますが、クエン酸カルシウムは時間に制約がなく、いつでも摂取可能です。アミノ酸キレートカルシウム製品なら就寝前に摂取することが推奨されています。もし心配のある人は、医師に相談してより適切な摂取量とタイミングを確認しましょう。
ただし、どの種類のカルシウムサプリメントを摂取するにせよ、一度に過剰摂取しないように注意する必要があります。なぜなら、一度に摂取するカルシウム量が多すぎると、体内のカルシウム吸収率が自動的に低下してしまうからです。そのため、高濃度のカルシウムを一度に補充するよりも、少量を何度かに分けて摂取する方が効果的です。