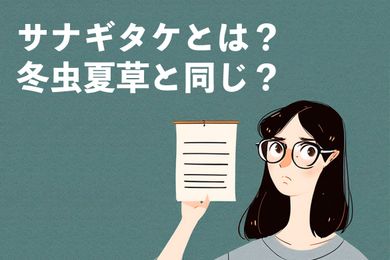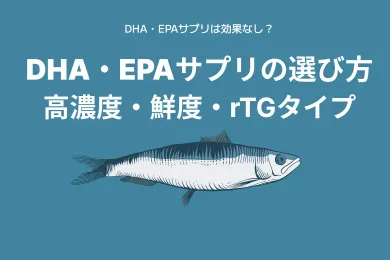ギムネマとは?
ギムネマ(学名:Gymnema sylvestre)は、キョウチクトウ科(旧ガガイモ科)に属する乳白色の多年生つる植物で、インドの中南部熱帯林で発見され、現在では太平洋の国々や南アフリカなど、熱帯・亜熱帯地域に幅広く分布している植物です(1)。
日本では、ホウライアオカズラという名前でも呼ばれるもので、沖縄県に分布しているとされています(2)。ギムネマは長いつると小さな黄色い花を持つ植物で、その葉がハーブに用いられます。ギムネマの葉には独特な香りがあり、葉の味はわずかな苦みを含む渋い味です。
ギムネマには多くの健康上の利点があり、古くから民間療法、インド・スリランカ発祥のアーユルヴェーダ、ドイツ発祥のホメオパシーなどで使用されており、数千年もの歴史があるとされています(3)。
特に、強力な抗糖尿病作用が特徴とされるギムネマは、アーユルヴェーダにおいて貴重なハーブとして用いられてきたとされています。「ギムネマ」という言葉の語源とされるヒンドゥーの言葉“Gurmar”は、「糖を破壊するもの」という意味を持つ言葉です。その名の通り、ギムネマは甘味物質の感知を低下させる特性を持っており、甘いものへの欲求を抑制し、糖分摂取をコントロールするために使用されてきました 。
これらが注目を集め、近年ではギムネマが持つ有効成分に関する研究が進むとともに、日本でもギムネマの成分を含んだ健康食品が増えてきています。
ギムネマの栄養素
ギムネマの葉には、トリテルペノイドサポニンをはじめとした配糖体、フラボン、飽和脂肪酸や不飽和脂肪酸、アルカロイド、植物ステロールなど豊富な成分が含まれています(3)。そして、中でも代謝を安定させる効能があるとして最も重要な活性成分とされているものは、トリテルペノイドサポニンの一つであるギムネマ酸(Gymnemic acid)と、ペプチドの一つであるグルマリン(Gurmarin)です。
トリテルペノイドサポニンとは?
トリテルペノイドサポニンとは、サポニン化合物に含まれるトリテルペノイド類の物質で、配糖体の中の一つのグループです。「サポニン」という単語は、サポゲニンという疎水性構造を持つ配糖体を指す言葉で、ラテン語の“sapo”が英語の“soap”の語源となっているように、サポニンもかき混ぜると泡立つ特徴から名付けられたとされています(4)。
サポニンは主に植物界に広く存在しているほか、ヒトデやナマコが含んでいることもあり、防虫作用や殺菌作用などを発揮している天然化合物です。植物はさまざまなサポニン化合物を、疎水性のトリテルペンという骨格を持つ「トリテルペノイドサポニン」として保持することで、生存するための防御手段として役立てていると考えられています(5)。これまでの研究により多くの植物由来のトリテルペノイドサポニンが発見されており、植物が生存のための防御成分として蓄えたトリテルペノイドサポニンには、ヒトにとっても循環や新陳代謝を助ける作用があることが報告されています。
ギムネマ酸とは?
ギムネマ酸は、ギムネマから同定されたトリテルペノイドサポニンの一種です。ギムネマ酸にはA1〜A4の4種類があるとされており、ギムネマにはギムネマ酸A1が最も多く含まれることが知られていますが、一般的にはA1〜A4の4種類を総称して「ギムネマ酸」と呼びます(6)。
ギムネマ酸は、塩味、酸味、苦味などの他の味覚に影響を与えることなく、甘味の感受性だけを低下させることができる特殊な効能があるほか、腸管でのグルコースの吸収を抑制する効能や、血漿中のグルコース濃度を下げる効能が報告されており、糖分摂取の欲求や過剰な摂取を減らす効果が示唆されています(7)。インスリン抵抗性を示す2型糖尿病のモデルラットにギムネマ酸を投与して効能と作用機序を調べた研究では、空腹時血糖値が有意に低下したことが報告されています(8)。
グルマリンとは?
グルマリンは、35個のアミノ酸で構成されるペプチドで、ギムネマ酸と同様にギムネマから同定された生理活性物質です。グルマリンも甘味に対する感受性を抑える効能があり甘いものへの欲求を抑制します。ラットを用いた研究では、グルマリンの投与によりラットがショ糖を摂取する量が有意に減少し、複数回の投与を継続してもリバウンドが起こることはなく効果が継続したと報告されています(9)。
ギムネマの効能
人を対象としたギムネマの効能を調べた臨床研究では、ギムネマ300 mgを含むカプセル、またはプラセボのどちらかを無作為かつ二重盲検法で分けたグループに1日2回計600 mg分を摂取してもらい、体重や血中成分などの指標を比較しました。その結果、ギムネマを摂取したグループでは有意に体重が減少したことに加え、脂質過剰の判別の指標の一つである超低密度リポタンパク質(VLDL)量も有意に減少したことが報告されています(10)。
上記の研究報告をまとめると、ギムネマは以下のような効能を持つと考えられています。
ギムネマの摂取が推奨されるグループ
上記の研究報告で示唆されている効能を踏まえると、ギムネマは以下に当てはまる方々にとって、特に摂取が推奨される健康食品であると考えられます。
ギムネマの適切な摂取量
現在までに行われた、人を対象としたギムネマの効能や安全性を調べる研究では、被験者に対して1日400mg(11)、600mg(10)のギムネマを投与した場合のいずれにおいても、有害事象は報告されていません。
したがって、このような用量を超えない範囲での摂取は、安全上の問題はないと考えられています。ただし、糖尿病治療などですでに薬剤を投与されている場合など、別の薬剤の作用に影響を与える可能性がある場合には必ず医師や栄養士と相談することが必要です。治療を受けていない場合でも、症状を自覚しているかどうかに関わらず、事前に確認をしてから摂取することはより安全であるためおすすめします。
ギムネマの副作用
上記の用量でギムネマを摂取した臨床研究では、副作用は報告されておらず、過去の研究の副作用の発生数を解析した研究においても、明確な副作用は確認されていません(12)。
ただし、ギムネマを過剰摂取してしまった場合、低血糖症状を引き起こす可能性があります。また、研究は主に成人に対して行われるため、妊娠中や授乳中の女性、および2歳未満の幼児など、小さいお子さんに影響を及ぼす可能性のある状況でのギムネマの摂取は、控えることが推奨されます。
上記の通り、ギムネマは糖尿病の経口薬と併用しないことが推奨されます。これにより過度な血糖降下を引き起こし、悪影響を引き起こす可能性を減らすことができます(13)。
ギムネマの摂取のタイミング
これまでの研究報告から、ギムネマは食事の前に摂取すると、甘味に対する感受性を低下させ、糖分摂取量を減らすことができ、最も効果的だと考えられています(10)(11)。食前にギムネマを摂取することにより、血糖代謝を安定させ、食後の高血糖の予防が期待できます。
ギムネマと相性の良い健康食品
人を対象とした別の研究で、ギムネマの抽出物をニガウリペプチド、クロム、およびシナモンを含むサプリメントと併用して摂取したところ、安全に体重や血中脂質の低下を達成できたという報告があります(14)。これらを一緒に摂取することにより、炭水化物の代謝が促進され、食前後の血糖の急激な変動を防ぐことが期待できます。