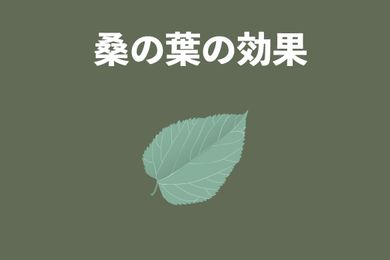ビタミンDは身体の健康維持のためには欠かせない栄養素ですが、摂りすぎには注意が必要です。ビタミンDを多く摂ろうとして、過剰に摂取してしまう方もいるのではないでしょうか。ビタミンDの過剰摂取は、かえって健康リスクを引き起こす可能性があるため、適量を知り、栄養バランスを整えることが大切です。
この記事では、ビタミンDの推奨摂取量や過剰摂取のリスクについてご紹介します。栄養の正しい知識を身につけることで、健康的な生活を送れるようになるでしょう。
ビタミンDの働き
ビタミンDは、具体的にどのような働きがあるのでしょうか。ここでは、その働きについて詳しく解説します。
カルシウム吸収の促進
まず、ビタミンDにはカルシウムの吸収を促進させる役割があるとされています。カルシウムは人体に多く含まれているミネラルの1種で、骨や歯を作るために必要な栄養素です。カルシウムを効率的に吸収するためには、ビタミンDの存在が重要です。ビタミンDはカルシウムの吸収をサポートして、その取り込みを促進させます。一方で、ビタミンDが不足するとカルシウムを適切に摂取しても、うまく身体に取り入れられなくなります(1)。このように、ビタミンDはカルシウムの吸収において非常に重要な役割を担っているのです。
骨代謝の促進
ビタミンDはカルシウムの吸収をサポートすることから、骨代謝を促進させて骨の健康維持にも働きます。骨は常に「壊す(骨吸収)・作る(骨形成)」を繰り返しており、このプロセスが「骨のリモデリング」です。
骨のリモデリングは健康な骨を維持するために必要で、ビタミンDは新しい骨の形成をサポートしています。ビタミンDを取り入れることで骨密度の向上や骨粗鬆症の予防が期待できます。ビタミンDが不足すると、このサイクルが乱れて骨吸収が優位となり、骨密度の低下や骨粗鬆症の原因となるのです(2)。
免疫系の強化
ビタミンDは、免疫系の強化にも重要な役割を果たしています。免疫とは、細菌やウイルスなどの外部の異物から身体を守るためのシステムです。ビタミンDを適切に摂取することで、この免疫機能が高まり、感染症をはじめとしたさまざまなリスクの軽減につながります。実際に、ビタミンDの摂取は急性的な感染症に対する抵抗力を高めるという報告もあります(3)。このように、ビタミンDは骨の健康だけでなく免疫系にも関係している重要な栄養素であることがわかるでしょう。
ビタミンDの1日の推奨摂取量と上限
さまざまな効果が期待されているビタミンDを摂取する際は、適量を守ることが重要です。ここでは、ビタミンDの1日の推奨摂取量と上限摂取量について解説します。
ビタミンDの1日の推奨摂取量
ビタミンDの1日の推奨摂取量は、年齢や性別によって異なります。成人の場合、1日あたりの推奨摂取量は5.5〜8.5μg(マイクログラム)とされています。具体的な推奨量について、以下の表にまとめました(4)。
|
年齢等 |
推奨量 |
|
18〜64歳(男・女) |
5.5〜8.5μg/日 |
|
65歳以上(男・女) |
5.5〜8.5μg/日 |
|
妊婦 |
7.0〜8.5μg/日 |
|
授乳婦 |
7.0〜8.5μg/日 |
このように、成人以降でもビタミンDの推奨摂取量はおおむね変わらないとされています。また、妊婦や授乳婦の場合、必要摂取量の範囲が多めに設定されています。
関連記事:ビタミンDを多く含む食品15選【管理栄養士監修】摂取量や注意点も紹介
ビタミンDの摂取量の上限
ビタミンDには摂取量の上限が設けられており、これを超えると健康被害のリスクが高まる恐れがあります。成人の場合、1日あたりの上限量は100μgまでとされています。具体的な摂取上限量について、以下の表にまとめました(4)。
|
年齢等 |
推奨量 |
|
18〜64歳(男・女) |
50〜100μg/日 |
|
65歳以上(男・女) |
50〜100μg/日 |
|
妊婦 |
100μg/日 |
|
授乳婦 |
100μg/日 |
このように、成人以降においては、どの条件でもおおむね100μgまでに設定されています。ただし、個人の健康状態や生活環境によっては、上限量が変動する点に注意しましょう。適切な摂取量と上限量を心がけることで、ビタミンDのメリットを安全に受けられます。
ビタミンDの摂りすぎで起こる初期症状
ビタミンDの摂りすぎによる初期症状としては、以下のとおりです(5)。
-
食欲不振
-
吐き気
-
嘔吐
-
便秘
-
脱力感
-
体重減少
これらの症状は、体内のカルシウム濃度の上昇や腸管の機能低下などによって引き起こされます。また、ビタミンDを過剰摂取する原因のほとんどは、サプリメントの使用が考えられます。サプリメントは使用を間違えると栄養素の摂取量が過多になるので、ビタミンDに限らず注意しましょう。
ビタミンDの摂りすぎによる初期症状に気づいたら、すぐにサプリメントの摂取を中止し、医療機関の受診をおすすめします。
ビタミンD摂りすぎのリスクは?
ビタミンDを摂りすぎると、深刻な健康リスクが生じる可能性があります。代表的な問題として、「高カルシウム血症」があげられます。高カルシウム血症とは、血中のカルシウム濃度が異常に高くなる状態のことです。
先ほど解説したように、ビタミンDにはカルシウムの吸収を促進する働きがあるとされています。そのため、ビタミンDを摂りすぎるとその働きが過剰となり、カルシウムのバランスが崩れてしまいます。高カルシウム血症の症状は以下のとおりです。
-
吐き気
-
嘔吐
-
食欲不振
-
便秘
-
脱力感
-
体重減少
さらに重症化すると、意識障害をはじめとした深刻な症状が現れることもあります。また高カルシウム血症が続くと、血管や組織に石灰化が起こり、心臓や腎臓にダメージを与える恐れがあります(6)。ビタミンDは健康に欠かせない栄養素ですが、摂りすぎには十分注意が必要です。
ビタミンDを適度に摂る方法
ビタミンDの摂りすぎを防ぐには、どのような方法があるのでしょうか。ここではビタミンDを適度に摂る方法について解説します。
バランスよく栄養を摂取する
ビタミンDを適度に摂取するには、バランスのよい食事が重要です。ビタミンDを多く含む食べ物は、以下のとおりです。
-
魚類(サケやマグロ)
-
きのこ類
-
卵黄
-
レバー
-
チーズ
これらの食べ物を適度に取り入れつつ、他の栄養素とのバランスも考慮しましょう。
日光浴をする
食事以外でビタミンDを摂り入れる方法として、日光浴もおすすめです。皮膚に日光(紫外線)が当たることで、体内でビタミンDの生成が期待できます。食事でうまくビタミンDを摂取できない場合は、日光浴も検討してみてください。日光浴の時間の目安は調査機関によって異なりますが、約15〜30分が推奨されています(7)。
ただし、真夏の日中や日差しの強い時間帯は肌にストレスがかかりやすいので、長時間の日光浴は避けましょう。日差しの強い時間帯は避け、朝や夕方などの紫外線が比較的弱い時間帯で日光浴をするのがよいでしょう。個人の状況や環境に応じて、適切に日光浴をすることが大切です。
サプリメントの使用には注意する
サプリメントは手軽にビタミンDを補給できる一方で、過剰摂取のリスクがあるので注意が必要です。サプリメントを使用する際は、摂取量と頻度に気をつけましょう。商品に記載されている推奨量を守り、過剰摂取にならないように注意する必要があります。とくに複数のサプリメントを併用している場合、含有量をよく確認して合計摂取量が上限を超えないようにしてください。
可能であれば、なるべく食事からビタミンDを摂取することも意識しましょう。食事によって十分なビタミンDを摂取していれば、サプリメントが不要な場合もあります。このように、ビタミンDサプリメントの使用には注意が必要です。適切な使用方法を守り、バランスの取れた栄養摂取を心がけることが大切です。
定期的な血液検査を受ける
ビタミンDの適切な摂取量を知るためには、定期的な血液検査も重要です。血液検査をすることで、自分のビタミンDの摂取状況を把握するきっかけとなります。
血液検査の頻度は、その方の状況によって異なります。ビタミンD不足のリスクが高い人や、サプリメントを使用している人は、少なくとも毎年1回以上の検査がよいでしょう。ビタミンDの血中濃度を把握できれば、摂取量のコントロールが行いやすくなります。定期的な血液検査を受けてビタミンDの過不足を防ぎ、健康的な生活を送りましょう。
ビタミンDの摂りすぎには注意しよう
ビタミンDは⾻の健康や免疫機能を保つための重要な栄養素ですが、過剰に摂取するとリスクとなります。とくに、サプリメントによる過剰摂取には十分に注意する必要があります。適切な摂取量を守ることで、ビタミンDのメリットだけを得ることが可能です。健康的な生活を送るために、今回の記事を参考にしてビタミンDの適切な摂取⽅法を⾒直してみましょう。