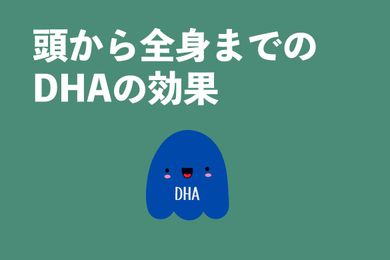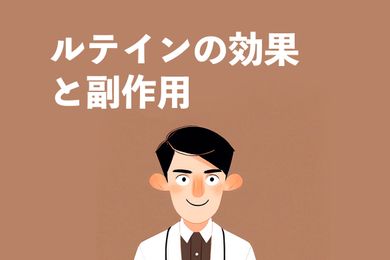リコピンと聞くと、真っ赤に熟れたトマトが頭に浮かんできませんか?トマトジュースなどの加工品で目にすることが多いリコピンですが、そのリコピンに期待される効果については、あまり詳しく知らない方も多いのではないでしょうか。ここでは、リコピンの抗酸化作用がもたらす健康効果や、効果的な摂取方法について解説していきます。
リコピンとは?
リコピン(Lycopene)は、美肌や生活習慣病予防において注目されている食品由来のカロテノイドの一つであり、植物や果物を赤く彩る自然の色素です。特にトマトに豊富に含まれています。リコピンは強力な抗酸化作用を持ち、その作用はビタミンE(α-トコフェロール)の約100倍、β-カロテンの2倍にもなります。リコピンの持つ抗酸化作用が、肌の若々しさや体の健康維持をサポートをしていることが報告されてます。(1)
リコピンはトマトの他にも、スイカ、柿、パパイヤ、グアバなどの赤い果物にも含まれていまが、同じく赤い食材でもいちごやりんごには、リコピンは含まれていません。リコピンを効果的に摂取するには、多く含まれている食材や摂取方法についても知っておく必要があります。リコピンを日常的に上手に摂取することで、健康維持や美容に役立てていきましょう。
リコピンに期待される健康効果とは?
リコピンは健康に良い効果が期待されています。
本来活性酸素は、細胞伝達や免疫調節において重要な役割を果たしています。しかし、紫外線やストレス、汚染物質などの影響により活性酸素増えすぎると、細胞を傷つけ老化につながってしまいます。
リコピンの持つ強い抗酸化作用によって、活性酸素の働きが抑えられ、さまざまな健康効果が期待できることが報告されています。ここでは、リコピンに期待されている健康効果について解説していきます。
肌の健康の維持
紫外線のダメージによって肌の細胞は傷ついてしまいます。リコピンの強力な抗酸化作用によって、肌の細胞を保護し、肌のハリの保持やシワ・そばかすの予防に役立ちます。また、紫外線のダメージによる肌の赤みを軽減するという報告もあり、健康的な肌のトーンを維持するためのサポートとしても期待されています(4)。
生活習慣病の予防や改善
主な生活習慣病には、高血圧や脂質異常症・糖尿病などがあり、これらの予防や改善にも、リコピンが関わっている可能性があります。活性酸素が、生活習慣病の原因となっているからです。リコピンの持つ抗酸化作用によって、LDLコレステロールが酸化するのが抑えられ、血液の流れを改善したり、活性酸素が体内のさまざまな細胞を傷つけ機能しなくなるのを防いだりする効果が期待されています。
血流の改善が動脈硬化を予防し、結果的に心疾患のリスク低減にもつながります(1)(5)。
代謝の促進
糖や脂質、酸素を運ぶのは血液であり、代謝を行っている臓器には血管が発達していることなどから、代謝の促進と血流の改善には深い関りがあることがわかります。活性酸素の酸化ストレスによって代謝が落ちて疲労感を感じることがあるかもしれませんが、リコピンの抗酸化作用で代謝の促進に導いてくれる可能性があります。
男性不妊症のサポート
精子は、酸化ストレスによる影響を受けやすいと言われています。リコピンの投与によって精子に関するさまざまなパラメーターが改善したという報告もあり、男性不妊症をサポートする効果も期待されています。(2)(3)。
リコピンの摂取がおすすめな方は
リコピンは体内で合成されないため、食事から摂取する必要があります。以下の方には特にリコピンの摂取がおすすめです。
リコピンが含まれる食品は?
トマト以外の食品にもリコピンが含まれており、例えば赤身のグアバ、スイカ、赤身のグレープフルーツなどがあげられます。(6)
|
食品 |
リコピン含有量(μg/100g) |
|
グアバ |
5,204 |
|
スイカ |
4,532 |
|
トマト |
2,573 |
|
ピンクグレープフルーツ |
1,419 |
|
パパイア |
1,828 |
リコピンの効率的な摂取方法は?
-
油と一緒に摂取する:リコピンは脂溶性の栄養素なので、油と一緒に摂取することで吸収率が高まります。
-
加熱調理する:トマトなどリコピンを含む食品を加熱調理すると、細胞壁が破壊され、リコピンの吸収率が上がります。
-
細かく刻む:食材を細かく刻んだり、ピューレ状にすることで、細胞壁が破壊され、リコピンがより多く放出されます。
-
相性の良い食材と組み合わせる:たまねぎ、にんにくなどと一緒に調理すると、これらの野菜に含まれる酵素の働きでリコピンが体に吸収されやすい構造に変化し、リコピンの吸収率が向上します。
リコピンの摂取目安量と副作用
リコピンの摂取目安量は、厚生労働省の日本人の食事摂取基準(2020年版)によって特に定められていません。しかし一般的に、15~20mgの摂取が目安とされています。大玉のトマト2個分ほどとも言われていますが、毎日そればかり摂取するのは、飽きてくるし、栄養バランスに偏りが生じる可能性もあります。さまざまな食材と組み合わせようとしても、なかなか上手に摂取できない場合には、サプリメントでリコピンを摂取するのもおすすめです。
またリコピンの過剰摂取による副作用はあるのでしょうか?リコピンは天然色素であり、過剰摂取により皮膚の色が黄色やオレンジ色に変わる可能性がありますが、摂取をやめると徐々に正常な状態に戻ります。一度に大量に摂取しようとせずに、毎日適量を摂取するようにこころがけましょう。
薬を服用している場合や薬をのんでいなくても病気の治療中の場合には、リコピンのサプリメントを摂取する前に、医師に相談するようにしましょう。
リコピンの摂取タイミング
天然の食品中のリコピンは、調理方法によって吸収率に大きな差が生じます。リコピンは脂溶性であるため、油脂を含む場合に吸収がより良くなります。
一方でサプリメントとしてリコピンを摂取する場合、リコピンがより吸収されやすいように油脂を配合した製品がおすすめです。またリコピンは朝に摂取する方がリコピンの血中濃度が上昇するという報告もあります。摂取するタイミングやその理由についてはまだ研究段階ですが、絶食時間の長さが関係している可能性もあり、今後の研究報告も注目されています(7)。