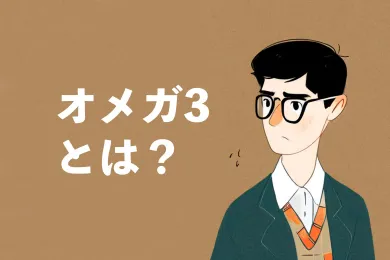脂質とは
脂質は炭水化物やタンパク質とならんで人体のエネルギー産生栄養素の一つであり、脂質を構成する重要な要素に脂肪酸があります。脂肪酸はカルボキシル基(COOH)を持つ炭化水素類(カルボキシル基+炭化水素基)のことで、その特性と分子の構造的な違いによって飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸に分類されます。
脂質はエネルギー源となり人体にとって必要な栄養素の一つであるとこには間違いありませんが、脂質を摂りすぎると血中のLDLコレステロール、中性脂肪の上昇、メタボリック症候群の悪化などを引き起こし、人体へ悪影響を及ぼす可能性があるので注意が必要です。
脂肪酸の種類は?
脂肪酸は脂質を構成する重要な要素です。ここでは、脂肪酸の分類について解説します。
-
飽和脂肪酸:全ての炭素原子が単結合でつながった脂肪酸
-
不飽和脂肪酸:二重結合を持つ脂肪酸
飽和脂肪酸とは
飽和脂肪酸の化学式は一般的にC_nH_(2n+1)COOHと表され、n は脂肪酸の炭素数を表します。例えば、ステアリン酸(18炭素の飽和脂肪酸)の化学式はC₁₈H₃₆COOHとなります。
飽和脂肪酸の種類
飽和脂肪酸には、様々な種類があります。主な飽和脂肪酸の種類をいくつか挙げます:
-
ラウリン酸: C₁₂H₂₄O₂、主にココナッツ油やパーム核油に含まれ、特に中鎖脂肪酸に分類されます。
-
ミリスチン酸: C₁₄H₂₈O₂、動物性脂肪や一部の植物油脂に含まれます。
-
パルミチン酸: C₁₆H₃₂O₂、主にパーム油や動物性脂肪に含まれ、広く使用されています。
飽和脂肪酸の摂取源は食べ物?
動物性脂肪
植物油脂
加工食品
飽和脂肪酸の効果と働き
飽和脂肪酸は、体内でさまざまな重要な役割を果たしていますが、適切な量で摂取することが重要です。
エネルギー源
体内でのエネルギー供給源として利用されます。特に運動時や長時間の断食後に、脂肪からエネルギーを供給する際に重要です。
細胞膜の構成
飽和脂肪酸は、細胞膜の構成要素としても重要です。特に安定性が求められる細胞膜や組織の構造的な一部としてとても重要な機能を発揮します。
ホルモンの合成
一部のホルモンの合成にも必要不可欠です。例えば、性ホルモンや副腎皮質ホルモンの一部は、飽和脂肪酸から合成されます。
脂溶性ビタミンの吸収
脂質の飽和脂肪酸は、脂溶性ビタミン(A、D、E、Kなど)の吸収を助ける役割があります。これらのビタミンは脂肪と共に摂取することで効率的に吸収されます。
飽和脂肪酸の摂取目安
飽和脂肪酸の摂取目安を決めるために参考になった欧米諸国のメタ解析・研究があります。(1)この研究では、飽和脂肪酸摂取量が1日の総摂取エネルギーの何%であるかと血中LDLコレステロール値の関係性を調べています。
飽和脂肪酸摂取量がエネルギー比率 10% E(エネルギー)未満では LDL‒コレステロールが 12% 減少するのに対し、飽和脂肪酸摂取量がエネルギー比率7% E 未満ではより強い 16% の LDL‒コレステロールの減少を認めています。
これをもとに、厚生労働省は日本人の飽和脂肪酸摂取量を1日に必要なエネルギーの7%未満と設定しています。
具体的には、まず自分の1日に必要なエネルギー量を把握しておく必要があります。1日に必要なエネルギーは標準体重×係数で、標準体重は身長(m)×身長(m)×22、係数は作業量、活動量によりことなります。詳しくは下記をご参照ください。
推奨される飽和脂肪酸摂取量は1日のエネルギー必要量の7%未満となるので、0.07をかけた数値になります。
例えば、身長160cmでデスクワークが主な仕事をしている方の場合、1日必要エネルギー量は1.6×1.6×22×(25~30)=1408~1690kcalとなり、推奨される飽和脂肪酸摂取量は(1408~1690)×0.07=99~118kcal(11~13g)となります。
【身体活動量の目安】
|
やや低い(ディスクワークが主な人・主婦) |
25~30kcal/㎏標準体重 |
|
適度(立ち仕事が多い職業:農作業・漁業など) |
30~35kcal/㎏標準体重 |
|
高い(力仕事の多い職業:土木建築業など) |
35~kcal/㎏標準体重 |
飽和脂肪酸を多く含む食品
飽和脂肪酸は特に動物性食品に多く含まれており、常温で固形であるという特徴を持っています。飽和脂肪酸を多く含む食品で主なものを以下にご紹介します。(2)
|
食品 |
100gあたりの飽和脂肪酸含有量 |
|
ココナッツパウダー |
55.25g |
|
無塩バター |
52.43g |
|
コーヒーミルク |
32.79g |
|
生クリーム |
27.62g |
|
マーガリン |
21.86g |
|
鶏肉の皮 |
16.30g |
|
牛サーロイン肉 |
16.29g |
|
ベーコン |
14.81g |
|
豚バラ肉 |
12.95g |
|
ウインナー |
10.11g |
|
卵黄 |
9.22g |
飽和脂肪酸はなぜ体に悪い?
過剰な飽和脂肪酸が人体に悪影響を及ぼす主な理由は、以下の点が考えられます。(3)
LDLコレステロールの増加
飽和脂肪酸は、血中のLDLコレステロール(悪玉コレステロール)を増加させるとされています。高いLDLコレステロールは動脈硬化のリスク因子であり、心血管疾患や脳卒中などのリスクを高めます。
血管の健康への影響
飽和脂肪酸を多く摂りすぎると、血管内の炎症が増え、血管の内壁に損傷が生じやすくなり、結果的に動脈硬化が進みやすくなります。
炎症の促進
過剰な飽和脂肪酸により、炎症反応を引き起こすサイトカインの放出が増加することがあります。慢性炎症が促進され、様々な慢性疾患の発症リスクが高まる可能性があります。
体内の抗酸化能力の低下
過剰な飽和脂肪酸は体内の抗酸化能力が低下する可能性があり、また、細胞や組織への酸化ストレスが増加し、細胞の損傷や老化が進む可能性があります。
糖尿病や肥満のリスク増加
脂質を過剰に摂取すると共に、飽和脂肪酸の摂取量を増やすこととなります。そして、飽和脂肪酸は不飽和脂肪酸と比べて、体内で脂肪組織に蓄積されやすいとされています。
飽和脂肪酸の摂取が過剰な場合、インスリン感受性の低下や肥満のリスクが増加するとされています。糖尿病やメタボリックシンドロームの発症を促進する可能性があります。
また、肥満は余剰のエネルギーが中性脂肪の形で脂肪細胞に大量に蓄積された状態であり、肥満などにより血中や細胞内の脂肪酸レベルが上昇すると脂肪毒性と呼ばれる細胞障害が生じメタボリック症候群の病態悪化につながることが考えられます。飽和脂肪酸は、肥満脂肪組織を中心とした全身性のインスリン抵抗性・慢性炎症や血管内皮機能低下を来たし、肥満者の動脈硬化進展における重大なリスクと考えられます。
まとめ
飽和脂肪酸の過剰摂取はメタボリック症候群や血管疾患を引き起こすリスクとなる可能性が高く、過剰な摂取は注意が必要ですが、飽和脂肪酸は私たちの生命維持に必要な重要なエネルギー源であるので、適切な量はしっかりと摂取することもまた重要です。
厚生労働省は飽和脂肪酸摂取量を1日に必要なエネルギーの7%未満を推奨しており、この基準を参考に、その他の栄養素もバランスよく取り入れた食事を摂取することが重要です。
また、脂質を摂取すると共に、不飽和脂肪酸も摂取できます。不飽和脂肪酸は飽和脂肪酸の炎症惹起作用に拮抗して、抗炎症・抗動脈硬化、心血管病発症予防効果を発揮することが示唆されており、不飽和脂肪酸を含む食品、サプリメントも取り入れると良いでしょう。
不飽和脂肪酸のオメガ3の説明:オメガ3の11つの効果・働きと手軽に摂取する方法|認知機能・心血管系の健康を支える