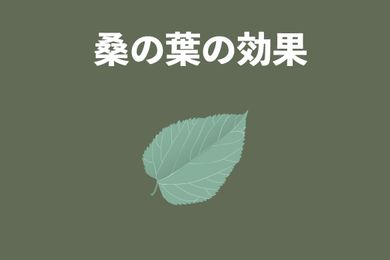腸活という言葉はすっかり定着していますが、実際何をしたらいいのか分からないという方も多いのではないでしょうか。基本的に腸活とは、腸内環境を整える活動のことを指します。
便秘を解消し、毎日状態の良い便を排出することが、腸活のスタートラインと言えるでしょう。今回は腸活の中でも大切な、食事面についての話をします。どんな食べ物が腸活に役立つのか紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
「腸活」とは?
腸活とは、腸内環境を整えることで、健康や美容、さらには免疫力の向上を目指す取り組みを指します。腸内には多くの善玉菌や悪玉菌が存在し、これらのバランスが体調に大きな影響を与えます。
腸活には「プレバイオティクス」「プロバイオティクス」の2つの要素が大切です。プレバイオティクスは善玉菌を育てる役割があり、プロバイオティクスは善玉菌を届ける役割があります。つまり、食物繊維や発酵食品を積極的に摂取することで、善玉菌を増やし、腸の働きを活性化させることが腸活の基本です。
|
成分 |
役割 |
主な成分 |
|
プレバイオティクス |
善玉菌を育てる |
・食物繊維(野菜・果物など) ・オリゴ糖(ごぼう・玉ねぎなど) |
|
プロバイオティクス |
善玉菌を腸に届ける |
・乳酸菌(ヨーグルト・発酵食品など) ・ビフィズス菌(ヨーグルト・サプリメントなど) |
腸内フローラのベストなバランスとは?
腸内細菌の様子は「腸内フローラ」と呼ばれるのですが、腸内に存在する多種多様な細菌が、植物の「フローラ(flora)」のように集まって共存していることに由来します。
「フローラ」という言葉はもともと植物群や植物の生態系を指すラテン語から来ており、微生物が腸内でコミュニティを形成し、バランスを保ちながら共存している様子を植物群に例えているのです。
腸内フローラは、善玉菌、悪玉菌、日和見菌のバランスによって構成され、健康や免疫、消化に影響を与えます。これらの腸内細菌の総数は100兆個にも及ぶと言われています(1)。
善玉菌を優勢にすることが腸活の基本となりますが、そのカギは日和見菌にあります。日和見菌はその名の通り、その時々の腸内環境により善玉菌側についたり、悪玉菌側についたりと役割を変えるのです。日和見菌は最も数が多いため、腸内環境を整えて善玉菌の味方に付けましょう。
腸活のメリット
腸活をすることで、体全体の健康や美容に大きな効果が期待できます。ここでは、腸活のメリットを整理してみましょう。
1. 便秘の改善
腸活の大きなメリットは便秘の改善です。「たかが便秘」と侮っていると、下腹部の痛みや不快感によるQOL(生活の質)の悪化や、自律神経の乱れなど、さまざまなリスクを招きかねません。腸活により善玉菌が増えることで、腸の動きが活発になり、便の排出がスムーズになります。
2. 代謝の向上と肥満防止
腸活により腸内環境が整うと、脂肪の吸収を抑え、なおかつ効率的にエネルギーを消費できる体質へと変化することが期待できます。
人間の腸内細菌は日和見菌の割合が最も多く、その中でも「ファーミキューテス門」と「バクテロイデス門」に所属しています。肥満傾向にある人はファーミキューテス門が多く、やせ傾向にある人はバクテロイデス門が多いという研究結果も発表されているのですが、その理由は、バクテロイデス門が作り出す短鎖脂肪酸にあるようです。短鎖脂肪酸には余分な脂肪の蓄積を防ぐ効果があるとされているため、肥満の防止につながるとされています(2)。
バクテロイデス門を増やすには、食物繊維をたっぷり摂取するなど、食事の改善が大切です。腸活でやせやすい体を目指しましょう。
3. 美肌効果
腸内環境が整うと、老廃物がスムーズに排出されるため、肌の調子が良くなります。便秘により腸内に便が留まる時間が長くなるほど、老廃物が再吸収されやすくなり、肌荒れにつながるからです。
また、腸活により腸内環境が整うことで、美肌作りに欠かせない栄養素が効率良く吸収できるようになります。肌のケアをするなら、肌の表面だけでなく腸活で体の内側から整えていきましょう。
4. 免疫力の向上
腸は免疫システムの大部分が集中しており、その割合はおよそ7割と言われています。そもそも腸に免疫システムが集中している理由は、栄養や水分などさまざまなものを吸収する場所であるから。有害な菌や物質が取り込まれた場合、腸がブロックしないと健康に悪影響を及ぼす可能性が高くなります。そのため、砦として腸には免疫システムの大部分が集まっているのです。
ただし、免疫システムを十分に機能させるには、腸内環境の改善が不可欠。善玉菌を増やし、腸内環境を良くすることで免疫力が高まり、風邪や感染症などにかかりにくい体を作ることができます。
5. 精神的な安定
腸は「第二の脳」とも呼ばれており、腸内環境が整うと、ストレスや不安感が軽減され、精神的にも安定しやすくなります。
その理由は、腸内環境が整うことで“幸せホルモン”と呼ばれている「セロトニン」が作られやすくなるから。セロトニンは食事に含まれる「トリプトファン」という必須アミノ酸が材料となります。トリプトファンは腸で吸収された後、脳に届けられ、精神的な安定をもたらすセロトニンへと変化します。腸内環境が整っているとトリプトファンが吸収されやすくなり、セロトニンの生産が捗るというように、好循環が期待できるのです。
腸内でもセロトニンは作られていますが、こちらは脳へ届けられることはなく、腸の蠕動運動を促したり、全身の骨形成などの役割を担っています。
腸活の詳しいやり方を知りたい方は、こちらの記事がおすすめです。
腸に良い食べ物ベスト10選
腸内環境を整えるために役立つ食べ物の中から、特におすすめしたいものを10選紹介します。これらの食品は、腸の働きを活発にし、善玉菌を増やす効果が期待できるものです。また、組み合わせて食べることで、より腸活効果がアップします。
1. ヨーグルト

1日の目安量:100g程度
ヨーグルトは発酵食品であり、乳酸菌やビフィズス菌など善玉菌を豊富に含みます。善玉菌の補給源となり腸内環境を整える働きがあることから、便通改善に効果的です。もし善玉菌が生きて腸に届かなくても、腸内の善玉菌のエサとなるため、ムダにはなりません。食物繊維を含む果物と組み合わせるのがおすすめです。
2. 納豆

1日の目安量:40g(1パック)
納豆に含まれる納豆菌が、腸内で善玉菌を増やす手助けをします。また、納豆には食物繊維が多く含まれており、摂取することで善玉菌のエサとなるのもポイント。これらの要素が合わさることで、腸内環境を効果的に整えます。食物繊維や乳酸菌を含むキムチとも好相性です。
3. キムチ

1日の目安量:40g(小鉢1杯分)
キムチは乳酸菌の発酵により、独特の酸味が生まれる発酵食品です。植物由来の乳酸菌は胃酸に強く、生きて腸まで届きやすいという特徴があります。また、キムチの材料である白菜や大根などの野菜には食物繊維が含まれている点も、腸にうれしい効果をもたらします。食物繊維を含むきのこ類や納豆などと組み合わせるとよいでしょう。
4. きのこ類

1日の目安量:100g(1パック)
しいたけ・しめじ・エリンギなどのきのこ類には、食物繊維が豊富に含まれます。食物繊維の中でも不溶性食物繊維(水に溶けない性質)を多く含みます。腸内の善玉菌のエサとなるだけでなく、便のかさを増やして便通を促すなどの効果が期待できます。発酵食品の味噌で調理したり、キムチや納豆などと合わせるのもおすすめです。
5. 味噌

1日の目安量:大さじ1/2杯(味噌汁1杯分)
味噌は日本の伝統的な発酵食品のひとつ。味噌に含まれる乳酸菌や麹菌が、善玉菌を増やすサポートをします。また、味噌の材料である大豆に含まれる、オリゴ糖や食物繊維も腸内環境を整えるのに効果的です。特におすすめの摂取方法が、味噌汁。ほかの食物繊維を含む野菜と一緒に摂取でき、より腸活効果を高められます。
6. バナナ
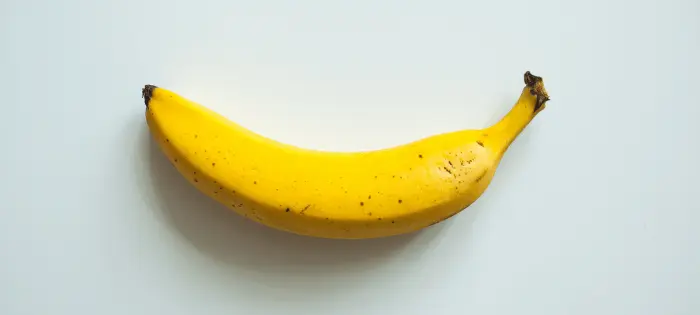
1日の目安量:1本(200g)
バナナは水溶性食物繊維(水に溶ける性質)を含み、腸内を掃除したり、善玉菌のエサになったりします。また、バナナに含まれるオリゴ糖も善玉菌のエサとなります。さらに未成熟の青いバナナにはレジスタントスターチという、食物繊維と同じような働きをする成分が含まれます。より食物繊維のような働きを期待したい場合は、青いバナナを取り入れるのもよいでしょう。
7. オートミール

1日の目安量:90g(1回30gが目安)
低糖質ダイエットに伴い、注目される機会が増えたオートミール。オートミールは不溶性食物繊維と水溶性食物繊維をバランスよく含み、腸活にうってつけの食品です。ヨーグルトなど発酵食品と一緒に摂取すると、乳酸菌の効果が合わさり、さらに腸活に役立ちます。
8. アボカド

1日の目安量:1/2個
アボカドは果物の中でもトップクラスの食物繊維量を誇ります。さらにアボカドを毎日摂取することで、腸内フローラの改善に役立ち、短鎖脂肪酸の増加に役立つという研究もあります(3)。納豆と合わせると、おいしく機能的な腸活メニューになり、おすすめです。
9. りんご

1日の目安量:1/2個
りんごの皮周辺には、ペクチンという水溶性食物繊維が含まれています。これは腸内の善玉菌のエサになるため、なるべく皮ごとりんごを食べるのがおすすめ。乳酸菌を含むヨーグルトと食べたり、オートミールに合わせたりするなど、他の食材との組み合わせも試してみましょう。
10. 甘酒

1日の目安量:100~200ml
発酵食品である甘酒は、善玉菌のエサとなるオリゴ糖を含んでいたり、麴菌が腸内環境を整えたりするなどの特徴があります。なお、甘酒は酒かすから作られるものと、米麴を発酵させて作られるものがあります。どちらにもメリットはありますが、酒かすタイプはアルコールを含むため、誰でも飲める米麴タイプだと安心です。
まとめ
腸活は生活習慣を整えることも大切ですが、食事面に気を配ることでより効果が高まります。中でも食物繊維などの「プロバイオティクス」と、発酵食品などの「プレバイオティクス」を意識して、食事に取り入れるようにしましょう。
忙しくて腸活を意識した食事が摂れない場合は、プレバイオティクスのサプリメントなどを利用するのもおすすめです。自分に合った方法を見つけて、無理なく腸活を続けていきましょう。