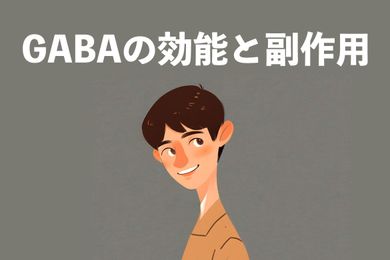ビタミンDといえば、骨の健康をサポートする栄養素としてご存じの方も多いでしょう。ビタミンDはカルシウムの吸収を助けることで健康な骨を維持する効果を持つため、不足すると骨軟化症や骨の成長障害、骨粗しょう症などにつながる可能性もあります。
一体どんな人がビタミンDを摂取する必要があるのでしょうか?ビタミンDについて薬剤師がお答えします。
ビタミンDとは?
ビタミンDは腸からカルシウムをしっかり吸収できるよう助け、健康な体作りにサポートをしてくれるビタミンです。
ビタミンDは脂溶性ビタミンの一つであり、油と一緒に摂取することで吸収率が高まります。食事やサプリメントなどから摂取できますが、体内での生成も可能な栄養素です。
皮膚が太陽の紫外線に一定時間さらされると、コレステロールを原料としてビタミンDが生成されるため、ビタミンDは「太陽のビタミン」とも呼ばれています。
しかし、日本ではビタミンDが不足している方は多いです。
東京慈恵会医科大学の研究によると、2019年4月から 2020年3月までの期間に東京都内で健康診断を受けた 5,518 人を対象に調査を実施し、そのうち98%がビタミンD不足だったと公表しました。(2)
日常的にビタミンDの補給を意識するのはおすすめです。
Tips:ビタミンは、水に溶けやすい「水溶性ビタミン」と油に溶けやすい「脂溶性ビタミン」に分類されます。
ビタミンDの種類
ビタミンDにはD2からD7までの6種類がありますが、その中でD4~D7は食品にはほとんど含まれていません。
一般的に「天然由来のビタミンD」と言う場合、ビタミンD2(エルゴカルシフェロール)とビタミンD3(コレカルシフェロール)の2つを指すことが多いです。
天然由来のビタミンDは、大きく分けて2種類に分類されます。1つはキノコなどの植物性食品由来のビタミンD2、もう1つは魚肉や鶏卵などの動物性食品由来のビタミンD3(コレカルシフェロール)です。
どちらも体内で肝臓や腎臓を経て、活性型ビタミンDへ変換されたのちに作用を発揮できるようになります(1)。
ビタミンDの働き
ビタミンDは強い骨を維持するためや健康のために必要な栄養素です。骨の主要な構成成分であるカルシウムの吸収を助けることにより、強い骨を維持します。
現在、多くの日本人でビタミンDが慢性的に不足していることが報告されました。
ビタミンDが不足すると、骨軟化症や骨粗しょう症などの骨がもろくなる病気にかかったり、骨の成長に影響がでたりする可能性があり、人体にとって欠かせない栄養素の一つです。
ビタミンDはどのように摂取する?
体内のビタミンD量を増加させるためには、一般的に2つの方法があります
-
日光浴による体内での生成を促す
-
食事やサプリメントから摂取する
体内での生成
適度に日光を浴びることで、体内でビタミンDが合成されます。しかし、日照時間は地域や季節によって異なるため、ビタミンDの合成量は一定ではありません。
また、美容のために、日焼け止めや日傘の使用、UVカットの服を着用する人が増えています。
そのため、肌が直接紫外線を浴びることが大幅に減り、ビタミンDの生成が制限されている可能性があります。
特に冬は日照時間が短いため、紫外線にあたる機会が少なくなりやすいため、積極的に日光浴を取り入れるようにしましょう。
代案として、食品からのビタミンD摂取をより意識する必要があるかもしれません。
食事やサプリメントから摂取
ビタミンDを豊富に含む食材としては、キクラゲ、しらす干し、卵黄などがあげられます。
バランスよく摂取する分には問題ありませんが、いつも同じような食材ばかり食べていると、特定の栄養素が過剰になったり、消化に負担がかかったりします。
そこでサプリメントを用いれば、手軽で効率的にビタミンDを補うことができます。
ただし食事からの摂取量には個人差があるため、過剰摂取には注意が必要です。
さらに一緒に配合されている他の栄養素にも着目してサプリメントを選ぶようにしましょう。
ビタミンDの摂取目安量
厚生労働省の食事摂取基準量によると、ビタミンDの摂取目安量と上限量は以下のようになります。(3)
|
性別 |
男性 |
女性 |
||
|
月齢や年齢 |
目安量 |
上限量 |
目安量 |
上限量 |
|
0~11(ヵ月) |
5.0 |
25 |
5.0 |
25 |
|
1~2(歳) |
3.0 |
20 |
3.5 |
20 |
|
3~5(歳) |
3.5 |
30 |
4.0 |
30 |
|
6~7(歳) |
4.5 |
30 |
5.0 |
30 |
|
8~9(歳) |
5.0 |
40 |
6.0 |
40 |
|
10~11(歳) |
6.5 |
60 |
8.0 |
60 |
|
12~14(歳) |
8.0 |
80 |
9.5 |
80 |
|
15~17(歳) |
9.0 |
90 |
8.5 |
90 |
|
18以上(歳) |
8.5 |
100 |
8.5 |
100 |
|
妊婦 |
- |
8.5 |
- |
|
|
授乳婦 |
8.5 |
- |
||
参照:「日本人の食事摂取基準(2020年版)」策定検討会報告書 /厚生労働省(2)
-
乳児(1歳未満)は目安量5.0μg/日(=200IU)上限量25 μg/日(=1000IU)
-
幼児(1歳以上7歳未満)は目安量3.0~5.0μg/日(=120~200IU)上限量20〜30μg/日(=800〜1200IU)
-
小児(7歳以上15歳未満)は目安量5.0~9.5μg/日(=200~380IU)上限量40 〜80μg/日(=1600〜3200IU)
-
青年(15歳以上18歳未満)は目安量8.5~9.0μg/日(=340~360IU)上限量90μg/日(=3600IU)
-
18歳以上の成人と妊婦・授乳婦は目安量8.5μg/日(=340IU)上限量100 μg/日(=4000IU)
ビタミンDを作るためには、適度に日光を浴びることが大切です。ただし、日照時間は地域や季節によって変わるので、注意しながら日光浴の時間を注意してください。
また、ビタミンDの食事からの摂取量には個人差があり、年齢によっても摂取目安量が異なりますが、実は多くの日本人でビタミンDが慢性的に不足していることが報告されました。
ビタミンD不足を起こさないために、日頃からビタミンDの摂取を心がけ、適度な日光浴を取り入れた生活を送るようにしましょう。
ビタミンDを豊富に含む食品
ビタミンDは日光浴により皮膚で合成されますが、食べ物からの摂取も大切です。ビタミンD2は、日光(紫外線)を照射したキノコ類に多く含まれます。
一方で、ビタミンD3を多く含むおもな食品は、魚・卵・乳製品です。動物性のビタミンD3は、植物性のビタミンD2に比べて生体内での利用率が優れています。
ビタミンDがおすすめな人
-
日焼けを避けたい人、日光を浴びる機会の少ない人
-
高齢者
-
免疫機能を向上させたい人
-
妊娠中や授乳中の女性
赤ちゃんと新生児はビタミンDが不足しがちです。そのため、妊娠中や授乳中の女性はビタミンDを摂取して、赤ちゃんや新生児に届ける必要があります。
ビタミンDが不足すると
ビタミンDはカルシウムの吸収を助け、骨の形成をサポートします。ビタミンD不足すると、骨がやわらかくなり、骨密度の低下、骨粗鬆症、骨軟化症や骨折リスクが高まります。
また、子どもにはくる病を引き起こし、成長や筋力に影響を与える可能性があります。
さらに、ビタミンD不足は免疫機能にも悪影響を及ぼすため、感染症やアレルギーのリスクが増加します。
ビタミンD2とビタミンD3の違いは?
ビタミンD2とビタミンD3は、摂取後の体内への吸収量は同程度ですが、ビタミンD3のほうが利用効率が良いとされています。
ビタミンD2とビタミンD3の違いについて確認しておきましょう。
含有されている食品の違い
ビタミンD2は「植物性食品」に含まれるのに対し、ビタミンD3は「動物性食品」に含まれています。
さらに、サプリメントに含まれているビタミンDには、「食品由来の天然ビタミンD」なのか、食品から抽出した「天然由来の合成ビタミンD」なのかといった原材料の違いもあります。
原材料名欄に”サーモンオイル”などの食品名が記載されている際は、食品由来の天然ビタミンDです。
一方で、単に"ビタミンD”や”ビタミンD2””ビタミンD3”と記載されている場合は、ほとんどのケースで天然由来の合成ビタミンDが使用されています。
【ビタミンD2サプリメントの原料】
-
天然由来の原料:キノコなどの植物性食品
-
合成由来の原料:キノコや酵母などから抽出したビタミンD2
【ビタミンD3サプリメントの原料】
-
天然由来の原料:魚肉や魚類の肝臓・卵黄などの動物性食品
-
合成由来の原料:ラノリン(羊毛脂)・魚の内臓などから抽出したビタミンD3
前述したとおり、動物由来のビタミンD3のほうが植物由来のビタミンD2よりも人間の体内で効率的に働くとされています。
効率的にビタミンDを摂取したい方はビタミンD3のサプリメントが望ましいでしょう。
食品中のビタミンD2とD3含有量の違い
食品100g中のビタミンD含有量を比較すると、動物性食品(ビタミンD3)のほうが植物性食品(ビタミンD2)よりも多い傾向にあります。
このような傾向がある中で、きくらげ(乾)は植物性食品ですが、100g中にビタミンD2を多く含んでいます。
しかし、きくらげは1人分4gほどのレシピが一般的なので、1人分の使用量が少なく、一度に摂取できるビタミンD2の量は5.2㎍ほどです。
一方で、ビタミンD3が含まれるしらす干し(半乾燥)は、丼にのせれば30~50g程度使用するので、一度に18~30㎍も補給できます。
きくらげのように100g中のビタミンD含有量が多くても、一度に摂取する量が少ない場合は、結果的に摂取できるビタミンDの量が少なくなってしまいます。
文部科学省の食品成分データベースや、ビタミンDの摂取目安量を参考に、バランスの取れた食事を摂取するようにこころがけましょう(6)。
血中ビタミンD濃度の維持時間
国際的な研究論文によると、ビタミンD3はビタミンD2よりも、代謝物である25OHDの血中に留まる時間が長いと報告されています。
ビタミンD3の方がビタミンD2よりも作用持続時間が長くなることが期待できます。(4)