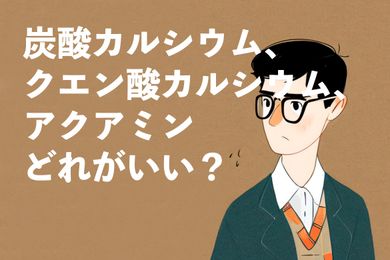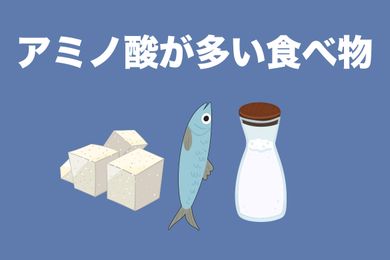皆さんは「サナギタケ」とは何かをご存知ですか?似たものとして挙げられる「冬虫夏草」という言葉を聞くと、どういったものかイメージできる方が多いかもしれません。
冬虫夏草は栄養ドリンクなど含め、東洋医学の重要な生薬として知られていますが、サナギタケは冬虫夏草と同じものなのでしょうか?
また、冬虫夏草と並べられるサナギタケにはどんな効能があり、摂取にはどんな制限があるのでしょうか?この薬食同源のサナギタケが私たちの健康にどんな効果を持つかを解説します。
サナギタケとは?

サナギタケ(学名:Cordyceps Militaris)は、北冬虫夏草または北虫草とも呼ばれ、ノムシタケ属(Cordyceps 属)に分類される真菌類の一種です(1)。真菌類にはキノコや酵母などが含まれているため、「サナギタケはキノコの仲間」ということもできます。
サナギタケは「昆虫に寄生するキノコ」という表現でよく知られる特徴的な生態をしており、チョウの幼虫(一般的に「芋虫」として知られるもの)に寄生して、体内で菌糸を伸ばしていきます。
サナギタケは菌糸を広げたことで宿主である幼虫が死んでしまうと、体表から棍棒上の子実体を形成します。
サナギタケと冬虫夏草は同じ?
サナギタケは私たちのよく知る冬虫夏草とはどう違うのでしょうか?実は現在知られているノムシタケ属は数百種類以上あるとされており、冬虫夏草(学名:Ophiocordyceps sinensis)もノムシタケ属の一種です。
サナギタケと冬虫夏草の両方を指して、「虫に寄生して菌糸を伸ばしたキノコと宿主の死骸を用いた生薬」という意味で、広義の「冬虫夏草」という言葉を日本で用いることもあります。
しかし、冬虫夏草はコウモリガの幼虫を宿主とする点などサナギタケと異なる点もあり、2007年に報告されたノムシタケ属の新しい分類学上の定義においても、サナギタケと冬虫夏草は、同じ属に分類される別の種を指すものとされています(2)。
つまり、サナギタケと冬虫夏草は厳密には別の種とされています。この考え方は、生薬として古くから用いてきた人々の狭義の「冬虫夏草」の考え方とも一致しているとされています。
サナギタケの用途は?
サナギタケや冬虫夏草を含むノムシタケ属が虫の死骸から子実体を形成させた状態のものは、紀元前2000年にはその存在が人類に知られていたとされており、東洋医学において最も重要な生薬のひとつとされてきました(3)。
自然にできた冬虫夏草は非常に希少である一方、サナギタケは冬虫夏草に比べると簡易に培養できることや、化学組成や薬効が冬虫夏草と似ていることなど多くの利点を持つことが分かったため、近年サナギタケは学術界でも非常に注目されています。
培養により研究材料を入手できることから、冬虫夏草よりもサナギタケは効果についての臨床試験が多く行われており、安全性の試験も冬虫夏草より充実しているとされています(1)。
サナギタケの効果とは?

サナギタケの研究は近年非常に豊富で、その多彩な栄養に関する詳細な分析が進められてきました。
サナギタケには、サナギタケから発見された抗生物質であるコルジセピン、免疫調整作用を持つ多糖類、抗炎症作用を持つアデノシン誘導体、利尿作用から眼圧低下や急性腎不全治療で用いられる糖アルコールであるD-マンニトールや、さまざまな生理活性物質に代謝されるL-トリプトファンなど、多くの成分が含まれていることが報告されています(4)。
サナギタケから見つかったコルジセピンの効果は?
コルジセピンはサナギタケから見つかった生理活性物質で、現在では核酸系の抗生物質として認識されているものです(5)。
コルジセピンはゲノムDNAの構成要素の一つとして、細胞のガン化の阻害と、ガン細胞の正常化にも寄与することが示唆されています。コルジセピンには、腫瘍増殖を抑える効能の他にも、抗炎症作用、脳血管や心血管の保護作用が報告されており、その効能から注目を集めています(6)。
サナギタケに含まれる多糖類の効果は?
多糖類とは、ブドウ糖として知られるα-グルコースやマンノースのような単糖類がいくつも繋がってできる高分子です。
「単糖類が繋がっているもの」という印象以上に、多糖類には抗炎症作用や抗酸化作用、免疫調整作用など、さまざまな効能があることが報告されており、その有用性から近年非常に注目されている物質です(7)。
多糖類は構成する単糖類、繋がり方などによって非常に多くの種類がありますが、サナギタケに含まれる多糖類も同様に、抗酸化作用、免疫調節作用、抗腫瘍作用、樹状細胞の成熟作用、抗炎症作用など、数多くの生理活性を示唆する報告がされています(4)。
サナギタケの多糖類をマウスに摂取させて抗炎症作用と活性酸素除去作用を調べた研究では、サナギタケの多糖類を摂取したグループのマウスの脾臓リンパ球活性、白血球総量、血清中の免疫グロブリン(IgG)レベルが有意に増加し、免疫機能が改善されたことが報告されています(4)。
また、この研究では、サナギタケの多糖類を摂取したマウスの体内の脂質過酸化指標物質マロンジアルデヒドの量が減少しており、酸化ストレスに対する保護の効果が免疫調整に作用しているということが示唆されています。
サナギタケの効果を調べたヒトに対する研究の結果は?
サナギタケをヒトに対して投与した臨床研究では、低容量(サナギタケ粉末0.5 g)、中容量(1.5 g)、高容量(3.0 g)それぞれを投与して効果を検証したところ、3つの容量全てで炎症性サイトカインの減少が確認され、サナギタケが免疫を調節し、過剰な炎症反応を抑制する作用があることが示唆されました(8)。
この研究を報告したチームは、サナギタケが免疫系を調節することにより、腫瘍形成抑制や免疫に起因する疾患の抑制など、さまざまな効能に繋がる可能性があると述べています。
サナギタケの適切な摂取の方法
他の糸状菌(キノコなど)と同様に、サナギタケは子実体に含まれる栄養価の方が菌糸体よりも高いと考えられています。実際にコルジセピンなどの成分は子実体に含まれていることから、サナギタケの効能成分を最大限活用するには、子実体を摂取することが効果的と考えられています(3)。
サナギタケには抑うつ状態の治療で重要となるL-トリプトファンやアデノシン誘導体が含まれることから、その安全性を調べるヒトを対象とした研究が実施されています(9)。
この研究では、デュロキセチンによる治療を受けている大うつ病患者に、サナギタケ抽出物またはプラセボのどちらかを6週間併用させた上で、両グループの安全性を比較しました。その結果、プラセボ群とサナギタケ抽出物摂取群とで有害事象の発生率に有意差はなく、サナギタケの摂取が安全であることが示唆されています。
マウスを用いた毒性の試験でも、高容量のサナギタケを投与しても副作用は確認されなかったと報告されています(10)。
これらの結果や生薬として利用されてきた背景から、サナギタケの安全性は現時点では高いと考えられており、副作用報告も限られたものであるとされています(9)(10)。
サナギタケは直接食材として料理に使用することができ、また、サプリメントとしても長期間にわたって摂取することも可能でしょう。
ただし、サナギタケは非常に多くの成分を含むことから、他の薬物を服用している場合は併用を避けるように注意すると、より安全です。
また、なにか症状がある際は、医学・薬学的治療が必要かどうかを、まず医師に相談する必要があります。サナギタケを食品原料として使用する場合、幼児、子供、妊婦、および真菌に過敏な人は、摂取を控えることが推奨されます。