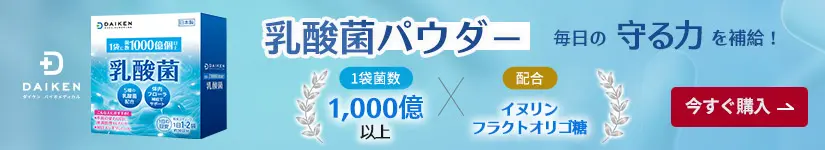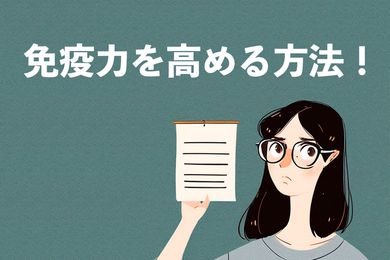近年、健康や美容への関心の高まりとともに「腸活」という言葉を耳にする機会が増えてきました。
しかし、腸活が体に良いことは分かっていても、具体的にどのようなことをすれば良いのか分からないという方も多いのではないでしょうか。
この記事では、誰でも今日から無理なく始められる腸活について、分かりやすく解説します。
腸活について正しく理解し、日々の生活に取り入れたいと考えている方は、ぜひ最後まで読んでみてください。
そもそも腸活って何?
腸活とは、腸内環境を良好に保つことを目的に、日々の生活習慣を整える取り組みのことです。
医学的に明確な定義はありませんが、生活習慣が腸の働きや、腸内細菌のバランスに影響することはよく知られています。
腸内環境が整うと、便通がスムーズになるのはもちろん、体の調子や気分など、さまざまな面で嬉しい変化が期待できます。
つまり、腸活は健康で快適な毎日を送るための、手軽で身近な取り組みなのです。(1)
腸活はどんな人におすすめ?
1. おなかの不調で悩んでいる人
腸内細菌のバランスが崩れると、腸の動きやバリア機能が低下し、便秘や腹部の張り、腹痛といったおなかの不調が起こりやすくなるといわれています。
おなかの不調に対しては、市販薬で一時的に症状を和らげる方法もありますが、根本的な改善を目指すには、日々の食事内容や生活習慣を見直すことが重要とされています。
腸活の第一歩として、排便回数や便の状態など、自分のおなかの変化に目を向ける習慣を持つことから始めてみると良いでしょう。(1)
2. 体調を崩しやすい人
私たちの体には免疫細胞がたくさん存在しており、その約70%が腸に集まっているといわれています。
腸内細菌は、この免疫細胞の働きを助け、体を守る力をサポートしています。
そのため、腸内細菌のバランスが崩れると、免疫の働きが弱くなり、体全体の調子にも影響が出やすいのです。
日頃から体調を崩しやすいと感じている方は、腸活によって腸内細菌のバランスを整えることが、健康を維持する助けになる場合があります。(2)
おすすめ:簡単に免疫力を高める食べものとは?生活習慣のポイントも含め管理栄養士が解説!
3. メンタルが不安定な人
腸と脳は、それぞれ独立した器官のように思われがちですが、実際には密接につながっています。
この双方向の情報ネットワークは「腸脳軸」と呼ばれ、近年の研究では、心の状態にも深く関わっていることが明らかになってきました。
腸内細菌叢のバランスが崩れると、脳と腸のコミュニケーションがうまく働かなくなり、うつ病や不安障害など、さまざまな精神疾患の病態に関与する可能性があると考えられています。
こうした背景から、メンタルが不安定と感じている方にとって、腸活は心の健康を支える土台づくりの一つとして注目されています。(3)
4. 肌のトラブルで悩んでいる人
腸内細菌のバランスが崩れると、乾癬やアトピー性皮膚炎、ニキビといった肌トラブルが起こりやすくなることが分かっています。
腸内環境が乱れることで免疫や炎症の調節がうまくいかなくなり、その影響が肌にも現れやすくなるためです。
スキンケアだけでは改善しにくい肌荒れを繰り返している場合、体の内側である腸の状態が関係している可能性も考えられます。
こうした背景から、肌トラブルに悩んでいる方にとって腸活は、外側からのケアを補う内側からのアプローチとしておすすめです。(4)(5)
毎日の食事でできる腸活とは?
1. しっかり水分を摂る
腸活を考えるうえでは食事内容に注目されがちですが、水分摂取も腸の健康を支える重要な要素のひとつです。
水分をしっかり摂ることで便の水分量が保たれ、便が柔らかくなりやすくなります。
その結果、腸の蠕動運動が促され、スムーズな排便につながるのです。
さらに、十分な水分摂取は腸内環境を安定させ、有益な腸内細菌が増えやすい状態になることが分かっています。
その結果、腸粘膜の機能が保たれ、腸全体の健康維持にも役立つ可能性があるのです。
まずは、日頃の水分摂取量を把握し、こまめに水分を摂ることを意識してみましょう。(6)
2. 食物繊維を摂る
腸活を考えるうえで欠かせない栄養素のひとつが食物繊維です。
食物繊維は、私たちの体の中で小腸では消化・吸収されず、そのまま大腸まで届くという特徴を持っています。
大腸に到達した食物繊維は、便の材料となってかさを増やし、便通を整える働きをします。
<食物繊維の代表格>
3.発酵食品を摂る
発酵食品は、毎日の食事に気軽に取り入れられる腸活の強い味方です。
ヨーグルトや納豆、味噌などを習慣的に食べることで、ビフィズス菌や乳酸菌といった善玉菌が増えます。
善玉菌が増えると、腸の働きが活発になり、便通が改善し、おなかの調子が整いやすくなるといわれています。
発酵食品の魅力は、特別な準備が必要ないという点です。
日々の食事に発酵食品を上手に取り入れてみましょう。(9)
4.オリゴ糖を摂る
オリゴ糖は、ビフィズス菌や乳酸菌などのプロバイオティクスを増やす手助けをします。
ビフィズス菌や乳酸菌などの腸にとって有益な菌が増えることで、腸内環境が整いやすくなります。
オリゴ糖は、ちょっとした工夫で毎日の食事に取り入れやすい甘味料です。
まず手軽なのが、飲み物やヨーグルトに加える方法です。
オリゴ糖は、優しい甘さがあるため、砂糖の代わりとしてコーヒーや紅茶、プレーンヨーグルトなどに少量混ぜると、味を大きく変えずに手軽に取り入れられます。(10)
5. ポリフェノールを含む食品を摂る
腸活で積極的に摂りたい成分のひとつがポリフェノールです。
ポリフェノールは、野菜や果物、コーヒー、紅茶など、身近な植物性食品に豊富に含まれる成分で、腸内で特別な役割を果たします。
ポリフェノールはそのままでは体に吸収されにくいのですが、腸内細菌の働きによって小さく吸収されやすい物質に変換されます。
この時、腸内の善玉菌が元気になり、腸内環境が整いやすくなるのです。
日々の食事で色とりどりの野菜や果物、紅茶や緑茶、コーヒーなどポリフェノールが含まれる飲み物を意識して取り入れることもおすすめです。(11)
腸活は生活習慣も大切!
食事と合わせて生活習慣の改善は腸活に大切です。
ここでは、腸活をする上で気を付けたい生活習慣のポイントをご紹介します。
1.十分な睡眠を確保する
良質な睡眠は、腸内環境を整えるうえでも大切な役割を果たしていることが、最新の研究で明らかになっています。
例えば、睡眠不足は腸内細菌叢のバランスを乱し、善玉菌や乳酸菌などの有益な細菌の減少につながる可能性が指摘されています。
つまり、睡眠を十分にとることは、腸内環境を整える腸活の大切な一部でもあるのです。
日々の腸活を意識するなら、まずは夜の睡眠をしっかりとることから始めてみましょう。(12)
2. 有酸素運動をする
近年の研究では、有酸素運動が腸内環境に良い影響を与えることが分かってきています。
ある研究では、1日60分ほど、少し息が弾むくらいの強さ(最大心拍数の約60%)で有酸素運動を行った人を調べたところ、腸内細菌のバランスに変化が見られました。
具体的には、腸内に住む細菌の種類が増えてバランスが整い、腸の中で作られる体に良い成分(短鎖脂肪酸)も増えたことが確認されています。
これまで運動習慣がなかった方は、いきなり激しい運動を行う必要はありません。
まずは、ウォーキングや軽いジョギングなど、比較的負荷の少ない有酸素運動から始め、無理のない範囲で継続することが大切です。(13)
3. おなかのマッサージをする
おなかのマッサージは、腸の働きをサポートするセルフケアのひとつです。
研究では、腹部をやさしく刺激することで副交感神経が活性化され、腸の蠕動運動を促し、便通の改善につながる可能性があることが分かっています。
一方で、おなかのマッサージが腸内細菌を直接増やすという科学的根拠は、現時点では十分にありません。
また、効果に関する研究の多くは便秘などの症状がある人を対象としており、健康な人すべてに同じ効果があるとは限りません。
そのため、おなかのマッサージは、腸内環境そのものを変える方法というより、腸の動きを助ける補助的な腸活として、無理のない範囲で取り入れるのがおすすめです。(14)
4. ストレスを解消する
心理的ストレスと腸内環境の関係をまとめた研究では、ストレスが強い状態にある人ほど、腸内細菌の構成に変化がみられる傾向が報告されています。
一方で、ストレスが腸内細菌の多様性を必ず変化させるとまでは言い切れず、影響の程度や仕組みについては、まだ研究が続いている段階です。
そのため、腸活では食事だけでなく、ストレスをためにくい生活習慣を意識することも大切といえるでしょう。
ストレスを感じた際には、早めに休息を取り、自分なりの方法で気分転換を行うことが大切です。
例えば、ゆっくりと腹式呼吸をする、窓の外を眺めて過ごす、ぬるめのお風呂に入る、軽くストレッチをする、好きな音楽を聴くなど、日常生活の中で意識的にリラックスする時間を作ると良いでしょう。(15)
まとめ
腸活は、難しい知識や特別なアイテムがなくても始められる、身近な健康習慣です。
毎日の食事や運動、睡眠など、普段の暮らしを少し意識するだけで、腸の環境は整いやすくなります。
完璧を目指す必要はなく、小さな一歩で十分です。
できることから取り入れてみると、腸活は自然と生活の一部になっていきます。
自分のペースで、無理なく腸活を続けていきましょう。
腸の健康のためにこちらも参考:消化に良い食べ物とは?胃腸に優しい食材について管理栄養士が解説