古くから日本で深く浸透してきた魚食文化。近年、1人当たりの購入量は減少傾向にある半面、マグロやサンマ、カツオなどはむしろ増加しているというデータがあります(1)。
特にカツオやサンマなどの魚は「青魚」と呼ばれ、オメガ3脂肪酸の一種であるDHAとEPAを豊富に含みます。
近年、機能性成分として注目されているDHA・EPAは、人々の健康を維持するために重要な栄養素です。今回はそんなDHA・EPAを含む青魚の種類と栄養素の働き、食べるメリットについて解説します。
青魚とは?

青魚は、背中から見て皮が青い魚のことを言います。一般的に赤身の魚が多く、比較的漁獲量の多い大衆魚で、群れを成して泳ぐ回遊魚などの共通点を持ちます。
例として、サバやイワシ、サンマなどがあてはまりますが、これは魚の外観や肉質から便宜上ついた名前のことで、実は明確な定義がありません。
そのことを踏まえたうえで、青魚の種類にどんなものがあるのかを見ていきましょう。
青魚の種類は?
ここからは、日本でよく食べられている青魚の種類と特徴について解説します。
サバ科

サバ科の魚には、マサバやマグロ、カツオ、サワラなどが該当します。
「紡錘型」や「流線型」と呼ばれる体型を持ち、高速で泳ぐのが特徴です。ほかの魚に比べて赤血球が多く、筋肉に多くの酸素を送れるように適応しています。鱗が目立たないのも特徴です。
マグロの栄養:マグロの栄養と健康効果を管理栄養士が徹底解説!部位別・種類別の比較やおすすめの食べ方、保存方法も伝授
アジ科

マアジやブリ、カンパチ、ヒラマサなどが該当します。
アジという名前は味がよいことから名づけられ、その多くが食用として利用されます。
ニシン科

ニシン、マイワシ、コハダ、サッパなどがあてはまります。
世界に200種類以上いると言われるニシン科の魚。腹部の真ん中に鋭いとげ状の大きな鱗(稜鱗)を持つのが特徴です。塩焼きや甘露煮、酢じめなど幅広い食べ方で親しまれます。
サンマ科

体型が刀に似ているサンマは「秋刀魚」と書き、旬は9〜11月頃です。
タチウオ科

銀白色の体色がトレードマークで、刀に由来して名づけられたと言われています。
トビウオ科

尾ビレで水面をたたくことで浮上し、羽のような大きな胸ビレを広げて飛びます。
時速70kmで水面下を泳ぎ、浮上した後の飛行距離はなんと400mを超えることもあるのだとか。
九州や日本海側では、「アゴ」と呼ばれ、だしに使われるほか、塩焼きや南蛮漬け、刺身にしても食べられます。
サヨリ科

下あごが鋭く突き出ているのが特徴で、大きいものだと40cmほどの体長になります。
「春告魚」と呼ばれ、春にかけて旬を迎える魚です。塩焼きや刺身などで召し上がれます。
カタクチイワシ科

下顎が小さく、上顎しか見えないのが名前の由来。鮮魚として見ることは少ないものの、しらすやちりめんじゃこの原料として有名です。
青魚の栄養素は?青魚を食べるとお体に良い?
一般的に「身体によい」と言われる青魚ですが、その理由はよくわからないという場合も多いのではないでしょうか?
そこでここからは、青魚に含まれて不飽和脂肪酸であるDHAとEPAの働きについて解説します。
DHAとEPA
不飽和脂肪酸のDHAとEPAを摂取することで、お体の健康維持にサポートできます。
また、DHA(ドコサヘキサエン酸)はオメガ3脂肪酸の一つで、体内のさまざまな機能にとって重要な多価不飽和脂肪酸です。
DHAは細胞膜の成分であり、考え力にサポートします。一方、EPA(イコサペンタエン酸)はサラサラの成分と知られており、効果が期待されている栄養素です(3)。
DHAとEPAはどちらも体内では産生できない必須脂肪酸で、食品から摂る必要があります。DHAとEPAは牛や豚などの肉類にはほとんど含まれず、青魚からの摂取がおすすめです。
DHA・EPAの両方がバランスよく含まれた青魚を、ぜひ普段の食卓に取り入れてみてください。
DHAとEPAを豊富に含まれる青魚ランキングTop15
種類豊富な青魚の中に、DHAとEPAの含有量が多い青魚ランキングはこちら。
| 順位 |
種類(100g当たり 生での比較) |
DHA(mg) |
EPA(mg) |
合計(mg) |
|
1 |
大西洋サバ(ノルウェーサバ) |
2,600 |
1,800 |
4,400 |
|
2 |
サンマ 皮なし |
2,100 |
1,400 |
3,500 |
|
3 |
ブリ 成魚 |
1,700 |
940 |
2,640 |
|
4 |
タチウオ |
1,400 |
970 |
2,370 |
|
5 |
イワシ類 メザシ |
1,400 |
930 |
2,330 |
|
6 |
カタクチイワシ |
770 |
1,100 |
1,870 |
|
7 |
サバ類 マサバ |
970 |
690 |
1,660 |
|
8 |
ニシン |
770 |
880 |
1,650 |
|
8 |
イワシ類 マイワシ |
870 |
780 |
1,650 |
|
9 |
アジ類 ニシマアジ |
1,100 |
520 |
1,620 |
|
10 |
サワラ |
1,100 |
340 |
1,440 |
|
11 |
カツオ類 カツオ 秋獲り |
970 |
400 |
1,370 |
|
12 |
ブリ ハマチ 養殖 皮付き |
910 |
450 |
1,360 |
|
13 |
シマアジ 養殖 |
900 |
400 |
1,300 |
|
14 |
コノシロ(コハダ) |
410 |
730 |
1,140 |
|
15 |
サバ類 ゴマサバ |
830 |
230 |
1,060 |
参考:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」
1位の大西洋サバは、スーパーなどで「塩サバ」としても見かける魚です。
また、青魚以外では、マグロやウナギ、サケ、マスなどにもDHA・EPAが含まれています。この後、選び方や鮮度を保つ方法も紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
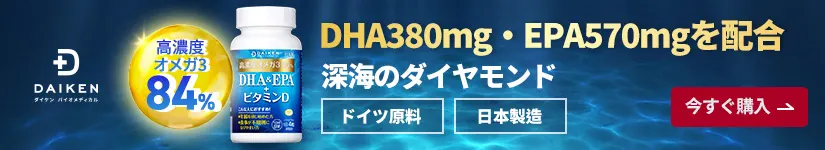
青魚にも含まれる栄養素:アミノ酸、タウリン
青魚にはDHAやEPAのほかにも、注目すべき栄養素があります。
アミノ酸の一種である分岐差アミノ酸は、筋肉の保持や増量に関わり、分解を抑制して筋肉のエネルギー源となります(4)。
マグロの赤身やカツオなどの回遊魚に多く含まれている栄養素です。
また、青魚の血合い部分に含まれるタウリンは、含硫アミノ酸の代謝中間体で、水に溶けやすい性質があります。
そのため茹でたり煮たりして食べる場合は、汁ごと食べきるのがおすすめです。
青魚の選び方
このようにさまざまな栄養素を含む青魚ですが、選ぶときにいくつかポイントがあります。
一尾の場合、目の色が澄んでいるもの、エラの色が鮮やかなもの、体表の色が青く、ツヤがあるものを選ぶとよいでしょう。
また、魚体に張りや弾力があり、腹部から内臓が出ていないことも、鮮度を見分ける目安になります(5)。
青魚を保存する際は、専用の棚を設けるか、小分けにして容器や袋に入れて冷蔵および冷凍します。
魚介類からのドリップは、食中毒の原因になる物質が含まれる可能性があり、ほかの食品にかからないようにするなど注意が必要です(6)。
また、赤身魚の場合は調味料に漬けて保存するのもよいでしょう(7)。
青魚の調理テクニックとレシピ紹介
青魚に含まれるDHAやEPAは、熱に弱い性質があり、加熱すると溶け出してしまうのが難点です。
煮る・焼くなどの調理法では約8割、揚げ物の場合は約5割に減ってしまいます。そのため、効率よく摂りたい場合は、刺身やホイル焼きなどの調理法がおすすめです。
グラタンやシチューなど汁まで食べられる料理、フライやムニエルは衣をまぶして、脂の流出をおさえるのもよいです。
缶詰を使う際は、汁も残さず使いましょう。
サバのさっぱり煮
-
サバのさっぱり煮は、甘辛い味付けでごはんとの相性抜群です。
-
皮目に十字で切り込みを入れたサバの切り身2つに、熱湯をかけたあと、冷水にとって水気をきります。
-
一片分のしょうがを薄切りと千切りに分けて切り
-
フライパンに水とお酢を100mlずつ、しょうゆとみりんを各大さじ2、砂糖大さじ1、生姜の薄切りを入れて煮立てます。
-
落し蓋をして、弱めの中火で煮汁を回しかけながら10〜15分ほど煮たら出来上がりです。
-
皿に盛り付けたら、生姜の千切りをのせます。
まとめ
今回は青魚の種類と栄養素、食べるメリットについて解説しました。
オメガ3脂肪酸の一種、DHAとEPAを含む青魚は、お体の健康維持や等に関わりがあるとされ、食品でしか摂ることのできない必須脂肪酸です。
魚が苦手な方も、えごま油や亜麻仁油をサラダやみそ汁にかける、必要に応じてDHA&EPAサプリメントを活用するなど、DHAやEPAを賢く補ってみてください。

効率的にDHA・EPAを補給できるDHA・EPAサプリ
忙しい日常で魚を食べる時間がない方におすすめなのが、ダイケンバイオメディカルのDHA・EPAサプリ:DHA&EPA+ビタミンDです。
1日4粒で、950mgのDHAとEPA(1000mgのオメガ3)を簡単に摂取でき、高濃度なので余分な脂質を気にせず、純粋なオメガ3を補給できます。
さらに、124%という高い吸収率で、DHAとEPAがしっかりと体内に活用され、健康維持に必要な栄養素を効率よく届けます。
ビタミンDも配合されており、カルシウムの吸収を促進し、骨の形成を助けます。日常的食生活が不規則である方におすすめサプリメントです。











