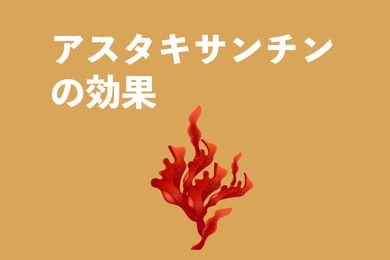DHAにはどのような効果があるのか、気になる方は多いのではないでしょうか。よく知られているDHAの効果は、脳の発達、認知機能の維持ですが、他には、目の健康や血流の改善にも効果があります。
また、DHAの抗炎症作用があるため、ドライアイや炎症性疾患の予防にも役立ちます。
この記事では、DHAの主な効果や健康上のメリットなどについて詳しくご紹介します。
DHA(ドコサヘキサエン酸)とは?

DHA(ドコサヘキサエン酸)とは、ヒトに欠かせない「必須脂肪酸」の1つで「不飽和脂肪酸」に属します。
不飽和脂肪酸は体内で合成ができないため、食べ物から摂取する必要があります。DHAは「オメガ3脂肪酸」と呼ばれる種類に分類されており、おもに魚に多く含まれています。
DHAは脳や目などのさまざまな場所に含まれており、胎児の脳の発達から、認知機能の維持や血流の改善まで、身体の健康にとって重要な役割を果たしているのです(1)。
DHAの効果
昔の話は、ご存知ですか。
イヌイット(エスキモー)の人々は、北極圏に住んでいるため、かつてはほとんど野菜を摂取せず、脂肪中心の食生活を送っていました。このような食習慣では、血栓症や肥満などの健康問題が懸念されることが予想されますが、彼らにはこれらの疾患が非常に少なかったとされています。
その理由として、研究者たちは「DHAとEPAを豊富に含む青魚やアザラシを常食していることが関係している」と結論づけています。
実際に、DHAはヒトのお体にとって、どのような効果とメリットがあるのでしょうか。
DHAは脳の発達や認知機能の維持に重要な役割を果たし、記憶力や集中力の改善にも効果があります。
目の健康にも良い影響を与え、ドライアイや目の不快感の改善が期待できます。DHAの効果は血流改善にも関与し、中性脂肪やコレステロールのバランスを整えることで、動脈硬化や高血圧の予防にも効果が期待できます。
また、抗炎症作用があり、炎症性疾患のリスク軽減にも役立ちます。ここでは具体的なDHAの効果について詳しく解説します。
DHAの効果1. 記憶力の改善

DHAは記憶力の向上が期待でき、短期記憶と長期記憶の両方によい影響を与えることが示されています(1)。
DHAは脳内の神経伝達を促進する作用や、細胞の保護などの役割があるとされています。(13)
-
脳細胞の保護
-
神経ネットワークの活性化
-
神経同士のやり取りの強化(脳神経間の情報伝達機能)
また、記憶を司っている「海馬」と呼ばれる脳内の組織に作用し、記憶力の維持・改善に関与するとされています(5)(6)。
そのため、そのような作用が記憶力の改善に寄与していると考えられています。
ただし、DHAの効果は個人差が大きく、どのような方でも作用が現れるわけではない点に注意しましょう。
DHAの効果2. 高齢者の認知機能の維持
DHAの摂取によって加齢による認知機能低下の予防につながるとされています。
DHAは脳の情報伝達機能をサポートすることとされています。DHAは記憶力の向上につながる点から、高齢者の認知機能の維持という役割も果たしているとされています。
実際に、DHAを摂取する頻度が多い方ほど、アルツハイマー型認知症の発症リスクが低くなりやすいという研究報告があります(1)。
とくに高齢者になると脳機能が衰え、認知症の発症リスクは徐々に高まるので、予防するにはDHAの摂取が重要といえるでしょう。
DHAの効果は個人差が大きいため、誰もが認知症の完全な予防につながるわけではありません。
しかし、DHAを含む栄養素を意識的に摂ることが、健康的な生活を送るための1つの要素となるのです。
DHAの効果3. 胎児と子どもの脳の発育

DHAは、胎児や子どもの脳の発育に好影響を与えるとされています。約82,000人の妊婦とその子どもの発達度合いを調査したところ、DHAを多く含む魚を食べる量が多いほど、発達が良好であることが示されています。
とくに「細かい運動」と「問題の解決能力」において、発達が遅れる子どもが少ないという結果が得られています(3)。
また、DHAの摂取によって出生体重の増加や、早産の減少がみられたという報告もあります(4)。
このように、妊娠中や授乳中の母親、そして成長期の子どもにとって、DHAの十分な摂取は重要といえるでしょう。
参考:DHA成分情報:働き、副作用と摂取方法【医師監修】
draft-DHAの脳機能、記憶力、認知機能の向上効果をエビデンスに基づいて解説
DHAの効果4. 集中力の維持

DHAには、集中力の維持をサポートする可能性があります。これは、DHAによる神経細胞の活性化や、抗炎症作用などによるものとされているのです。
実際に、軽度の認知症の高齢者に対してオメガ3脂肪酸(n-3系脂肪酸)を摂取したところ、記憶力だけでなく集中力の改善がみられたという報告があります(8)。
日々の食事やサプリメントでDHAを意識的に摂取すれば、仕事や勉強などでより高いパフォーマンスを発揮できる可能性があります。
DHAの効果5. 血中の中性脂肪の低下

中性脂肪の増加は血液がドロドロとなり、血流が悪くなる原因の1つです。DHAは血中の中性脂肪の低下や、コレステロールバランスの維持をサポートするとされています(9)。
他の研究により、DHAを含む魚肉ソーセージ(DHA 850 mg、EPA 200 mg)を1日1本、4週間摂取した結果、中性脂肪が高脂血症の範囲からほぼ正常範囲に低下する効果が示唆されました。(14)
DHAの効果6. 血流改善

DHAには血流を改善する効果があるとされており、これによりさまざまな健康上のメリットが期待できます。
DHAを摂取することで、中性脂肪やコレステロールが減少し、血流状態の改善につながるのです。
このように、DHAは脳や眼に対して効果があるだけでなく、血管の状態に対してもよい影響が出る可能性があります。
動脈硬化や高血圧などの血管に関する疾患を予防するためにも、DHAを意識的に摂取しましょう。
DHAの効果7. 抗炎症作用

DHAには抗炎症作用があるとされており、これによりさまざまな炎症性疾患のリスク軽減につながります。
実際に、DHAをはじめとしたオメガ3脂肪酸(n-3系脂肪酸)の摂取によって、潰瘍性大腸炎やクローン病といった炎症性の病気の改善が報告されています(10)。
このDHAの抗炎症作用によって、炎症性疾患の発症抑制だけでなく、長期的な健康維持にも重要な役割を果たしているのです。
日常的にDHAを含む食べ物を摂取することで、健康的な生活をサポートできるでしょう。
DHAの効果8. 目のケアとドライアイの改善

DHAは脳だけでなく、目の健康維持にもつながります。ドライアイの方に対して、オメガ3脂肪酸(n-3系脂肪酸)が含まれているサプリメントを使用したところ、症状の改善がみられたという報告があります(7)。
さらに、オメガ3脂肪酸の摂取によって花粉症による目の不快感への対策としても注目されているのです。
これらはDHAに備わっている、抗炎症作用や目の機能の安定作用によって起こるとされています。
普段からドライアイや目のかゆみなどに悩まされている方は、DHAの積極的な摂取を検討してみましょう。
DHAの1日推奨摂取量
DHAの推奨摂取量は、年齢や性別によって異なります。DHAを含めたオメガ3脂肪酸(n-3系脂肪酸)の摂取量の目安は、以下のとおりです(11)。
-
子ども(1〜2歳・男女):約0.7g/日
-
成人男性:約2.2~2.3g/日
-
成人女性:1.7〜2.0g/日
-
妊婦:約1.7g/日
DHAを摂り入れる際は、これらの摂取量を意識しておきましょう。
DHAのおすすめ摂取方法

DHAを効果的に摂取するには、おもに食事からの摂取とサプリメントの利用の2つの方法があります。
食事からのDHA摂取源としておすすめなのが、マグロやサバなどの魚介類です。先ほどの例で解説したように、魚介類には多くのDHAが含まれているため、意識的に食卓に取り入れるとよいでしょう。
食事からのDHA摂取源:
青魚の種類は?青魚の栄養素とメリットをご紹介
DHAが豊富な魚と食品:美味しくてDHAが多い魚の調理方法を紹介【管理栄養士執筆】
DHAが多い食品:青魚
端場愛管理栄養士によると、DHAが豊富な食材と言えば、やはり魚です。
「魚を食べると頭が良くなる」という言葉が示すように、魚に含まれるDHAは脳の働きや情報伝達をサポートし、健康維持に欠かせません。DHA(ドコサヘキサエン酸)は体内で合成できない必須脂肪酸であり、食事から摂取しなければ不足してしまうこともあります。
特にDHAを豊富に含む魚は、青魚や脂の多い部位が特徴です。アンコウの肝やトロの部分がその代表で、DHAが高い含有量を誇ります。
DHAが豊富な生魚のランキング

|
食品 |
DHA含有量(100gあたり) |
|
|
1位 |
アンコウ(肝) |
5100mg |
|
2位 |
ミナミマグロ(トロ部分) |
4000mg |
|
3位 |
クロマグロ(トロ部分) |
3200mg |
|
4位 |
サバ(生) |
2600mg |
|
5位 |
サンマ(皮なし・生) |
2100mg |
サバやサンマ、マグロなどもDHAを効率よく摂取できる魚としておすすめです。さらに、DHAを多く摂取するためには、刺身や焼き魚など、調理方法にも注意を払いましょう。脂質が溶け出さないシンプルな調理法が、DHAの摂取量を最大化する秘訣です。
現代の食生活では、魚離れが進んでおり、その結果、DHA不足が懸念されています。
しかし、DHAを積極的に摂取することで、健康を守り、生活習慣病の予防にもつながります。魚を日常的に取り入れ、DHAの効果を最大限に活用しましょう。
DHAサプリの活用
一方で、サプリメントによるDHAの摂取も選択肢の1つです。サプリメントのメリットは、魚を食べる機会が少ない方や、苦手な方でも手軽にDHAを摂取できる点です。
また、サプリメントは含有量が明確なため、必要な量を正確に摂取できます。
ただし、DHAサプリメントを選ぶ際は、DHAの含有量、濃度や品質(酸化、精製方法など)に注意しましょう。
過剰摂取は心房細動という不整脈の発症リスクにもつながるので、推奨量を守った摂取を心がけてください(12)。
DHA・EPAサプリメント飲むタイミングは寝る前?朝?エビデンスに基づいて効果的な飲むタイミングを解説
DHA・EPAサプリ効果なしの5つの原因は?効果を実感できない原因を説明【医師監修】
日々の生活におけるDHA摂取の重要性を知っておこう
DHAは脳の発達や認知機能の向上、目の健康維持など、幅広い効果が期待できる栄養素です。
とくに胎児や子どもの脳の発育に欠かせないため、妊婦や子育て中の方は意識的に摂取することが大切です。
また記憶力や集中力の改善、血流改善、抗炎症作用など、成人にとってもメリットが多いといえます。DHAを摂取するためには、魚介類を積極的に食べるほか、DHAサプリメントの利用もおすすめです。
ぜひこの記事を参考に、DHAを摂取して毎日の健康作りに役立ててみましょう。