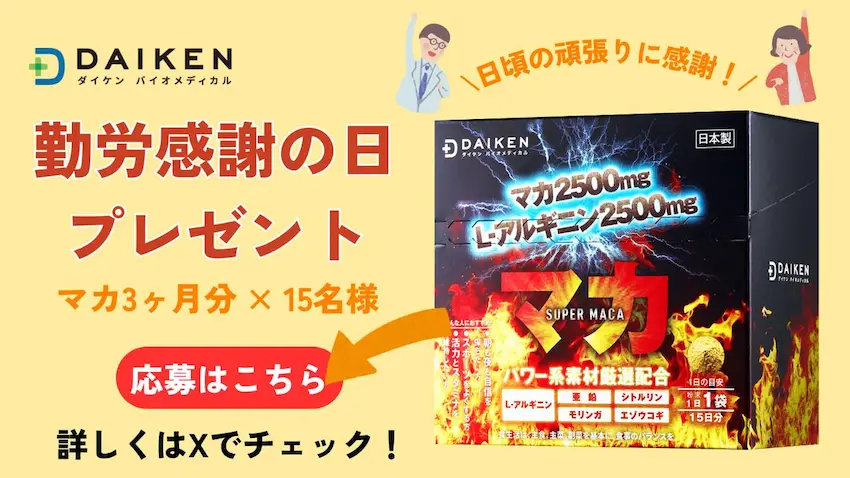亜鉛は人体に欠かせない微量ミネラルであり、体内で多くの代謝に関与しています。
亜鉛と聞くと、滋養強壮効果や男性向けのイメージが強い栄養素だと考えがちですが、実際は女性にとってもお肌の若さや美しさ、健康にも欠かせない重要な栄養素であり、子供たちの成長と発育にも必須の栄養素です。今回は亜鉛の効果とメリット、そして安全かつ効果的な摂取方法について紹介します!
亜鉛とは?
亜鉛の概要
亜鉛は、鉄に次いで重要だと認識されている微量ミネラルです(1)。
微量ミネラルとは、体内にわずかしか存在しないにも関わらず、体にとって非常に重要な役割を果たす必須ミネラルを指す言葉で、1日の摂取量が100 mg未満の必須ミネラルを微量ミネラルと分類することもあります(2)。
実際に、亜鉛は日本人の体内には約2gしか存在しませんが、核酸やたんぱく質の合成に関与する酵素をはじめとした、多くのたんぱく質の構成成分として機能するとともに、血糖調節ホルモンであるインスリンの構成成分等として重要な働きをしています(3)。
また、亜鉛は前立腺や精子に多く存在し、生殖機能の維持においても重要です。亜鉛はその働きから、新陳代謝、生理機能の調整、免疫力の向上など、非常に多くの健康上の役割を果たす栄養素です。
亜鉛が不足するとどうなる?
亜鉛が不足すると、小児では成長障害や皮膚炎が起こり、成人でも貧血、皮膚の不調、粘膜、血球、肝臓等の再生不良や味覚障害、嗅覚障害が起こるとともに、免疫たんぱくの合成能が低下することが知られて、老若男女の健康を脅かす可能性があります(3)。
亜鉛が欠乏することで起こる疾病(亜鉛欠乏症)が広く認識され始めたのは、1961年にあるイラン人の21歳男性が貧血や性腺機能低下症を起こしたことがきっかけとされています(1)。
この男性は当時パンやじゃがいも、牛乳のみで生活しており、治療のなかで亜鉛サプリメントを投与したところ回復しました。その後の研究でこれらの症状は亜鉛不足が原因であると分かりました。
それ以降、亜鉛への関心が非常に高まり、今では栄養学や医学でその重要性は確立されています。
現在では、厚生労働省により、「国民の栄養摂取の状況からみてその欠乏が国民の健康の保持増進に影響を与えているものとして厚生労働省令で定める栄養素」のなかに亜鉛が指定されており、亜鉛は日常的な食事だけで十分に摂取することが難しい栄養素とされています(3)。適切な量の亜鉛を摂取する必要性が高いと考えられています。
亜鉛の10つの効果
さまざまな研究により、亜鉛には多くの重要な効能があり、体内の正常な機能を維持し、多くの生理機能を整える働きをすることが分かっています。亜鉛の働きをまとめると、以下のようになります。
亜鉛の効果1. さまざまな酵素を含むたんぱく質の成分となる
亜鉛は、体内でさまざまな酵素を含むたんぱく質と結合し、その働きと構造を維持する重要な働きをしていることが知られています(4)。
そのため、亜鉛を適切に摂取することは体の構造を維持する重要な意味を持ちます。
亜鉛の効果2. エネルギー、糖、たんぱく質、核酸の正常な代謝を維持する
亜鉛はDNA生成やRNA転写などにも深く関わり、細胞分裂やたんぱく質生成にも重要な物質であることが知られています(5)。
また、亜鉛は糖を代謝してエネルギーにする役割を担うインスリンを助ける働きもするため、エネルギーや糖の代謝においても重要な物質だと考えられています(6)。
亜鉛の効果3. 皮膚組織のたんぱく質を生成し、お肌の健康と若々しさを保つ
亜鉛はたんぱく質の生成にも重要な役割を果たすため、亜鉛を適切に摂取することは健康的な肌を保つことにも繋がります。
実際に、亜鉛欠乏症の主な症状として皮膚炎が「日本人の食事摂取基準(2020年版)」に記載されており、その重要性がうかがえます(3)。
亜鉛の効果4. 正常な味覚と食欲を維持する
同様に、亜鉛欠乏症の主な症状には味覚障害も挙げられています(4)。
このことから、味覚や食欲を保つ意味でも亜鉛は重要な役割を果たしていると考えられています。
亜鉛の効果5. 成長期の発育を促進する
亜鉛はたんぱく質の生成を促すだけでなく、成長ホルモンの働きにも深く関わり、特に成長期に十分な発育をする上で非常に重要な役割を果たすことも報告されています(7)。
子供に対しても亜鉛不足は注意する必要があると考えられています。
亜鉛の効果6. 赤ちゃんの成長
妊婦や授乳婦の方々にとって、亜鉛の摂取により赤ちゃんの成長を助ける働きがあるため、非常に重要とされています。
「日本人の亜鉛摂取基準量」でも、妊婦の方や授乳婦の方は追加で摂取する量が定められています(3)。
亜鉛の効果7. 生殖機能のサポート
亜鉛はテストステロン(男性ホルモン)の合成と調整に重要な役割を担っていると示唆されていますので、亜鉛は男性の精力剤として非常によく知られております。実際に亜鉛は精子の生成や前立腺機能を促進する効能が報告されています(8)。
亜鉛の効果8. 免疫力、抗酸化力の向上を助ける
亜鉛は、免疫系の異常や炎症反応の原因となるIL-6などの炎症性サイトカインの過剰生成を抑制するほか、老化の原因や動脈硬化などの疾患リスクとなる活性酸素種の過剰生成を抑制することが報告されており、免疫力や抗酸化力の向上の効果があると示唆されています(9)。
亜鉛の効果9. 男性型脱毛症(AGA)の予防
健康的な毛髪には正常な毛包の形成が重要です。亜鉛は毛包の回復や老化を予防する働きがあるため、男性型脱毛症(AGA)の予防効果が期待されています。
亜鉛の効果10. 運動機能の向上
亜鉛は筋力や運動機能を向上させ、筋肉の修復に重要な役割を果たします。運動後の筋肉痛を和らげる効果もあり、亜鉛不足が筋力低下を引き起こすことがあります。さらに、亜鉛はエネルギー産生をサポートします。
また、テストステロンとの関連性もあり、亜鉛不足が疲労や集中力低下を招く可能性があります。
参考:男性に亜鉛の4つの効果を解説!精力や持久力・脱毛の悩みとおさらばしよう
亜鉛を豊富に含む食品ランキングTOP10
亜鉛不足の状態がある場合、亜鉛含有量の高い食品を選ぶことをおすすめします。以下の表1で、亜鉛含有量の多い食品トップ10をご紹介いたします!
表1. 亜鉛含有量の多い食品トップ10(10)

|
順位 |
食品名 |
可食部100gに含まれる |
|
1位 |
牡蠣(水煮) |
18.0 |
|
2位 |
小麦はいが |
16.0 |
|
3位 |
牡蠣(生) |
14.0 |
|
4位 |
カツオ類(塩辛) |
12.0 |
|
5位 |
パプリカ(香辛料粉末) |
10.0 |
|
6位 |
ボラ(カラスミ) |
9.3 |
|
7位 |
うし(ビーフジャーキー) |
8.8 |
|
8位 |
ぶた(スモークレバー) |
8.7 |
|
9位 |
ごま鯖(鯖節) |
8.4 |
|
10位 |
カタクチイワシ(田作り) |
7.9 |
ただし、食材から亜鉛を補給する際には、食材に含まれる高コレステロールや高脂肪にも注意が必要であり、亜鉛含有量の高い食品に偏った食事はかえって体に負担をかける可能性があります。
亜鉛を含む健康食品も摂取する一つの方法として取り入れることで、体に大きな負担をかけずに亜鉛を摂取することができます。
例えば、体力と精力を向上させる効能が報告されているマカは、乾燥のマカ粉末100gあたりに亜鉛を3.8 mg含むほか、炭水化物、ビタミン、たんぱく質の必須栄養素や、抗酸化作用が報告されているマカ特有の成分マカミドなど豊富な栄養素が含まれており、忍容性も高い食品であるため、亜鉛サプリメントと組み合わせることも有効的です(11)。
参考:マカとは?マカの働き・栄養素・色の違いと食べ方を紹介
亜鉛が不足しやすい6種類の人とは?

厚生労働省が「日本人の食事摂取基準(2020年版)」で定めるように、健康を維持し、生理機能を整えるためには、性別や年齢を問わず適量の亜鉛を摂取する必要があります(3)。
そのなかでも、多くの研究や報告を踏まえて、特に以下の5種類の人々は、亜鉛を意識的に摂取したほうが良いとされています。
1. 高齢の方
高齢の方は食事パターンが制限され、栄養バランスの偏りがあることが多いほか、加齢に伴う腸管吸収の変化、不十分な咀嚼、心理社会的要因、薬物相互作用などで亜鉛を十分に摂取できないことが増えることが示唆されています(12)。
2. 妊活中の方や赤ちゃんを授かった妊婦の方
亜鉛は生理機能を整えたり、赤ちゃんの成長をサポートする働きをしてくれます(3)(8)。
3.子供や若い方
健康の維持と成長や発育に亜鉛が重要な栄養素であることが知られています(3)。
4. 傷病者や手術を受けた患者さん
亜鉛は皮膚組織のタンパク質合成を助けるほか、免疫系の維持にも役立つため重要となります(9)。
5. ベジタリアンの方
野菜や果物は含まれる亜鉛量が比較的少ないため、ベジタリアンの方が特に注意すべき栄養素として鉄と並んで亜鉛が挙げられます(12)。
6. コンビニ食や加工食品摂取が多い方
市販の加工食品には様々な食品添加物が使用されています。その中に亜鉛キレート作用を持つ添加物(亜鉛キレート剤)は、消化管から亜鉛の吸収が悪くなっていることが報告されています(13)。
亜鉛はどのように摂取すれば良い?1日の摂取量は?
厚生労働省が定める「日本人の食事摂取基準(2020年版)」に基づき、亜鉛の摂取目安量や耐用上限量は年齢によって細かく規定されており、表2のように定められています(3)。
上記の通り、赤ちゃんの成長を促進するために、妊婦の方や授乳婦の方には、1日あたりの摂取推奨量にそれぞれ付加量が定められているので、注意が必要です。
表2. 日本人の亜鉛の摂取基準(mg / 日)(3)
|
性別 |
男性 |
女性 |
||||
|
年齢等 |
推奨量 |
目安量 |
耐容上限量 |
推奨量 |
目安量 |
耐容上限量 |
|
0~5(月) |
― |
2 |
― |
― |
2 |
― |
|
6~11(月) |
― |
3 |
― |
― |
3 |
― |
|
1~2(歳) |
3 |
― |
― |
3 |
― |
― |
|
3~5(歳) |
4 |
― |
― |
3 |
― |
― |
|
6~7(歳) |
5 |
― |
― |
4 |
― |
― |
|
8~9(歳) |
6 |
― |
― |
5 |
― |
― |
|
10~11(歳) |
7 |
― |
― |
6 |
― |
― |
|
12~14(歳) |
10 |
― |
― |
8 |
― |
― |
|
15~17(歳) |
12 |
― |
― |
8 |
― |
― |
|
18~29(歳) |
11 |
― |
40 |
8 |
― |
35 |
|
30~49(歳) |
11 |
― |
45 |
8 |
― |
35 |
|
50~64(歳) |
11 |
― |
45 |
8 |
― |
35 |
|
65~74(歳) |
11 |
― |
40 |
8 |
― |
35 |
|
75以上(歳) |
10 |
― |
40 |
8 |
― |
30 |
|
妊婦(付加量) |
|
+2 |
― |
― |
||
|
授乳婦(付加量) |
+4 |
― |
― |
|||
亜鉛の副作用は?
表2の通り、30歳〜64歳の場合の亜鉛の耐用上限量は、男性で1日45 mg、女性で1日35 mgとされているため、この上限を守って長期的に摂取すれば安全だと考えられています(3)。
亜鉛への反応は個人差も当然あるため、高用量の亜鉛を補給した場合、食欲不振、吐き気、嘔吐、下痢などの症状が現れる可能性がありますが、これらの症状は摂取をやめれば緩和されると考えられます。
亜鉛の補給は徐々に継続して行うことで、気力を持続させ、より健康になる助けになるでしょう!
参考:男性に亜鉛の4つの効果を解説!精力や持久力・脱毛の悩みとおさらばしよう
アルギニンとは?アルギニンの10つ効果と副作用【5分でわかる】
シトルリンの効果:ED改善と運動パフォーマンス向上の仕組みを解説